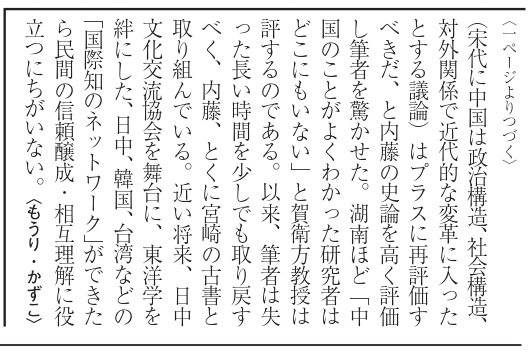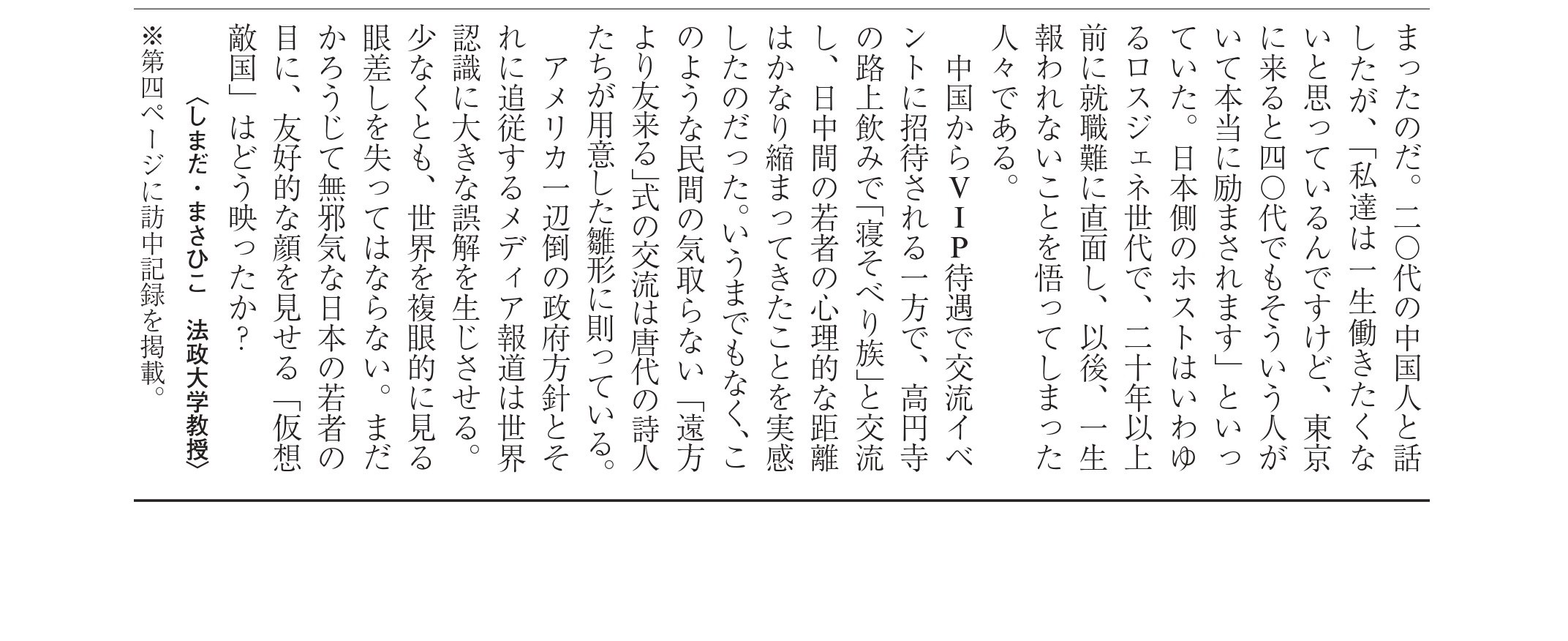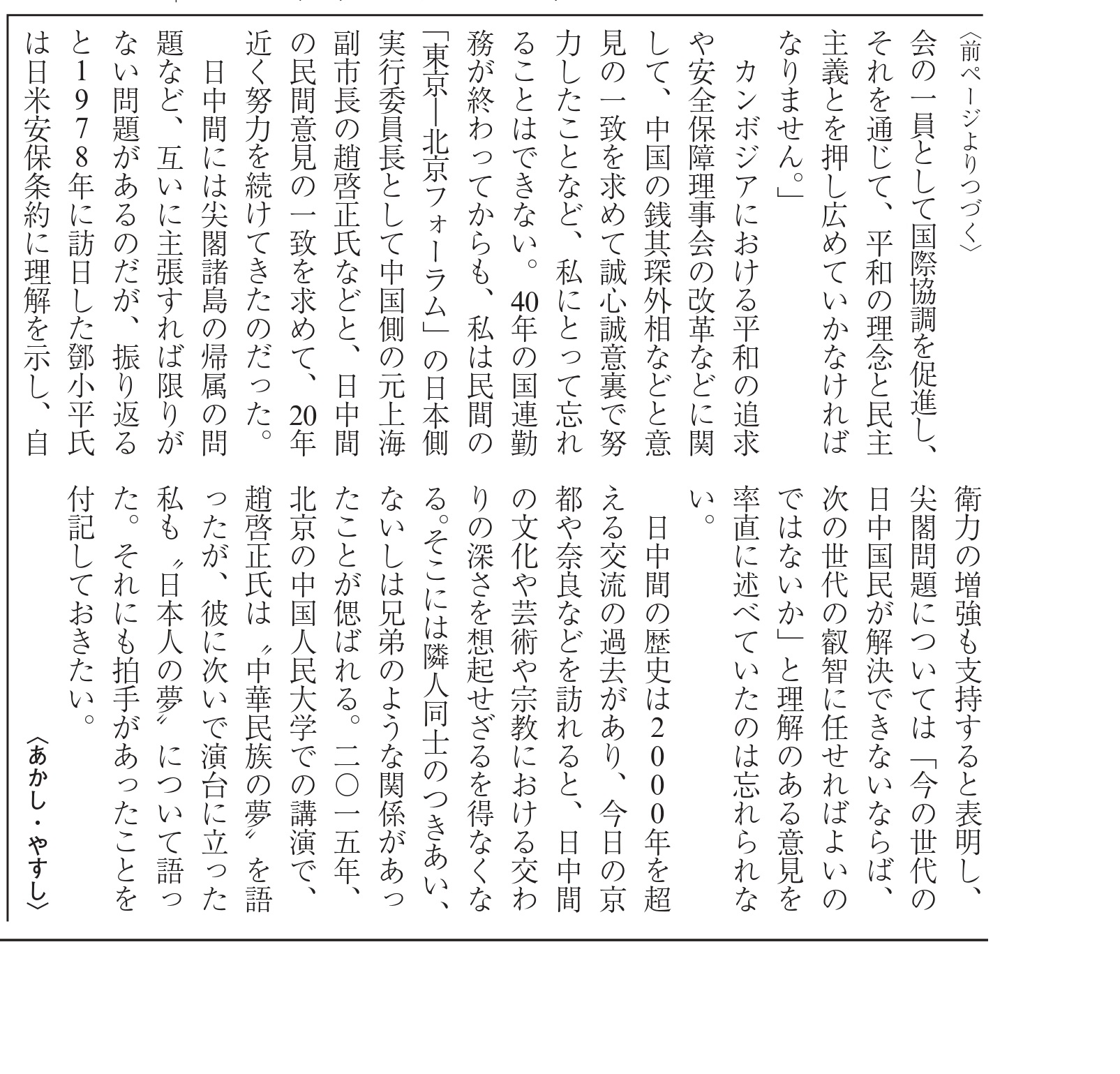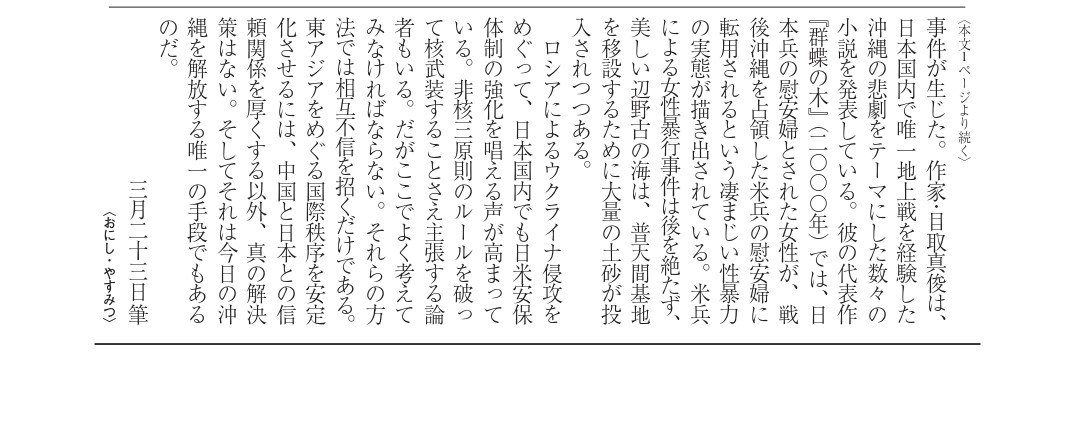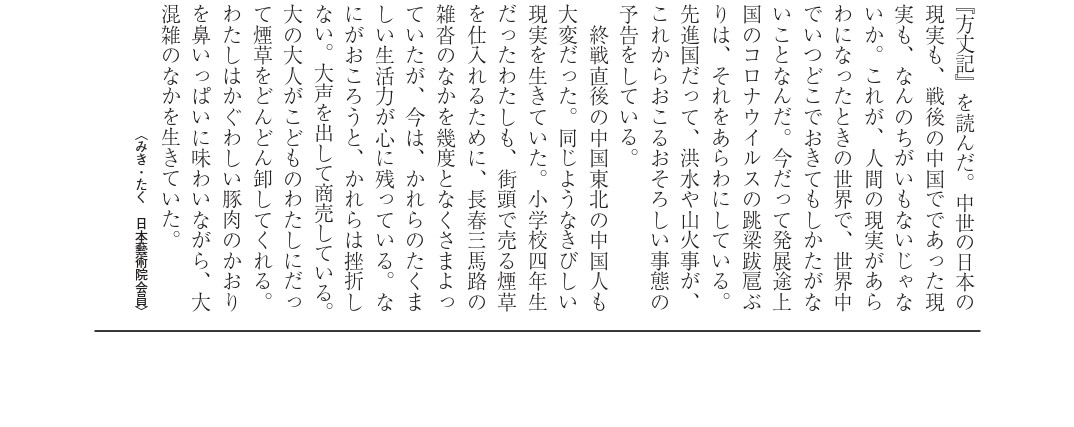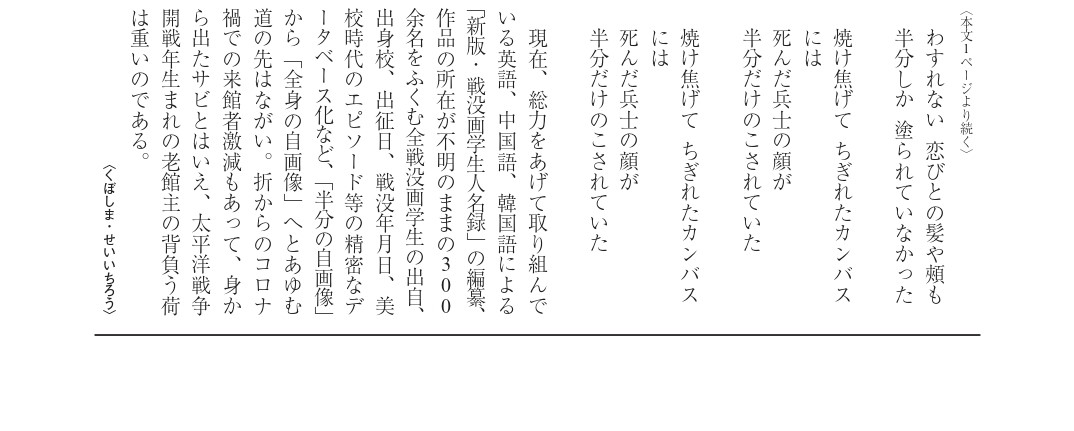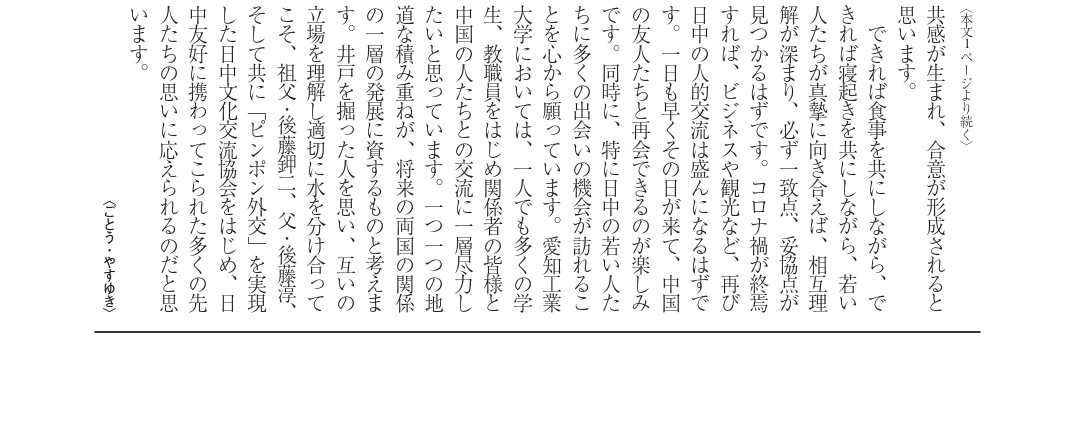歌に国境はなし ー音楽著作権交流を重ねて
一般社団法人日本音楽著作権協会会長、作曲家
弦哲也
陰影深し「桃花源」 二十年ぶりの中国再訪
日本中国文化交流協会常任委員、無言館館主、作家
窪島誠一郎
上海にて余秋雨氏と久闊を叙す(No.935 2024.2.1より)
日本中国文化交流協会常任委員、ジャーナリスト
加藤千洋
対面交流の真価(No.934 2024.1.1より)
日本中国文化交流協会会長、作家
黑井千次
「日中友好」だった半世紀、これからの半世紀は?(No.933 2023.12.1より)
早稲田大学名誉教授
毛利和子
三年ぶりの交流雑感(No.932 2023.11.1より)
日本中国文化交流協会常任委員、作家
島田雅彦
今に通じる内山完造の精神(No.931 2023.10.1より)
内山書店会長
内山籬
今年(癸卯歳)の書初め(No.930 2023.9.1より)
日本中国文化交流協会常任委員、書家
石川九楊
日中交流の長さと厚み(No.929 2023.8.1より)
元国連事務次長
明石康
エンタメ交流を一層盛んに(No.928 2023.7.1より)
吉本興業ホールディングス株式会社代表取締役社長
岡本昭彦
中国工筆画師生訪日団を歓迎する(No.927 2023.6.1より)
日本中国文化交流協会副会長
日本画家
田渕俊夫
ぼくと中国(No.926 2023.5.1より)
小澤昔ばなし研究所所長
小澤俊夫
日中関係ー昔と今とー(No.925 2023.4.1より)
元駐中国大使
谷野作太郎
静嘉堂と中国の宝物(No.924 2023.3.1より)
静嘉堂文庫美術館館長
河野元昭
「共生世界」済南国際ビエンナーレ(No.923 2023.2.1より)
川崎氏岡本太郎美術館館長
土方明司
2023年 年頭にあたって(No.922 2023.1.1より)
日本中国文化交流協会副会長・理事長
俳優
栗原小巻
古代の記憶がつなぐもの(No.921 2022.12.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
作家
中上紀
兵馬俑と古代中国展の開催(No.920 2022.11.1より)
学習院大学名誉教授
鶴間和幸
「手触り」の交流を守ろう(No.919 2022.10.1より)
日本中国文化交流協会副会長
洋画家
入江観
日中国交正常化五十周年に際して
終着点のない道の途上で(No.918 2022.9.1より)
日本中国文化交流協会会長
作家
黑井千次
問いかける眼―雪舟「慧可断臂図」<絵と文>(No.918 2022.9.1より)
水上玲
敗戦後、一変した日本が復興再建に懸命の頃生れ育った団塊世代の私も、「玄冬」の老境を迎え、パンデミック体験もさながら時々刻々変容する内外情勢に戸惑う昨今である。
バベルの塔ならぬバブルの塔など有象無象を造り続けて、異常気象・環境破壊をもたらす現代。コロナという神の啓示が下りマスク生活の中、人流・物流の循環が止まり経済に変調をきたし、その上ロシア・ウクライナの戦争状態となり人間の叡智はどこへやら、次世代へのバトンタッチも心もとない限りだが、一方ではもう地球を離れて宇宙生活の夢の時代の実現化へ・・・
さて、この三年間暫し立ち止り、私の中国文化との出会いを辿ってみた。遡れば一九五七年の小学生の頃、佐世保で開業医の父に、時折り、床の間の掛軸の前に妹と正座させられ、軸の漢文を教わり暗誦させられたこと。
それは当時、父が敬愛していた親和銀行頭取で代議士の北村徳太郎氏直筆の贈呈の魯迅の句であったが難解ながらリズムで覚えた。父に届く同氏の外遊先の西欧諸国からの絵葉書の見聞記には戦後日本の有り方や後世に希望を託すものであり、父には世界を身近に感じる貴重な資料であったろう。二十代で軍医候補生から軍医として朝鮮・満州・日本を往来し、終戦はフィリピン山中で生死の逃避行だったらしい。引揚後は医局に戻りやがて新地の佐世保で開業、十年後の春早世した。
時は移り、一九八二年から三年間夫の赴任先のバンコク駐在時期に、私は華僑の著名な水墨画家の林耀老師の下へ入門し、画仙紙に墨の濃淡滲み掠れ、線点面の用筆用墨で織りなす山水画・花鳥画が瞬く間に生命が宿る美しさに魅せられ、臨模練習の四苦八苦が始まる。
帰国後、一九九三年から現在まで馬驍水墨画会に所属し、気韻生動・骨法用筆等の謝赫の六法や芥子園画伝の基礎画論を学び、さらに現代的テーマへの応用と構図を考える過程を馬驍先生と王荻地先生に教わる。また大竹卓民先生の教室では日中の美術史や日本画と水墨画の違い、水墨画の紙の変遷を知り、工筆画の絹布への模写や、新山水と写意画技法等も幅広く勉強した。又、山水画の本場中国への写生を兼ねての名峰旧跡、美術館博物館巡りや五山を始め北から南まで先生方との旅は十数回に及び、その風土や精神を表すには、モノクロの抽象世界と納得。黄山で湧雲の絶えまない静動に太極拳の呼吸法だと得心、不動の山に生動の雲水は上虚下実の様であった。
二〇〇九年に、馬・王両先生二人展が杭州の唐雲美術館で開催の折、紹興の魯迅故里を訪れ、その記念館の入口で出迎えてくれたのがあの魯迅の句の石碑であった。佇んだまま懐旧の思いで口吟し、父がここへ連れてきてくれたのではと歳月はその延長線上にあると再認識し、魯迅と父が重なって見えた。
「横眉冷對千夫指俯首甘為孺子牛」
旅は時空を超え意味深く感慨無量となった。
最期に願望達成の出来事
水墨画における気韻生動の「気」とは何かを知りたくて、導引養生気功を張玉潔先生に長年習い、また、中国文化センターで初心者向けの少林寺武術気功の秦西平先生の指導を受け静功と武術の動功の違いを学んだ。天地人の気が宇宙・自然界と人間の体内のエネルギーと関連している東洋思想・哲学が陰陽五行説に基き、見えない気は万物を司る大気水蒸気であり人間はその中の一部であるという認識。偶々先生が資格認定を取得なされた、嵩山少林寺総本山での武術体験留学ツアーに五年前に誘われ、夢に見ていた、慧可断臂図の達摩洞にも登り瞑想もするとの内容に心弾んだ。
禅宗の初祖達摩大師が中国に渡り迫害を受けながらも面壁九年の修業をした場所でもあり雪舟晩年作のこの人物画は緊張感と異様なエネルギーを感じさせる唯一の作品。その絵の洞窟迄の二時間の山登りは苦しかったが、山上の達摩洞で像を囲み十分の瞑想中一瞬、冷んやりした空気が漂い澄んだ気持になった。
雪舟は二年間の臨済禅の画僧として修業を積み、帰国後は、山水長巻等数々の名品を描き続けたが、人物画のこの作品は雪舟の達摩大師への畏敬の念のオマージュであり、胸中に温めていた最高の一作を遺したのであろう。
大師の法衣の淡墨の太い篆書体の線は強靭な精神を表す雪舟の思いの深さの一気呵成の運筆で描き切り、白地の留白は、瞑想の段階では「無」より高い境地の「空」に達した達摩大師の心を表現したのではないか。
また緊張感の慧可断臂図の精密描写とはうらはらに重層的奥行のある岩襞に剽軽かつ奇妙な笑みを含んだ大きな岩穴は、達摩大師の「心眼」であり鋭い眼は見る者への「今」を問いかけている気がしてならない。
〈みずかみ・れい 水墨画家〉
「兵馬俑と古代中国 ~秦漢文明の遺産~」開催にあたって
「里耶秦簡」展示の意義(No.917 2022.8.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
茨城大学名誉教授
茂木雅博
紀の川の流れとともに 有吉佐和子の文学(No.916 2022.7.1より)
日本ペンクラブ理事
日本旅行作家協会会長
下重暁子
宇宙洪荒(No.915 2022.6.1より)
作家
浅田次郎
ケニアからの視座(No.914 2022.5.1より)
法政大学名誉教授・前総長
田中優子
沖縄返還50年を前に――ロシアによるウクライナ侵攻を憂う(No.913 2022.4.1より)
三重大学理事・副学長
尾西康充
他者への想像力を豊かに
ー岩波ホール閉館にあたって(No.912 2022.3.1より)
岩波ホール支配人
岩波律子
伝えたいこと(No.911 2022.2.1より)
日本中国文化交流協会顧問
茶道裏千家第十五代・前家元
千 玄室
途中の充実のために(No.910 2022.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
作家
黑 井 千 次
大きな懐 中国の“空気”(No.909 2021.12.1より)
俳優
山 本 亘
中国東北で終戦直後を生きた(No.908 2021.11.1より)
詩人、作家
三 木 卓
「無言館」開館25年ーー「半分の自画像」のこと
(No.907 2021.10.1より)
「無言館」館主、作家
窪 島 誠 一 郎
「ピンポン外交」50周年を迎えて
(No.906 2021.9.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
愛知工業大学学長
後 藤 泰 之
大きく変わった局面の中で大切にしたい原点と姿勢
(No.905 2021.8.1より)
前岩波書店社長
岡 本 厚
シルクロード世代の文化交流に学ぶ
(No.904 2021.7.1より)
中央大学文学部教授
榎 本 泰 子
團伊玖磨先生を憶う―逝去20年 中国・福建でシンポジウム(No.903 2021.6.1より)
日本中国文化交流協会理事
声楽家
永 井 和 子
 饅頭を尋ねて成都へ行く(No.902 2021.5.1より)
饅頭を尋ねて成都へ行く(No.902 2021.5.1より)
作家
嵐 山 光 三 郎
忘れられない仲間(No.901 2021.4.1より)
河北新報社代表取締役社長
日本中国文化交流協会顧問
一 力 雅 彦
創立六十五周年と本誌創刊九百号に寄せて(No.900 2021.3.23より)
日本中国文化交流協会会長
作家
黑 井 千 次
絵本が繋いだ中国と韓国との交流(No.899 2021.2.1より)
絵本作家
浜 田 桂 子
新年を迎えて(No.898 2021.1.1より)
日本中国文化交流協会副会長・理事長
作曲家
池 辺 晋 一 郎
奇跡の生還から38年(No.897 2020.12.1より)
登山家
松 田 宏 也
疫病と都市史(No.896 2020.11.1より)
青山学院大学教授
伊 藤 毅
雌伏の中で思うこと(No.895 2020.10.1より)
日本中国文化交流協会副会長
洋画家
入 江 観
新型コロナ世界と日中交流(No.894 2020.9.1より)
日本中国文化交流協会顧問
東大寺長老
森 本 公 誠
劇団民藝70周年を迎えて
―演劇の力を届けたい (No.893 2020.8.1より)
俳優、劇団民藝代表
奈 良 岡 朋 子
コロナ禍から感じること
―未来を見据える重要性 (No.892 2020.7.1より)
日本中国文化交流協会顧問
KADOKAWA取締役会長
角 川 歴 彦
一日も早い復興を願う (No.891 2020.6.1より)
日本中国文化交流協会副会長
二十六世観世宗家
観 世 清 和
未来医学研究会の夢と信念~日中交流による未来医療の実現(No.890 2020.5.1より)
未来医学研究会会長、東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長
清 水 達 也
都市文化を通じた日中交流 (No.889 2020.4.1より)
日本中国文化交流協会評議員
建築家
團 紀 彦
「悪疫年(プレイグイヤー)」2020(No.888 2020.3.1より)
日本中国文化交流協会理事
日本女子大学教授
成 田 龍 一
日中友好を天皇制から考える (No.887 2020.2.1より)
日本中国文化交流協会理事
放送大学教授
原 武 史

年頭に当って
(No.886 2020.1.1より)
日本中国文化交流協会副会長
俳優
栗 原 小 巻
中国の国務院よりお招きを受けて、2019年9月30日、10月1日、中国建国70周年の式典に、参加致しました。
30日の夜は、人民大会堂での晩餐会が開催され、習近平国家主席よりこれまでの中国の歩み、これからの展望が、語られました。
翌1日は、天安門広場での、日本では報道されなかった文化パレード、日本でも報道された軍事パレードを、見学致しました。
「人民解放軍は1948年11月『遼瀋戦役』で勝利を収め、東北全域を解放した。この年の12月30日に、毛沢東氏が、新華社に「革命を最後まで進めよ!」との1949年の新年の祝辞を書き示して、全国の人心を大いに奮い立たせた」(劉徳有『時は流れて』より引用)
平和は、座して待つのではなく勝ち取るという郭沫若氏の言葉も、この書では、紹介されています。
わたくしは、パレードを見ながら、一人の日本女性に思いを馳せました。それは、1939年、黒煙が立ちこめる、爆撃のさ中、中国にて、重慶、上海から、祖国日本に向けて反戦を叫んだ、勇気と信念の女性、長谷川テルです。
初の日中合作ドラマで、主演の長谷川テルを演じた時、私は、平和の尊さを身に染みて感じました。
戦争は、あまりにも多くの犠牲を生みます。
中国の悲しみ、そして、日本の悲しみ。
私は、日本全国を、演劇で50年近く巡演しています。広島、長崎では、あの日を想像すると胸がしめつけられます。
先ほど引用した、『時は流れて』の著者、劉徳有先生は、わたくしが最も尊敬する先輩であり、親しい友人の一人です。
先生は、この書の序文で、平和・発展・友好・協力が日中の重要な言葉だと記されています。
昨年夏、私は、長谷川テルさんの遺児、作家の長谷川暁子さん、日中文化交流に生涯尽くされている横川健さんと奥様、日中映画交流史を書かれたジャーナリスト劉文兵氏の5名で長谷川テルさんを偲んで、ジャムスに行き、その墓所で深く頭をたれ、花を手向け、手を合わせました。
長谷川テルさんの平和への思いを、少しでも次の世代に伝えたい、それが私の願いです。
日中映画祭などを通じて、微力ですが、文化交流の中で平和の尊さを訴えています。
ジャムスのあと北京で、劉徳有先生と再会し、「皆さんの代表団の平和の精神を重く受けとめる」との発言をいただき、感動しました。
建国70周年―。
朝鮮半島は、いまだに、戦争状態であるという事は、昨今、メディアを通じて多く語られています。
アジアは緊張状態です。それは、誰もが認めるところです。
私は、一昨年『松井須磨子』を北京菊隠劇場で上演しました。劉文兵氏の字幕翻訳を始め、中国のスタッフの皆さんが協力して下さいました。
友好、協力、重い言葉です。
中国の建国70周年のメッセージ、文化パレード、文化の祭典を、是非、世界が受け止めてほしい、軍事ではなく、外交こそが平和と発展への道です。
そして文化芸術に携わる我々は、劉徳有先生のご提言された四つの重要な言葉、平和、発展、友好、協力をより深く、深く受け止めたい。
2019年9月30日、10月1日、建国70周年式典に参加して、今後の日中文化交流協会の果たすべき役割の大切さを、強く感じています。
私は10年間、ユネスコのスペシャル・アドバイザーとして、東アジア子供芸術祭で、東アジアの子供たちに、人類の尊厳・平等・相互の尊重を、詩に託し、何度も語りかけてきました。
緊張状態にある、東アジアの平和を、座して待つのではなく、文化芸術の力で勝ち取りたい。
念頭に当って、今、思うところです。
<くりはら・こまき>
上海での「鑑真和上と唐招提寺
東山魁夷作品展」開催を慶ぶ
(No.885 2019.12.1より)
律宗管長
唐招提寺第八十八世長老
西 山 明 彦
今般、中華人民共和国建国七十周年と日中文化交流協定締結四十周年を記念して、中国・上海博物館に於いて「鑑真和上と唐招提寺東山魁夷作品展」が開催されます。期間は、本年十二月十七日より明年二月十六日の期限で、唐招提寺御影堂障壁画六十八面総てと寺宝である国宝「金亀舎利塔」、重要文化財「東征伝絵巻」、重要文化財「勅額」が出展されます。御影堂障壁画の総てが、海外に出るのは此度が初めての事となります。
十年間に及ぶ画伯の事績をあらましご紹介いたしますと、
・昭和四十六年(六十三歳)七月、唐招提寺御影堂障壁画の制作を受諾
・昭和四十七年(六十四歳)、この一年を鑑真和上と唐招提寺の研究にあてる
・昭和四十八年(六十五歳)、障壁画準備の為、日本各地の海岸と山地を取材
・昭和五十年(六十七歳)五月、第一期障壁画「山雲」「濤声」が完成
・昭和五十一年(六十八歳)、中国桂林を訪問、この年より三回にわたり中国を訪問
・昭和五十二年(六十九歳)四月、パリのプチ・パレ美術館にて「山雲」「濤声」が展示
・昭和五十三年(七十歳)、北京と瀋陽で「東山魁夷展」開催
・昭和五十四年(七十一歳)、第二期障壁画四十二面の構想をまとめる
・昭和五十五年(七十二歳)二月、「黄山暁雲」「揚州薫風」「桂林月宵」完成
・昭和五十六年(七十三歳)七月、第三期となる鑑真和上像厨子絵「瑞光」奉納
以上の事績は、正に鑑真和上東征十年にも、匹敵する偉業であると思います。
画伯は、障壁画の制作に着手されたときの心情を、『「山雲」「濤声」と題して日本の山と海の風景画を描いた。和上が日本に着かれた時は、既に盲目になっておられたことを思うにつけ日本の風土を描いて和上の心眼に見て戴き、その山の風の音、海の波の響きをお聞かせしたいと考えたからである。また和上の徳の高さ、慈愛の深さを山と海にたとえた。』と述べておられます。また、『日本と中国を文化の上で結ぶ上に、大きな貢献をされた和上に捧げる障壁画の意義が成り立つ』とも述べられております。
思い返せば昭和五十三年十月二十八日、当時の中国国務院副総理鄧小平閣下が来日された際、唐招提寺をご訪問され 鑑真和上像の里帰りを実現していただき、日中間のかつてない盛事となりました。この時も「日本国宝鑑真和上像中国展」の下準備や東山魁夷画伯の中国国内写生の旅での安全等多くの方々のご助力がありましたが、中でも元中国仏教協会会長趙樸初先生のご尽力は、多くの記録が伝える所です。先生は、日中友好を願われ「黄金の絆」として両国仏教徒の道標となっておられます。
この度の展覧会を通じて鑑真和上の偉業は勿論の事、日中友好に生涯を捧げる方々に思いを馳せて頂ければと願っております。
〈にしやま・みょうげん〉
日中の文明的常数
(No.884 2019.11.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
社会学者
大 澤 真 幸
どんな社会や国にも、「文明的常数」のようなものがあって、それは、近代化しても変わらない。文明的常数とは、その社会が、文字や都市や国家などの文明的な要素を導入したときにセットされた、基本的な構え、つまりコンピュータのOS(オペレーティング・システム)のようなものである。それぞれの社会や国の文明的常数は、その社会・国の強みにもなれば、弱みにもなる。
日本の文明的常数は、「帝国的な秩序のかなりの周辺」ということに規定された態度である。帝国的な秩序とは、中華帝国のことである。日本列島は、帝国の中心からかなり離れている。間には海もある。とはいえ、日本は、帝国の中心で何が起きているのかがわからなくなるほどの辺境ではない。
このような条件のもとにある社会は、どうなるのか。まずは、帝国の中心でなされていることの模倣である。周辺から見ると、帝国の中心にある洗練された制度や文化や価値観は、ことごとく合理的で魅力的である。日本は、だから、中国からあらゆることを学び、すべてのことをマネした。
しかし、日本列島の位置は、帝国の最先端の制度や文化を完全にコピーするには、中心から離れすぎてもいる。その距離のゆえに、コピーはどうしても劣化する。また、帝国の中心からの干渉や介入も受けにくい。こうして日本は、帝国の先進的な要素を選択的に取り入れ、またしばしば独自に「カスタマイズ」して活用した。今、私がこの文章を書くのに使っている「文字」は、そうした要素の典型である。漢字仮名交じり文は、中国の文字の日本なりの変形の産物だ。
では、中国の文明的常数は何か。もちろん、「帝国」としての態度である。今やかつてのような世襲の皇帝はいないが、中国は今でも帝国だと思う。
帝国とは何か。例えば、今、アメリカのトランプ大統領は、「アメリカ・ファースト」と唱えながら、貿易等のあらゆる局面で中国と張り合っている。自国や自民族を「ファースト」とするこうした考えほど、帝国の原理に反するものはない。
帝国は、多様な民族や共同体を共存させ、包摂するところに本質がある。だから、帝国は、たとえば洗練された法をもつ。小さな部族や親族の範囲を超えて通用する法を、である。あるいは、帝国は、部族や村々を超えて人々を惹きつけ、統合する普遍思想をもつ。そして、各地の方言を超えた「世界言語」として役立つ文字をもつ。漢字こそ、まさにその世界言語であった。
「ファースト」と唱える者の排他性は、帝国のやり方に著しく反している。私は、中国に「帝国」的に振る舞ってほしい、と願っている。周辺の日本人をずっと魅了してきた帝国として、である。そうすれば、中国主導で、つまり帝国のもつ包摂力によって、米中の摩擦は解決されるだろう。
〈おおさわ・まさち〉
中華人民共和国建国七十周年に寄せて
(No.883 2019.10.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
新しく生れた中華人民共和国は、長い歴史の中に誕生し、様々な課題を乗り越えつつ、ここに建国七十周年を迎えました。
我々の日本中国文化交流協会は、新中国の誕生から七年後に結成されて活動を開始しました。したがって新中国の誕生から成長へと進む歩みのほとんどの歳月、その国の進路や動向に深い関心を抱きつつ今日まで歩んで来た、といえます。
我が協会は結成以降、歴代の会長のもと、様々な分野で活動している多くの人々を役員に迎え、会員に集め、手探りのようにして文化交流の仕事を始め、多々の課題を乗り越えつつ、様々な稔りを生み出して来たことを振り返ると、新中国の建国七十周年を迎えるまでの歳月は、我々にとっても大切な年月であったのだ、とあらためて考えぬわけにはいきません。
誕生間もない中国からは、現代国家としての準備がまだ十分には整わず、多くの課題を抱えて急な坂道に車を押し上げて進もうとする気迫を感じ続けて来ました。
新しい国のそのような懸命な姿に接し、時にはこちらも当の道の険しさを見つめるようなことはありました。しかしただ一度も、誰ひとり、現代国家として出発した中国が、やがては先行する諸国を圧倒する存在へと成長するに違いないことを疑う者はいませんでした。
新中国の歩んで来た歳月を、ただ地図の上での隣国の現代史としてではなく、古くからの文化の面における大切な存在として交流して来た国の今の姿として、我々日本人は受け取らねばなりません。建国以来の新中国の七十年は、稔りの歳月であったことは間違いありませんが、まだ手の届かぬ領域や問題も多く残されていると思われます。新しい中国の持つ新しい重みを一方の腕に感じつつ、もう一方の腕には、まだ開かれぬ領域に埋もれているような重い文化の層までを視野におさめ、新たなる文化交流の扉を押し開かねばならぬだろう、と考えます。
新中国誕生以降の七十年は、その宿題を、今を生きる我々日中両国の人々の前に積み上げたのだ、ともいえるかもしれません。
新中国建国七十周年に、心からの祝意を表します。そして同時に、次なる課題に立ち向う準備をするため、新しい一歩を踏み出す仕事に取りかからねばならぬ、と考えている次第です。
〈くろい・せんじ 作家、日本藝術院長〉
日本美術の母胎は中国に在る
(No.882 2019.9.1より)
出光美術館館長
出 光 佐 千 子
私は、日本の水墨画、文人画などの研究を重ね、英国のセインズベリー日本藝術研究所、大英博物館日本部に約四年ほど在籍し、その後、出光美術館で約十年間学芸員を務めてまいりました。そして今年四月、出光美術館館長に就任いたしました。
出光美術館は、私の祖父・出光佐三(出光興産株式会社創業者)が蒐集したコレクションを後世の人々の教学の助けになるようにと、一九六六年に開館いたしました。二代目館長の出光昭介は、海外との文化交流に努め、特に中国との交流に尽力しました。日本と中国の国交が回復した一九七二年以来、国家文物事業管理局(現・中国国家文物局)、故宮博物院、中国歴史博物館(現・中国国家博物館)、中国社会科学院考古研究所などの先生方が当館を訪問されました。このような交流から、故宮博物院研究員で著名な中国陶磁研究者であった馮先銘先生の御令嬢・馮小捷氏が当館で勤務されたこともありました。そして、日中文化交流協会の御協力で、「近年発見の窯址出土中国陶磁展」(一九八二年)を当館で、当館収蔵の陶磁器名品を展観する「陶磁の道―中国、日本、中東、欧州の間の陶磁交流展」(一九八九年)を故宮博物院で開催するなど、頻繁な交流が続いております。
私は大学在学中に、幸運にも当館理事で琳派が専門の山根有三先生、陶磁器が専門の長谷部楽爾先生らと中国各地の博物館を巡り、その魅力を体感いたしました。卒業旅行では、小捷氏の案内で、友人たちと上海から蘇州、桂林、昆明、成都、西安、北京などを十日ほどかけてバスで旅したことがあります。スケールの大きさ、懐の深さ、多民族の共存など、日本にはない奥深さを肌で感じ、中国の魅力に心を奪われていきました。その影響から、私は池大雅(一七二三―七六年)を研究するようになりました。大雅は、日本に伝わった中国の画風を学び、西湖、瀟湘八景をよく主題にした江戸中期の文人画家です。文人画は、詩文や儒教の教養を備えた文人たちが、絵画の技巧よりも内容の豊かさを重んじて描く雅趣に富んだ絵画です。その薫陶を受けた大雅の代表作「西湖春景・銭塘観潮図屏風」(重要文化財 東京国立博物館蔵)は、日本に伝来した画譜と蘇軾による銭塘の高潮を虹に喩えた漢詩に拠って、波が虹色に描かれています。鎖国時代にあり、中国へ渡航できなかった当時、中国の文化を敏感に感受し、想像を膨らませ、憧憬の地・中国を描いた画家が多くいました。それ故、現実とは異なる部分もありますが、これが却って独特の趣を醸し出しています。
中国は、私にとって最も身近な外国です。中国の美術なしには、日本の美術を語れません。何故なら、日本美術の母胎は中国に在ると思うからです。美術の面白さは、作品から画家たちの思いを感じることができ、未知の空間へ想像力を馳せることができることです。今後も、人とのつながりを大切にしながら、心を揺さぶる美術作品と出会える美術館を目指していきたいと思います。
<いでみつ・さちこ 青山学院大学准教授、博士(美術史)〉
アニメが持つ無限の力
(No.881 2019.8.1より)
日本アニメーション株式会社
代表取締役社長
日本動画協会理事長
石 川 和 子
日本の国産アニメーションは、2017年に公開から100年を迎えました。そして今日、日本アニメ産業の市場規模は2兆円を突破し、そのうち中国を中心とする海外での売り上げが9,948億円、アニメ産業市場全体の約46%を記録しています(日本動画協会刊『アニメ産業レポート 2018』)。中国市場の重要性が益々高まっている中、昨年には、日中両国間で映画共同製作や人的交流を促進するための「日中映画共同製作協定」が発効されました。今年6月末には、中国の習近平国家主席がG20大阪サミットに出席するために訪日され、安倍晋三首相との首脳会談で10項目の共通認識を達成しました。このような非常に良い流れの中で、今年7月にアニメ業界訪中団が実現しました。
一行は、「日中映画共同製作協定」締結のために尽力され、中国側からの信頼が厚い角川歴彦氏とともに、アニメ業界の主要な企業の代表者が参加してくださいました。日中文化交流協会を通じて中国人民対外友好協会に日程の御手配を賜り、文化観光部、国家広播電視総局、国家電影局などを訪問し、日中アニメ市場拡大に向けた話し合いの場を持つことができました。今後の交流の在り方や、共同製作、人材育成、規制基準などについてお話するうちに、双方の目指すところが同じであると実感できたことが大きな収穫でした。在中国日本国大使館や外務省、経済産業省などの関係者も交流に加わってくださり、「日中アニメーション協定」締結の必要性と、官と民が連携した新たな交流関係構築の重要性を日中双方で確認することもできました。
もう一つ、収穫があります。それは、今回の訪中を通して、私の父・本橋浩一の遺志を引き継ぐことができると確信できたことです。父は、1975年、「アニメを通して、人間性の涵養に寄与したい」という思いから、日本アニメーション株式会社を創業しました。高畑勲氏と宮崎駿氏が監督、作画に関わった「フランダースの犬」「赤毛のアン」「母をたずねて三千里」などを代表とする「世界名作劇場」シリーズ、「ちびまる子ちゃん」など120を超える作品を制作してきました。父は、長年中国との交流を大事にし、中国の子供や大人たちにも素晴らしい作品を届けたいという思いから、中国での放送に腐心し、30年前には「世界名作劇場」の数作品がCCTVで放送されました。現在、「ちびまる子ちゃん」は、日本と中国で同時配信が実現し、これも父の努力の賜物と言えます。
日本と中国との交流で言えば、1941年に上海で公開された「西遊記 鉄扇公主の巻」がアジア初の長編アニメ映画であり、戦時下の日本にも輸出され大きな影響を与えました。最近では「千と千尋の神隠し」が中国で公開され、大きな反響を呼んでいます。私は、アニメは国境を越え、人の心を育む無限の力があると信じています。日本アニメが、隣国である中国でこれだけ受け入れられるのは、他の国同士では見られない程、日中両国の文化が通じ合っているからだと思います。アニメという文化を通して、日本と中国が引き続き手を取り合って、足音高く進み続けていくことを祈っています。
〈いしかわ・かずこ〉
大学生交流の意義
―王旭東院長との約束
(No.880 2019.7.1より)
日中文化交流協会常任委員
東京藝術大学名誉教授
宮 廻 正 明
1984年、3千人の青年が中国に招かれた。私も恩師である平山郁夫先生の推薦で加わり、初めて中国の地を訪れた。33歳の時だった。その時に各地での交流や悠久な歴史を体感した感動は今でも深く印象に残り、その後の人生の歩みに大きな力になっている。
今年6月、中国大使館の招請、中日友好協会の受け入れにより、日中文化交流協会大学生訪中団110名が北京、蘭州、敦煌を訪れた。私が団長となり、団員は、協会の役員、会員からの推薦を受け、全国40の大学から選抜された様々な分野の学生だ。それぞれの学生が自分の目で中国を見て、各地の同世代の若者と友情を育む目的で参加してもらった。出発日の空港で学生たちの顔を見た時、皆、当時の私と同じく、希望に胸を膨らませた表情をしていた。
北京到着後、まず向かった故宮博物院では、院長に就任したばかりの王旭東先生と再会を果たした。今春まで敦煌研究院院長の任にあった王先生とは、30年近くの付き合いで、私が最も信頼する中国人の一人である。王先生とは以前から一つの約束を交わしていた。「文化交流は、両国交流の基礎である。特に、国の未来を担う若者の交流が大切で、若い世代の交流を盛んにしよう」との内容である。私も大学在任中から、研究者や学生の人的往来を促進してきた。しかし、その数には限度があった。今回100名もの学生を連れて訪中することができ、王先生との約束の一端を果たすことができたと実感している。故宮博物院では、磁器の絵付け、篆刻、装飾品の制作体験を用意してくれていた。
北京林業大学、蘭州大学では、ともに日本語や英語ができる学生が中心になって歓迎してくれた。協力してテーマを決め、考えをまとめて発表し合った。さらに歌や踊り、楽器の演奏、書道のパフォーマンスなどで友情を深めた。打ち解けて楽しく食事を共にしている様子を見ていると、嬉しさが込み上げてきた。
敦煌では、シルクロードの要衝であった陽関に立ち、往時の繁栄に思いをはせた。鳴沙山では皆が砂山に登り月牙泉を実見した。そして莫高窟では4世紀から一千年に渡って造営され仏教美術として世界最大の規模を誇る彩色塑像と壁画を堪能した。
中日友好協会は全行程、周到な御手配をしてくださった。到着した夜は宋敬武中国人民対外友好協会副会長が歓迎の宴を、帰国前日には程海波中日友好協会副秘書長が歓送の宴を開いてくださった。心からの感謝を申し上げたい。
芸術に限らず、日本の文化の多くは中国から伝わってきたものだ。私は常々、文化は独占する時代から共有する時代になったと話している。歴史を振り返ってみても、日本と中国はお互いが影響し合い、学び合い、今日に至っている。今回の学生たちの交流が友情と相互理解の芽となり、将来大きく森のように成長してほしいと願って止まない。
〈みやさこ・まさあき 日本画家〉
中島健蔵の生きた戦前と戦後の「昭和」の時代
―逝去40周年に思う
(No.879 2019.6.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
平安女学院大学客員教授
加 藤 千 洋
初代理事長として協会の運営の基礎を固められた中島健蔵が1979年6月11日に他界し、早くも40年の時が流れた。
その謦咳に接したこともない筆者が、逝去40周年に一文をものにするというのはややおこがましいと考え、せめて中島の代表作を読み直してからにしようと2冊の本を手にとった。
岩波新書『昭和時代』(第1刷は1957年5月)と朝日選書『後衛の思想―フランス文学者と中国』(第1刷は1974年11月)だ。
この4月から5月は「平成」から「令和」へと、世間はちょっとした「改元ブーム」で湧いたが、この年号問題について中島は『昭和時代』の中でこんなことを書いていた。
「天皇を基準にした『明治』、『大正』、『昭和』というような年号が、将来も長く続くかどうか、わたくしの個人的な意見では、既成の事実としての、『昭和』が年号の最後になるべきだと思う」
そして、こう続ける。
「明治、大正、昭和に生きた人間としては、これらの年号を無視して歴史を考えることはむずかしいのである」「生まれたのが明治、育ったのが大正、社会に出たのが昭和ということになる」「自分では『昭和』の人間であると思っている」と。
その昭和の「戦中」に体験したあることが、中島をして「戦後」の昭和で中国との関係を結ばせることにつながる。『昭和時代』と『後衛の思想』でページを割いて言及する、日本占領下のシンガポールでの「ある体験」だ。
中島と交流のあった方々には知られている話だと思うが、要約すればこういうことである。
昭和16年末の日米開戦から間もなく、中島は徴用されてシンガポールで軍属の宣伝班員になる。ある日、街で華僑の女性に呼び止められ、青年の写真を見せられる。消息が途絶えた息子を必死に捜しているが、もしやこの子を知らないかというのだ。
そうしたことが二度、三度と重なる。そのことから中島は日本軍が抗日抵抗運動を鎮めるために起こし、ひた隠しにした「華僑大虐殺」の事実を知ることになった。
中島が1956年発足の協会の理事長職を引き受けると、「フランス文学者だったのに、なぜ中国関係に深入りするようになったのか」と何度も問われるはめになる。
その時に用意していた答えを『後衛の思想』では次のように書く。
「答えははっきりしている。きっかけはシンガポールでの経験である(中略)わたくしの苦悩は深くなる一方であった。しかも、その苦悩は、戦地では表に出すことができなかった。苦悩のうちに、わたくしは、日本と中国との関係が、日本の将来の運命を左右することになると確信するようになった」(同書18頁)
この春の改元で、メディアの取材に多くの国民が「令和は平和な時代に、戦争のない時代になってほしい」と答えていた。
結構なことだ。ただ平和は願っているだけでは、しっかりと確保できない。そのために何か自分ができることを「実践」することが大事だ。日本中国文化交流協会を軸にした中島の「戦後の昭和」の生き方に、私はそれが示されていたように思うのだが。
<かとう・ちひろ>
※加藤氏は、「アジア文明対話大会」に出席するため、5月14日から北京を訪問。
中国と私
― 6度目の訪中に思う
(No.878 2019.5.1より)
日本中国文化交流協会顧問
無名塾主宰、俳優
仲 代 達 矢
私の生まれは1932年、日本軍が本格的に中国東北地方へ攻め入ったいわゆる〝満州事変〟の翌年であった。後年に小林正樹監督による長編映画『人間の條件』に出演した。原作者である五味川純平の従軍体験を役者として実感したこともあり、「日本の中国侵略」という負の遺産は、今に至っても心に沁みついている。
小学2年生のときに父親が死去したこともあり、少年時代の生活は極貧状態であった。戦後、学制が新制に変わり、高校は夜間部に入った。昼間は、競馬場で警備員として働き、映画、芝居見物に通った。白井義男に憧れ、プロボクサーになろうと考えたこともあった。そんな日々の中、俳優座公演「女房学校」を観劇した際、千田是也の演技に感銘を受け、1952年、俳優座養成所に4期生として入所した。同期生には佐藤慶、佐藤允、中谷一郎、宇津井健らがいた。その頃は映画が黄金期を迎えようとしていた。養成所時代に10度目に受けたオーディションにやっと合格し黒澤明監督の「七人の侍」(1954年)に、セリフなしの浪人役をつとめて映画デビューした。この出演で武士の歩き方ができなかった私は黒澤監督をいら立たせ、「俳優座では歩き方も教えないのか」と罵られ、ワンカットに朝の9時から午後3時までの半日がかりの撮影となってしまい、最終的に「仕方ない、OK」となったというほろ苦い思い出がある。
初めての訪中
俳優座創立者の1人で、演出家としても活躍した千田是也が日中文化交流協会の創立に携わったことを後に知った。1959年から公開された映画「人間の條件」では、旧満州を設定した場面が多かった。当時の国際情勢と日中間の国交が無いゆえに、実際の撮影は中国での撮影はなく、北海道サロベツ原野周辺で撮影が行なわれた。初めて中国を訪れたのは、1977年の日本映画人代表団に参加した時であった。当協会の編成によるもので、木下恵介団長のもと、映画監督の小林正樹、松山善三、熊井啓、映画音楽の木下忠司、撮影監督の岡崎宏三ら錚々たるメンバーで、俳優は吉永小百合と私だった。この時代は「文化大革命」の荒波が漸く終息し、文化人も本来の持ち場に帰って、街の中に活気が溢れ始めていたのを記憶している。それから、映画祭での訪中や、私的なウルムチ、トルファンへの旅があった。
「大地の子」で朱旭さんと共演
終戦50年の1995年に放映された日中共同製作テレビドラマ「大地の子」は忘れ難い作品だ。山崎豊子原作によるもので、敗戦後の混乱の中、旧満州で残留孤児となった青年の波乱万丈の生涯を、全7回、計10時間50分で描いた超大作だった。主人公・陸一心(中国名)を上川隆也が演じ、中国の名優・朱旭さんが養父を、私が実父を演じた。戦争の爪痕の中で、懸命に生き抜く日本人と中国人を描き大きな反響を呼んだ作品だった。朱旭さんは北京人民芸術劇院に所属し、私も演じたアーサー・ミラーの「セールスマンの死」を演じていたこともあり、すぐに意気投合し深い親交を結んだ。陸一心の行く末を2人が語り合う場面を撮り終えたとき、周りにいた日中両国のスタッフが、みな涙していたことを記憶している。同作品は中国側の多大な協力があって完成したが、歴史的に敏感な場面が多いのか、中国では正式放映はされなかった。いつの日か、この作品が中国でも放映されればと願っている。朱旭さんが昨年逝去されたことは痛恨の極みであった。だが、2015年に当協会の招きで来日され、無名塾を訪ねてくださり、感動の再会ができたことを記しておきたい。
北京と上海で大歓迎を受ける
この3月に日本演劇家訪中団で約10年ぶりに6度目の訪中をした。中国戯劇家協会の招きによるもので、中国戯劇家協会主席で俳優の濮存昕さん、千田是也、杉村春子とも親しかった92歳の俳優・藍天野さん、映画「ココシリ」で知られる陸川監督、上海市戯劇家協会主席の楊紹林さんといった皆さんと交流した。北京と上海での交流会や座談会には、大勢の老若男女が集まってくれ、熱心な質問に役者冥利に尽きる思いがした。これまで映画180本、芝居70本に出演してきたが、中国では、私の場合、演劇よりは映画俳優として知られている。小林正樹監督の「切腹」、黒澤明監督の「用心棒」「椿三十郎」「乱」などが中国で紹介されていたせいか、映画に関する質問が多かった。
今年は戦後74年、中華人民共和国建国70周年を迎える。日本と中国が良好な関係になることは大切なことだ。日中友好が世界平和の模範となるよう、私も俳優として尽力していきたい。86歳の私がいつまで現役で舞台に立ち続けられるかどうかわからない。今年も映画出演のほか、秋から明年にかけて半年間、23歳の時に千田さんと巡回公演した思い入れの深い舞台「タルチュフ」が予定されている。来年は87歳、数え年の中国では米寿になるとのこと。機会があれば、米寿で中国の舞台に立ってみたいと思っている。
〈なかだい・たつや〉
日中医学交流の難しさ
(No.877 2019.4.1より)
日本医療学会理事長
髙 﨑 健
私は臨床医として医療に従事してきましたが、近年は、病院運営や高齢者問題その他多くの医療問題にも関心を持って活動して来ています。
私の師である故・中山恒明先生は、国際外科学会から「世紀の外科医賞」を授与された世界的外科医でしたが、医療制度改革、臨床医育成、専門医制度、その他多方面の社会活動にも関わって来られました。そしてこれらの活動に対し昭和57年、勲一等瑞宝章が授与されました。中山恒明先生は、常に「患者さん中心の医療」の実現を目指して来られ、この精神は我々多くの弟子にも染み付いています。
現代の医療現場では科学的エビデンスに基づいて作成されたガイドラインに沿って医療を行なうことが求められて来ています。その結果、人としての患者さんの存在が忘れられ科学技術優先の医療となる事態も起こっており、患者さんと医師との信頼関係は希薄化して来ています。この問題は中国では日本以上に大きな問題になっています。
私は中国との関係を深めて20年になります。当初から気になっていたのは、先進医療を求めメディカルツーリズムとして来日される中国からの患者さんのことです。彼らは言葉や高額な治療費問題を抱え、住み慣れた土地を離れ知り合いもいない日本へ精神的不安を抱えながら治療を受けに来られているのです。そこで我々が出来ることは中国の医師と交流し、中国でも日本と同じ治療が受けられるような医療環境作りに協力することだと考え、北京の中日友好病院の知人の医師と話し合い医療交流を始めた経緯があります。中国でも「患者中心の医療」と言う言葉はよく聞かれました。しかし具体的にはどう言うことであるのか理解されてはいませんでした。近年は、毎月北京を中心に、中国各地で活動をして来ていますが、中国の若い医師は医療技術の習得には非常に熱心です。しかし日本以上に中国での医師と患者さんとのトラブルは深刻な状態であり、より良い人間関係を築くためには単に医療技術の交流だけではなく医療文化の交流を深めることがより大切だと思っています。しかしこれは大変に難しいことです。
今年2月下旬、日中文化交流協会が編成した日本医学訪中団で、医療機器や医学出版の方々と一緒に北京、福州、アモイを訪ねました。中国人民対外友好協会の周到な接待もあって、最新の病院や介護施設での参観と交流を通し、新たな見聞を得、再認識できた事もあり、収穫の多い旅でありました。しかしながら触れられたくないところは隠されており、表面的な説明に終わっているところも多く、これでは本当の交流にはならないと感じた部分もありました。
現在、北京大学医学部には各学年の1割以上に日本人留学生が在学しています。一度彼らと会合を持ったのですが70名以上の学生が集まってくれました。この他の大学にも日本人留学生は居られるそうです。このような若い人達が中国の若者と親密な友情関係を築き、蟠りのない付き合いを始めるようになれば本当に両国にとってより意味のある交流が進むだろうと期待しています。
〈たかさき・けん 医師〉
日中著作権シンポジウム
(No.876 2019.3.1より)
一般社団法人 日本音楽著作権協会会長
い で は く
知的財産権に関する話題は今や世界的な関心事でありますが、一口に知財といってもそれを構成する中味は多岐に亘っており、著作権もその一つであります。さらに私が身を置くのはその中の音楽部門、日本音楽著作権協会で、私共の協会は今年創立八十周年を迎えます。
ふり返れば多くの大先輩達が苦労を重ね、時には自己犠牲を払い、日本の音楽作家の生活を確立するために努力し、がんばってきたおかげで、今や世界でもトップクラスの優良管理団体に成長しました。
私共の仕事はいうまでもなく作詞、作曲者、音楽出版社から信託された歌や音楽楽曲の著作権管理であり、利用者の皆さんからいただいた著作権料を権利者の皆さんに分配することです。いってみれば利用者と権利者を結ぶ扇の要のような立場ですから、利用者の方々には利便性やわかり易さを、権利者の方々には早く正しく分配することが最も肝要です。
一方では著作権料をいただく為の努力、世の中の人々に著作権というものを理解してもらう作業をしなければなりません。「他人が作ったものを使う時はそれを作った人に何がしかのお金を払う」というごく当り前のことを今さら理解してもらうというのも情けない話ですが、現実ですからしかたありません。
今日ではデジタル化、ネットワーク化の発達により各国の歌や音楽のコンテンツが世界中で使用される時代になりましたからより大変です。特にアジア諸国は欧米に比べると人々の著作権に対する意識や認識が希薄であり、また管理団体の規模も小さく、その国で使われている楽曲の使用頻度に比べ、著作権料の徴収、分配額が少ないというのが現実です。このような状況下では音楽や歌を創作して生活をする作家はなかなか育ちません。
私は以前から「アジア人が持つ音楽的才能は欧米人に負けていない。その情緒的ナイーブさはむしろ勝っている。」との思いを持っていました。それもあって私は師匠である作曲家遠藤実先生と話し合い、先生の財団(遠藤実歌謡音楽振興財団)事業として「アジア歌謡祭」を五年間実施し、先生の亡き後は「日中著作権シンポジウム」を開催し、両国が直面している著作権問題を討議しています。
このシンポジウムは一年毎に開催地を日本と中国交互にして、テーマはその都度、話題や問題になっているものを取り上げ、現状報告や対策をディスカッションしてきました。これまでのテーマは「中国著作権法第三次改正」「カラオケに関する現状と著作権」「音楽インターネット配信の現状と問題点」等で、今年三月、七回目が新潟市で開かれます。
何故中国がパートナーなのかというと、現在のアジアに於ける著作権保護状況を考えた時、経済的なものもふまえ、将来日中のリーダーシップの下でアジア各国の音楽管理団体の整備、発展につなげ、それがアジア人の音楽的才能の啓発や、対欧米に伍した楽曲発信に資すると考えたからです。
遠藤先生と作った『北国の春』をアジア何億の人々が歌ってくれたことへの感謝の気持ちも含めてこの事業を続けています。
新しい日中関係構築へ
―シルクロード国際シンポジウムを開催して
(No.875 2019.2.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
東京藝術大学客員教授
前 田 耕 作
東京藝術大学は、昨年12月13日、文化庁、日本中国文化交流協会、中国日本友好協会、敦煌研究院、日本経済新聞社の協力を得、日経ホールと東京藝術大学において日中平和友好条約締結40周年を記念する「シルクロード国際シンポジウム&トークセッション」を開催した。シンポジウムは第1部「文化が紡ぐ道―敦煌・中央アジア・奈良」、第2部トークセッション「作仏・観仏三昧談義」と長時間に渉るプログラムから構成された。ひろくより多くの人びと、特に若い世代の参加と共感を得たいという思いもあっての企画だった。申し込み人数は1部2部とも1000名を遥かに超えたため、抽選による入場者を決めなければならなかった。
第1部の開催にあたり、主催者を代表して筆者、中国側を代表して程海波中日友好協会副秘書長、王旭東敦煌研究院院長が挨拶した。その共通の趣意は、このシンポジウムをもって文化交流の歴史に学び、文化遺産保護の活動を通じ、日中の新しい友好関係を積み上げる第一歩とするというものであった。
シンポジウムでは井上隆史東京藝術大学特任教授の総合司会で次の5つの講演が行なわれた。
入澤崇龍谷大学学長 「シルクロード研究への日本の貢献」
林梅村北京大学教授 「近年のシルクロード考古学の新発見と研究」
張元林敦煌研究院敦煌学情報センター長 「敦煌―シルクロード文化の宝庫」
青木健静岡文化芸術大学教授 「神々のシルクロード―ゾロアスター教、マニ教、キリスト教、イスラーム」
映像「シルクロード・弥勒の道を探る」 (井上隆史制作)の上映と筆者による解説
シルクロードを多様で多声的な文化交流の道と捉え、時代によって様相を異にする結実を地中海の世界から日本海に至る広大な空間に置き直し語る広やかな視座が交差し、会場には大きな共感の風が吹きわたった。
シンポジウムに合わせた映像の制作も新しい試みであったが、アフガニスタンの現地の人々によって撮影されたバーミヤン遺跡や、敦煌研究院の支援と協力によって実現をみた莫高窟と麦積山石窟と炳霊寺石窟の現状を伝える4Kカメラによる映像の力は圧倒的で、聴衆に強い印象を与えた。このシンポジウムで提起された論議とその成果を踏まえ、東京藝術大学は日本の初期仏教に大きな影響を与えた弥勒の誕生した原点を求める共同の作業を開始する。
第2部は宮田亮平文化庁長官の挨拶の後、山下靖喬氏による素晴らしい津軽三味線演奏につづき、籔内佐斗司東京藝術大学大学院教授による講演「ほとけの意味とそのかたち」と、いとうせいこう、みうらじゅん両氏によるトークセッション「仏像大使、シルクロードを語る」が行なわれ、若者たちの笑いを誘った。シンポジウムを成功裡に終えることのできたのは、日中文化交流協会の力強い支援のお陰であったと深く感謝申し上げたい。
<まえだ・こうさく>
新年にあたって
(No.874 2019.1.1より)
日本中国文化交流協会副会長・理事長
池 辺 晋 一 郎
あけましておめでとうございます。2019年は、東京オリンピック・パラリンピックの前年であり、5月1日からは新しい元号に変わる節目の年です。日中関係は、国交回復から47年め、そして平和友好条約締結から41年となります。いずれも人間に置換すれば、不惑を過ぎ、人生で最も充実する年齢域。付記すれば私たちのこの協会は1956年に設立されましたから、今年は、実に63年めです。
この年月は長いとも言えますが、しかし日本と中国両国の歴史を想うとき、中国での、私のある体験に触れなければなりません。
映画人代表団(篠田正浩団長)の一員として訪中したときのことですから、1991年です。ところは西安の陝西歴史博物館。はじめの部屋は、たしか何百万年か前──太古の時代の展示でした。いくつめかの部屋で、ようやく「原人」(たぶん数十万年前)が登場。次は石器時代、次は青銅器時代、そして古代国家の時代……そろそろ足が棒状態になってきて……すると「唐」!
知ってる!つい、この間だ……。
瞬間の、この感慨に、我ながら笑みがこぼれたこと、忘れられません。何を言っとるか……。でも、中国では、こうなるのです。何という壮大なところでしょう……。
閑話休題。63年め、でした。
63年間、日中間はずっと平穏だったかというと、そうではありません。さまざまなことが起こりました。現在も、困難な問題を抱えています。しかし、人間の歴史には凹凸がある、と私は思うのです。平和な時代、戦いの時代、また平和な時代、再び戦いの時代、そしてまた平和な時代……。ずっとこの繰り返しでした。今、困難なことがあっても、いつか必ず解決する。だが、次にまた困難が生じる……。
だから放っておけばいい、ということを言いたいのではありません。人智を超えたものが存在するのではないか、と思うのです。地球は今「間氷期」ですが、これは約11700年前に氷河期が終わってからの話。いつまた、氷河期が来るか、わかりません。
日中関係とは、そのくらい大きなスパンで捉えてもいいのではないでしょうか。すなわち目先ではなく、ずっと先の未来を視野に入れて対処していくべきものなのではないか、と素人考えで感じるのです。
「唐…この間だ!」の感慨は、私にこのような想いを抱かせたのでした。
さて、皆さまご承知のとおり、日本は私たちのこの「日本中国文化交流協会」のほかに、日本中国友好協会、日本国際貿易促進協会、日中経済協会、日中友好議員連盟、日中協会、日中友好会館の、「日中友好7団体」と呼ばれる組織等多くの友好団体を擁しています。これらに関わる人すべての熱意と努力を、新たな「友好条約締結41年め」へ注ぎたいではありませんか。何といっても、長い長いおつき合いのなかの、新たな1年なのですから。
<いけべ・しんいちろう 作曲家>
日中関係を思う
―日本経済界訪中団に参加して
(No.873 2018.12.1より)
株式会社セブン銀行特別顧問
安 斎 隆
日本銀行、日本長期信用銀行、アイワイバンク銀行(後のセブン銀行)等、金融界に携わって半世紀になる。中国との関わりでは、日銀在任中の1974年から約3年間にわたって香港に駐在した。当時の香港には多くの中国系銀行が進出していたが、文化大革命中だった中国は経済が低迷して外貨準備が涸渇、しかも自力更生路線の踏襲もあり、借金をできない状態だった。親しくなった中国系銀行のトップに「海外にある銀行支店での外貨預金受け入れ、リース、信託、輸入ユーザンス(輸入代金の支払い猶予)もある」と助言。将来を見据えながら可能な一歩を踏み出すというアドバイスが評価されたのか、帰任にあたり「中国のお好きな場所に案内したい」と招待を受けた。そこで、あこがれの敦煌に行きたいと申し出たが、1976年は激動の時期だった。周恩来、朱徳、毛沢東が相次いで逝去、さらに唐山大地震があり、敦煌訪問は実現しなかった。
香港から帰ってからも関係は続いた。90年代半ばに中国が決済システムを海外から導入する方針を決め、欧米や日本に国際顧問団の派遣を要請してきた。私が日本代表となり3カ月に1回、北京を訪れた。最先端のシステム導入を提案する欧米に対し、私は現在の実力に見合うシステムの導入を求めた。後に首相となる朱鎔基氏に私の意見を認めてもらったことは記憶に新しい。
今日の中国は急速な経済発展に伴い、文化、文明、生活レベルが上がっている。しかし、経済発展が急激過ぎると民度が追いつかない問題が出てくる。日本におけるバブル経済の形成と崩壊はこのことが起因していたと言える。ここ数年、中国はまさに同じ様な問題に直面しており、民度を上げ、物事の考え方を転換していく必要がある。中国でも長年続いた一人っ子政策の弊害が出ており、若者が金銭や精力を生活向上や遊びに費すという風潮が見られる。兄弟がいて勉強の競争相手になり、また助け合う。兄弟喧嘩をして人との付き合いや仲直りを学ぶ。国と国の関係も同じで、日中両国は隣同士、大事な競争のパートナーだ。良好なライバル関係によって競争の仕方を学ぶことができる。これが共に発展するための秘訣と考えている。
今年9月、長年の念願であった敦煌訪問が実現した。日本経済新聞社と日中文化交流協会が毎年実施している日本経済界訪中団に参加、敦煌莫高窟をはじめ甘粛省の麦積山石窟、炳霊寺石窟などを訪ねることができた。特に麦積山石窟で「菩薩と比丘立像」(第121窟、北魏時代)を鑑賞できたことは望外の喜びだった。というのは、十数年前に東京で、この像を描いた絵画に出会い、菩薩像と比丘像の何とも言えない愛らしい姿が気に入り買い求めていたのだ。
〈あんざい・たかし〉
天空の浄土にて
(No.872 2018.11.1より)
日本中国文化交流協会評議員
中 上 紀
紺碧の空にポタラ宮殿が白い肌をきらきらと輝かせていた。ここは高地チベット、宮殿を上まで登ると標高三八〇〇メートルになるという。体調が本調子ではなく、階段を上がりながら息切れと頭痛がした。旅の疲れからでなければ、高山病のせいだろう。
きんと冷えたラサの最初の朝、ジョカン寺に向かった。巡礼の老若男女たちが五体投地でお祈りをしている。下に専用のマットを敷き、横にはバター茶の入ったポットと、たまにスマートフォンが置いてある。お参りの列は長く、遅々として進まないのに、皆文句ひとつ言うでもなく一歩一歩を踏みしめていた。流暢な日本語を話すガイドの後ろにつき、柴崎友香・谷崎由依・阿部智里各先生方と、私で構成された代表団は、観光客用に設えられた通路をすいすいと進む。
仏典の原本を求めて日本人でチベットに初めて入り、『西蔵旅行記』を記した河口慧海の頃は、こんなお寺の訪れ方は考えられなかったはずだ。東京から北京まで約四時間、北京からラサまで約四時間半。かたや慧海はチベットに入るまでに三年。当時は鎖国中だったということもあるが、もともとチベットは中国大陸の果て、ヒマラヤ山脈の麓という、厳しい自然に閉ざされた場所だった。
父方の故郷である熊野にはかつて「補陀落渡海(ふだらくとかい)」という行があった。僧が限られた日数分の水や食料と共に小舟に乗り込み、外から釘で打ち付けられて那智の浜から船出する。目指したのは補陀落と呼ばれた極楽浄土だ。古代の日本人は、海の向こうに常世の国があると信じ、水平線から来るものを崇め、憧れ、そこに行こうと試みた。そこ、すなわち中国大陸のことである。そこに行けば補陀落がある。補陀落はサンスクリット語でインドの観音浄土ポータラカから来た。そして、ポタラ宮も、ポータラカが由来であった。
チベットの作家の方々との座談会でこのお話をさせていただいた。とりわけ一年前、日本から来た私たち作家との会議のためにわざわざ北京に飛んできてくださったツェリン・ノルブ先生に、お伝えしたかった。日本人のチベットへの憧れを。どんなに世界が近くなろうと、日本人が、私たちが、いつも大陸に特別な思いを抱き、見つめていることを。
座談会には農村を題材にした小説を書かれているニマ・ペントゥ氏をはじめ三人の女性作家も来られていた。チベットで女性による小説が発表されるようになったのは一九八〇年代で、少し前までは女性は文筆で収入を得ることなど考えられなかったと聞いた。作家の皆さんは、日本の着物にどこか似たチベットの民族衣装を纏ってきてくださっていた。座談会の後の食事会は歌と踊りとお喋りが尽きなかった。祝う、吉祥、という意味でもある「タシーデレ」と互いに何度も言い合い、いつまでも別れたくなかった。
北京では鉄凝先生をはじめとした作家の皆さんたちとの嬉しい再会や、魯敏先生との新たな出会いを心より楽しんだ。中国滞在を通じて、日本の先生方ともたくさんお話をさせていただいた。再見という言葉がこれほどに心に沁みた旅はない。
<なかがみ・のり 作家>
日中平和友好条約締結40周年に当たって
(No.872 2018.11.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
東京大学公共政策大学院院長
高 原 明 生
1978年に日中平和友好条約が締結されて今年で40周年を迎えました。1972年に国交が正常化されて既に6年が経っていましたが、平和友好条約の締結により、日本と中国の間の吊り橋が鉄橋になった、というのが当時の福田赳夫総理のコメントでした。
条約の批准書を交換するために鄧小平氏が来日し、昭和天皇と会見したほか、新幹線に乗り、多くの近代的な工場を参観しました。「日本を訪れて近代化とは何かがわかった」と述べ、「中国の近代化建設をお手伝いいただけますか」と松下幸之助氏に話しかけて、「何であれ、全力で支援するつもりです」という答えを得ています。その後、中国は徐々に経済の対外開放と市場化を進めましたが、日本の政財界は強力にそれを支援しました。その結果、80年代に日中関係の蜜月が実現したのは、多くの人が懐かしく思い起こすところだと思います。
日中平和友好条約では、主権と領土の保全や内政不干渉など中国が唱える平和五原則を取り入れたほか、国連憲章の重要な原則である、すべての紛争を平和的な手段により解決することが謳われています。そして今日に続く同条約の重要な意義は、日中それぞれが覇権を求めないと約束したところにあると言えましょう。
そもそも覇権とは何でしょうか。これは、中国が外交を論じる際によく使う言葉です。当時の中国は、反覇権の合意を最大の脅威であったソ連に対抗する統一戦線の形成と見なしたがっていました。ですが日本側が条約の交渉過程で覇権の意味を問うても、中国側は「おわかりでしょう?」とはぐらかして、その定義を明言することはなかったそうです。
そこで私は中国で使われている『現代漢語詞典』を引いてみました。するとそこには、国際関係上、実力をもって別の国を操縦ないしコントロールする行為だと記されています。言い換えれば、力を恃んで自分の意思を相手に押し付けること、それが覇権の行使だと言ってもいいでしょう。
当時、中国が覇権を求めるようになると考えた日本人は多くないでしょう。ですが、中国の指導者たちは興味深い言葉を残しています。鄧小平氏が、日本の園田直外相との会談で、「もし中国が将来覇権を求めることがあれば、世界の人民は中国の人民と共に覇権を求める中国政府に反対すべきだ」と語ったことはよく知られています。
その5年前、1973年には、周恩来氏が米国から来た若い女性の研究者と面白い会話をしました。貴女は中国が将来覇権国家になると思いますかと周総理が尋ねたところ、それはないでしょうと答えが帰ってきました。するとすぐに「それはわかりませんよ、中国は覇権の道を歩むかもしれません」と述べ、「ですが、もしそうなったら、貴女はそれに反対すべきです。そしてその世代の中国人に、周恩来が反対するよう言ったのだと伝えて下さい」と続けたのです。
恐らく、二人の指導者は、冗談を言ったわけではないでしょう。人であれ国家であれ、実力が向上するにつれ、その理想も振る舞いも変わる可能性があることを知っていたのだと思います。日本においても、日露戦争までの主張と、それに勝利した後の振る舞いに大きな違いが生じたことはよく指摘されています。
両国が40年前の約束を守り、平和を維持していくためには何が必要でしょうか。今や共通する脅威であったソ連もなく、日中は戦略目標を共有していません。それだけに、残念なことではありますが、紛争が生じたとしても、お互いに力を恃むことなく、どのように自制するのかは現実的な課題となっています。
自制のためには、相手についての正しい理解も必要でしょう。両国間の認識ギャップ、そしてその基である情報ギャップを埋める努力を続けねばなりません。そして日中平和友好条約でいう紛争を解決する平和的な手段とは、ルールであり、実力の濫用、すなわち覇権を許さない法の支配にほかなりません。人権を尊重し、法によって国内と国際の秩序を支えることを願う中国人が増えているのは救いです。日中平和友好条約を思い起こすことが、日本でも改めて平和と人権の大切さを考えるきっかけになればよいですね。
<たかはら・あきお 現代東アジア政治>
青年に栄えあれ
(No.871 2018.10.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
安 部 龍 太 郎
日中平和友好条約締結四十周年を記念した日中大学生千人交流大会に参加するために、日中文化交流協会が組織した百名の大学生訪中団の団長を拝命した。
一行は八月二十四日に北京空港に着き、翌日山西省の太原空港に飛んだ。その後バスで平遥まで移動。明の頃にきずかれた平遥古城を見学し、翌日には太原にもどって山西博物院を訪ねた後、山西大学での学生交流会にのぞんだ。
大学正門では山西大学党委員会書記の師帥先生自ら出迎えていただき、しばしの懇談の後に学生たちの交流風景を見学した。
「中国語が話せなくても大丈夫ですよ。うちの学生は皆英語でコミュニケーションできますから」
師先生は自信たっぷりにそうおっしゃるが、私は内心不安だった。
百名のうち英語や中国語ができる学生も何割かいるが、あまり話せない学生もかなりの数にのぼるだろう。だから活発に話すのは一部の学生だけで、他の学生は置いていかれるのではないか。
そう考えていたが、会場に着くなりそんな不安は吹っ飛んだ。師先生のご配慮により、山西大学側も百名の学生を出席させ(夏休みの日曜日にもかかわらず参集してくれていた)、一対一で向き合って話せるようにしていただいたので、活発な話し声が会場でうなりを上げているほどだった。
言葉がうまく通じない相手とも、スマホの通訳アプリを使ったり、漢字による筆談によって意思を通じ合い、見ているこちらがうらやましくなるほど生き生きと話し合っている。
その表情を見ていると、青年の無限の可能性が感じられて涙がこみ上げてくるほどだった。
交流会の後には図書館を見学した。蔵書三百六十万冊。四階建ての図書館は吹き抜けにして彩光を良くし、使いやすさに配慮した素晴しいもので、未来を担う学生により良い勉学の環境を与えようという大学側の熱意が感じられた。
その後アトラクションの発表会があり、山西大学生のプロ並みの歌やダンス、楽器の演奏を堪能した後、学生食堂での夕食会となった。
この席でも大学生たちはパートナーとなった相手と食卓を囲んでいた。まさに同火共食の交わりで、別れのバスに乗り込む時には感極まって泣き出す学生もいたほどである。
翌二十七日には大同市に移動して雲崗石窟を見学。二十八日には北京に移動。翌二十九日には本番とも言うべき「日中大学生千人交流大会」にのぞんだ。
日本の五団体の学生五百名、中国の学生五百名が一堂に会し、日中友好と相互の平和的発展について意見交換をおこなった。
青年の無気力、消極性が取り沙汰される昨今だが、今回のメンバーはそうした懸念を一蹴してくれた。
実に収穫の多い秋の旅だった。
<あべ・りゅうたろう>
写真集「天地創造」の撮影を終えて
(No.870 2018.9.1より)
写真家 白 川 義 員
私の人生最後の仕事「天地創造」の撮影が、先日中国の武陵源で終わり、今編集中で来年暮れに出版の予定である。これまでプロになって五十八年間に世に出した十一作に今回のものも含め総てが私の思想信条理念信念による「地球再発見による人間性回復へ」と標榜する仕事で一作の例外もない。まず「地球再発見」とは、地球は何百億光年という悠久無限の宇宙にあって、これも又何百億個という星の中の一個の星だが我々はこの星以外に住める星がない。つまり一個の宇宙船に乗った運命協同体である事実。つまり運命協同体の宇宙船の中で戦争をする愚劣を認識できる写真であること。これは五十数年昔、六年間ヨーロッパ・アルプスに籠って撮影中、日の出の太陽を受けて真赤に輝く鮮烈荘厳な風景を眺めながら、地球上にこのような凄い風景を実際に見た人間は一体何人いるであろうかと考えながら思考が拡大して行ったのである。次の「人間性回復へ」はまず人間と動物を分ける唯一絶対の違いは何か、それは人間精神があるかないかの違いである。ではなぜ人間だけに人間精神があるのかである。三百万年昔我々の祖先である猿人がこの世に現われたとき、彼等は自然が演じる壮大なドラマに凄絶な感動と深遠な畏れを持ったのである。地震が来ても台風が来ても津波が来ても手も足も出ない。彼等は自然とその背後の宇宙に偉大な巨大な精神の存在を感得するに至るのである。そして畏敬の念を持ち敬虔の祈りを捧げたのである。つまり原始宗教が生じたが故に、彼等に偉大な精神革命が起こってサルがヒトになった。
これらの私の思想信条を写真にしたのが、これまでの私の作品集である。「アルプス」「ヒマラヤ」「アメリカ大陸」「聖書の世界」「中国大陸」「神々の原風景」「仏教伝来」「南極大陸」「世界百名山」「世界百名瀑」「永遠の日本」そして今回の「天地創造」である。そしてこれらはすべて前人未踏の撮影であった。「南極大陸」などは撮影など関係なく「南極大陸」一周に成功したのは歴史上私と同行した私のグループ三人だけである。三十七年前に出版した「中国大陸」上下全二巻も当時中国をあれだけ広範囲に撮影できたのはまさに奇跡といわれた。いったのは中国撮影家協会の会長であった徐肖冰氏や多くの会員の皆さんである。第一あの当時中国が混乱を極めた文化大革命の直後、中国側ヒマラヤ、カラコルム、パミール、天山山脈五五〇〇キロを撮影する許可が出るなどと考えた人間は世界に一人だっているわけなどないのである。写真の世界はもちろん山岳関係の人達も皆仰天だった。パキスタンとの国境線上にある世界第二の高峰K2、中国名チョゴリ(八六一一米)とその周辺はあます所なく特に徹底的に撮って「中国大陸」下巻に掲載した。これらの写真が広く世界に公表されたのはもちろんこれが最初であった。その後「世界百名山」ではこれらの国境線上にある名山例えば最高峰のエベレストはもちろん、すべての山について八〇〇〇米の上空から航空撮影ができる異例の許可が出て中国側からも徹底的な航空撮影に成功して凄い写真を公表することができたのである。生涯忘れることのできないありがたい出来事で、今も常に手をあわせている。 〈しらかわ・よしかず〉
※本年6月に実施した白川義員氏の湖南省武陵源への取材は、日中文化交流協会が協力し、在日写真家の馮学敏氏が同行した。
「日中仏教書法展」開幕式に参加して
(No.869 2018.8.1より)
日本中国文化交流協会顧問 東大寺長老
森 本 公 誠
今年八月十二日は日中平和友好条約締結四十周年を迎える。これを記念して日中文化交流協会が企画した「日中仏教書法展」が寧波市仏教協会をはじめ寧波市関係各位の協力を得て、寧波市で開催されることになった。筆者は図らずも訪中団の団長として、書家の杭迫柏樹、天台宗書道連盟理事長の大野亮弘両副団長他団員総勢十六名とともに、六月二十三日の開幕式に出席した。
この書法展は、日中双方のおよそ百名からなる代表的な僧侶や書家が寄せた揮毫を日中文化交流の一環として、寧波だけでなく七月には東京、九月には比叡山延暦寺においても開催されるもの。前日の午後四時前、寧波空港に着くと、寧波市仏教協会副会長の観宗寺印超住職他、人民政府職員らの出迎えを受け、花束を頂戴した。宿泊先のマリオットホテルで宮廻正明氏を団長とする東京藝術大学代表団と合流、一行は前身時代の東京藝大に留学し、のち禅僧となった弘一法師の卒業時の自画像を最新の技術で複製し、これを寧波市側に寄贈するためであった。
早速、宮廻団長とともに寧波市仏教協会会長で天童寺住職の誠信方丈と会見、歓迎の言葉を受けた。そのあと金黎萍寧波市民族宗教事務局局長主催の歓迎夕食会に列席した。料理は精進であった。中国側出席者は周悦徳他民族宗教事務局関係者と誠信会長や宗立・印超両副会長、書画家の陳啓元諸氏であった。
金局長はまだ若い女性で、その隣に坐った。三十年以上前、初めて訪中したときのことを思い出しながら、よい機会とばかりに金局長に宗教局の役割や仏教協会との関係など、ざっくばらんに聞いてみた。金局長から聞いた話は隔世の感があった。それでも民族宗教事務局の監督下に置かれていることには変わりない。
翌日の開幕式は寧波市仏教協会内の四明延慶講堂で行われ、誠信会長に続いて挨拶をさせて頂いた。寧波は古代より水上交通の拠点として栄える一方、仏教の聖地として空海・最澄・栄西・道元といった日本の祖師たちが学んでおり、中国側もよく知るところであったが、重源上人について触れられることはなかった。平安末期の戦乱で東大寺が灰燼に帰したとき、上人は六十一歳の高齢にもかかわらず、復興事業の責任者に選ばれ、およそ二十五年をかけて成し遂げたこと、それまで中国に三度渡った経験があり、その最新の知識を生かしたこと、その恩返しにと阿育王寺舎利殿再建のための材木を日本から送ったことなどを紹介した。
宮廻団長より弘一法師自画像の贈呈式のあと、日本側の杭迫・大野副団長他と中国側の誠信会長・陳啓元書家他とによる揮毫会が開かれ、見事な達筆を堪能した。休憩ののち仏教協会内の食堂で精進による昼食会があり、なかなか美味であった。テーブルは中国側と日本側とに分かれていたが、筆者は急遽誠信会長の隣席に呼ばれた。文化大革命で僧侶は還俗しなければならなかったが、今や大勢の若者が仏門に入っている。急速な発展を遂げつつある中国の現代社会のなかで、仏教界が果たす役割など忌憚のない意見を伺った。ついでに、まだお若い感じだったので年齢を尋ねると六十とのことであった。
昼食後観宗寺を訪問した。最澄にゆかりの寺である。かつては広大な寺院だったらしく、今は二分され、半分は仏教協会の施設に転用されている。境内にはこれから建てる堂舎の垂木材が山と積まれ、その一本一本に寄進者名が墨書されていた。
翌二十四日の午前中、五磊霊山講寺を訪問した。ホテルからバスでおよそ三、四〇分、それから山中を走ること三〇分、三国時代の呉国朱烏年間にインド僧那羅延が創建したという古刹である。かつて紅衛兵がことごとく破壊したが、もっか復興の只中にある。住職は開幕式の司会を務めた宗立仏教協会副会長。住職自らの案内で、境内を参観した。昼食はお寺の食堂でご馳走になった。正面に舞台があり、その両側壁面に大型のテレビ画面が設置されていて、小ホールの感がある。マイクで歓迎の言葉があり、こちらから答礼の挨拶を述べた。
食事はセルフで枝豆やらトウモロコシ、ジャガイモやチンゲン菜など、農作物を次々と取っていくと、大きな皿が一杯になった。宗立住職のまえでいただきながら尋ねると、作物はすべて自分たちで栽培しているという。大変ですねと言うと、自分は近所の農家の出だから、農作業は生まれたときから身についているので苦はない。共同生活の僧侶は百名を超えるとか。一人っ子で出家したいと言い出したとき、両親は猛反対したが、次第に理解して、今や両親とも寺内でボランティアとして働いているとのことであった。
午後はまず阿育王寺に向かった。阿育王とはインド・マウリヤ王朝のアショカ王のこと。三世紀末近くの西晋時代、ある猟師が殺生の罪で地獄に堕ちると恐れていると、阿育王塔を礼拝懺悔すれば罪を免れると教えられて、塔を探し求めたところ、この地で地中より忽然と宝塔と舎利が出現したという。歴代の皇帝たちから崇拝を受け、とりわけこの地を統治した五代の呉越国最後の王、銭弘俶(せんこうしゅく)は阿育王寺の仏舎利信仰に篤く、阿育王の故事に倣って八万四千の仏舎利小塔を製作し、領内各地に頒布した。北宋が興起して中国を統一しつつあったとき、第二代皇帝太宗に謁見、阿育王塔を献上し、北宋への帰順を誓った。
それから間もなくした九八三年、東大寺僧奝然(ちょうねん)が入宋した。帰国時に生身の釈迦像を摸刻したと伝える京都・清凉寺の釈迦如来立像の納入品は、呉越の仏舎利塔の出土遺物と極めて近いという。以後日本で仏舎利信仰が盛んになる。
実はここ阿育王寺こそ重源上人ゆかりの寺である。上人もまた熱心な舎利信仰の持ち主であった。一一六八年、上人はのちに臨済宗の祖となる栄西を伴って阿育王山と天台山を参詣した。
我々一行は阿育王寺に着くと、心澄監院の案内で境内を参観、筆者からは持参した自著『善財童子求道の旅』と重源上人が晩年に自らの事績を記した『南無阿弥陀仏作善集』のうち、阿育王山舎利殿再建用の材木を送った部分の複写をわたした。
その後天童寺に向かい、誠信方丈から貴重な話を伺い、翌二十五日は終日天台山国清寺を訪れたが、紙数も尽きたので擱筆する。
<もりもと・こうせい>
中国音楽家代表団の来日を歓迎する
(No.868 2018.7.1より)
日本中国文化交流協会副理事長
東京藝術大学教授
永 井 和 子
ご周知のとおり、今年8月12日、日中平和友好条約が締結されてから40年を迎えます。この記念すべき節目を目前に、日中文化交流協会は、中国音楽家協会管楽学会主席の于海氏を団長とする中国音楽家代表団一行4名を日本へ招請します。于海氏は、著名な指揮者であり、日本の音楽家と深い親交を築いておられます。さらに、中国音楽家協会副秘書長で打楽器奏者の王建国氏、南京師範大学音楽学院院長で音楽学がご専門の徐元勇氏、武漢音楽学院副院長で古箏奏者の高雁氏と多士済々な代表団であり、以前にも増して活気を帯びた専門交流ができるのではないでしょうか。日中両国政府間においても、民間各界においても、交流が盛んに推し進められようとしている今、まことに時を得たことであり、心から一行の訪日を歓迎し、実りある交流になることを祈っています。
日中文化交流協会は、1956年の創立以来、文学、芸術、学術、科学技術などの交流を実施してきており、その中でも芸術の一分野として、音楽の交流にも力を注いできた歴史を先達の協会員から折々に伺っています。日中両国の国交が正常化する以前から、歌舞団やオーケストラ、民族音楽団などの演奏会の相互開催を行ない、その基礎となる音楽界での人的往来は、1970年代まで遡ります。日中文化交流協会は、1976年に作曲家團伊玖磨先生を団長とする日本音楽家代表団をはじめて中国に派遣しました。その後、定期的な相互往来がしばらく間をおいていた時期もあったと聞きますが、その中にあっても、両国の音楽界が互いに手を取り合って、歴史の流れの中を足音高く進み続けていることを誇りに思います。
2012年、私は日本音楽家訪中団で念願の新疆ウイグル自治区を訪問しました。宴が進むにつれ、必ず誰かが歌い出す。それに応えて又一人が歌う。更に踊りが始まる。楽器があればそれを奏でる。人々の中に常にいきづくエネルギー…音楽、歌、踊り。人の表現の原点を見た思いでした。
昨年には、貴州省東端に位置する黎平県肇興村を訪問する機会を得ました。ここは中国少数民族の侗(トン)族の村で、「大歌節」と呼ばれる歌祭り開催に併せての訪中でした。侗族には文字がありません。その文字を持たない人たちが、どのようにその気持ちを伝え、自分たちの歴史を引き継いでいるのでしょう―そこに歌が存在するのです。私は侗族の言葉はわかりませんが、心に伝わってくるものが確かにありました。私の専門とするオペラに通ずるものがあり、とても貴重な体験となった旅でした。
今の時代、SNSやメールでやり取りをし、人と言葉を交わさない人がいるということをよく耳にします。両国民の心の通い合いが更に密になってほしいと願う今、言葉を通して、また音を通して両国民の心が大河のように行き交い、信頼を深めることを祈りながら到着を待ちたいと思います。中国音楽家代表団の到着を待ちたいと思います。
〈ながい・かずこ 声楽家〉
マルチ文化人、弘一法師の自画像
(No.867 2018.6.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
東京藝術大学名誉教授
宮 廻 正 明
弘一法師は、新しい中国が生まれる揺籃の時代に活躍した禅僧で、中国では「南山律宗第十一代祖師」と称えられている。本名は李叔同。若き日に李岸の名で日本へ留学、東京藝術大学の前身である東京美術学校で西洋画を学んでいる。時代が大きく変わろうとしていた時期、美術はもとより、音楽、演劇、文学など多分野で異才を発揮した。1906年には日本で芸術団体「春柳社」を創立、『アンクル・トムの小屋』を上
演し大成功を収め、『日中文化交流』誌の題字を揮毫した欧陽予倩とともに中国話劇(新劇)草創期の中心的役割を果たした。日本留学中に革命運動にも参加したという。帰国後、浙江省杭州の虎跑寺にて出家得度、中国仏教の発展に大きな役割を果たした。宗教人という範疇にとどまらず、今でいうマルチ文化人だったこともあり、現代でも彼の才能を高く評価する人が多い。
昨年、日中文化交流協会を通じ、寧波市人民対外友好協会から、弘一法師が描いた卒業制作が大学に残されているのではないかと問い合わせがあった。早速、調べてみると、1911年作とされる自画像と、帰国後に仏門に帰依したとの手紙が残されていることが判明した。そこで、東京藝術大学と日中文化交流協会は、日中平和友好条約締結40周年を記念する今年、この「自画像」を最新のクローン技術で再生し、弘一法師ゆかりの地である浙江省の寧波に寄贈する運びとなった。
この作品は、今年6月に寧波で開催される『日中仏教書法展』に特別展示した後、由緒ある観宗寺に寄贈し、永く中国の方々に鑑賞していただくことになる。私の師である平山郁夫画伯と親交のあった在日中国人画家の王伝峰氏にも支援をいただいたことを記しておきたい。
寧波は中国仏教の聖地であり、空海、最澄、道元はじめ多くの日本僧が学ぶとともに、この地から各種の文化が日本へ伝えられた。中でも仏教絵画や南宋、北宋の絵画が日本文化の根幹をなす精神性に与えた影響は大きい。度重なる戦乱等で、あの時代の絵画作品はほとんど寧波に残っていない。10年ほど前に奈良国立博物館で「聖地寧波」と題する文物展が開かれ大きな反響を呼んだ。奈良や京都には、寧波から伝わった絵画、仏像、書が数多く残っているのだ。今後は、東京藝術大学が独自に開発した高精度なクローン文化財制作技術を使い、寧波で生まれたこの世界最高レベルの文化を寧波へ戻していけたらと願っている。
私にとって寧波は特別な土地である。1989年に発表し初めて院展奨励賞を受賞した『甍海一宇』は天童寺周辺の風景を描いたものだ。イノベーションした弘一法師「自画像」贈呈のため、6月に寧波を再訪する。その際、天童寺周辺をゆっくりと散策したいと思っている。
〈みやさこ・まさあき 日本画家〉
土岐善磨の訪中詠
-国交が正常化した翌年の代表団-
(No.866 2018.5.1より)
日本中国文化交流協会顧問
日本文藝家協会副理事長
篠 弘
いまや歴史上の古い逸話である。国交が正常化した翌年の「日本文化界代表団」九名が訪中したのは、一九七三年二月で、四五年前のことである。団長は八七歳の顧問土岐善麿、副団長は戸板康二、秘書長は白土吾夫、異色の団員に寂聴ならぬ瀬戸内晴美の諸氏が加わる。四四歳の篠が入り得たのは、善麿の作歌・研究の両面にわたる最後の弟子で、いわば介添え役であった。
当時はまだ、香港、深圳から入国した。その二十日余りの旅程を概括することよりも、善麿が「いのちありて」と題して詠まれた二八首から数首を引き、いかに中国を愛していたかを明らかにしておきたい。
いのちありて 三たび北京の大地を踏む 春きさらぎの風も寒からず
すでに善麿は、1960年と64年に訪中していたが、厳冬の北京は初めて。下句はそれに耐えうる気概を示しながら、自分が恵まれた稀有なる存在であるかを噛みしめる。
米寿を越え 万里長城へも登れりと 路の残雪に刻みおくべし
一行と共に八達嶺に赴き、城壁の上に残る雪を手にして微笑された表情を思い出す。
幾キロにたきこめし香(こう)の漂うか 地下壕深く たどりゆくとき
当時は、文革のさなかであり、民衆の労力によって作られた立派な地下壕を案内された。
思いきや 郭先生が 賓館の わが居室まで 訪い来ますという
人民大会堂で郭沫若(かくまつじゃく)の招宴があり、民族飯店の部屋まで、善麿を迎えにこられ、いたく感激した一首。郭先生とは、善麿は訪中のつど、杜甫研究などについて歓談していた。
時代と人のきびしさよ さらに 著者署名の 『李白と杜甫』を 旅に読むとき
文革の風潮に合わせて、いち早く筆者が、杜甫よりも李白を認めるようになった「時代のきびしさ」を、読み取った寂しさを隠さなかった。
うす暗くはなれし檻(おり)にパンダのおすの 眠るともなく 動くともなく
帰路に広州の動物園でパンダを見る。雌が数頭で、一頭のみの雄が鬱状となり、檻に隔離されるさまに、善麿は目をとめていた。
三度目の訪中を愉しみながらも、「いのちありて」の短歌で、文革中の気運を如実に察知されていたように思われる。
帰国したのが三月一四日。じつは一週間も経ずして、返礼として代表団が来日されたのである。国交の正常化が、いかに両国にとって渇望されたものであったことか。楚図南(そとなん)、謝冰心(しゃひょうしん)、李季(りき)の三氏が、目黒の土岐邸を訪れる。李氏は長詩「王貴と李香香」の作者で、われわれ一行の案内役をされた方である。
若き日の叙事詩の作を さりげなく 民謡のみと言いて微笑す
頂いた一冊は、最初の訪中の貴重な記念品となる。
編集者であった私は、この十数年後に、北京・商務印書館と『日中辞典』『中日辞典』を共同出版する契機となる訪中であった。
<しの・ひろし 日本現代詩歌文学館館長・歌人>
能楽を国際理解の一助に
(No.865 2018.4.1より)
日本中国文化交流協会副会長
二十六世観世宗家
観 世 清 和
今年2月、冬季五輪が開かれていた韓国の平昌へ、観世流から愚息の三郎太はじめ弟子ら13名が招かれ訪問しました。オリンピック憲章に基づき、開催都市の平昌、2020年夏季の東京、2022年冬季の北京が協力し、文化プログラムを通じて大会を盛り上げようという取り組みです。日中韓古典芸術リレー公演で私どもは「羽衣」を上演し、大変ご好評をいただきました。中国は京劇、韓国はアリランを披露。各国の古典芸能上演だけでなく、出演者らと親睦を深め、交流会で互いの国柄や現状について意見交換するなど、実りある人的交流ができる場であったようです。このような民間の文化交流は、継続してゆくことが大事だと感じています。
私自身は1989年に「日本伝統芸能五人の会」で花柳千代先生、野村万作先生らと北京、洛陽、西安で訪中公演を行ないました。京劇の人間国宝の先生方の舞台を拝見し、本物の強さを感じました。中日友好協会会長であった孫平化先生が流暢な日本語で「能楽も歌舞伎も文楽も、ある程度の基礎知識があって観なければ難しいと思う、京劇も同じだ」とおっしゃったことも印象に残っています。想像力を逞しくし、演者の息遣いを感じライブ感覚で観るのが能楽の楽しみ方のひとつです。一方、孫平化先生がおっしゃったように、能楽が成立した室町時代に思いを馳せ、古事記、万葉集、など古典の世界をある程度学び、基礎知識を持って観ると一層理解が深まります。能楽は、観阿弥、世阿弥がつくりあげた日本独自のものかというと、そうではありません。「白楽天」など中国を題材にした演目も数多く、物語の背景、根底が中国の故事に由来するものが豊富にあります。室町幕府は明との貿易を重要視し、武家のたしなみとして、能楽を奨励しました。その後、安土桃山、江戸時代まで受け継がれました。能楽を謡い、舞い、中国の故事を学び、武家の教養を深める。能を演じることで、中国の古典、日本の古典を学べるのです。能のルーツを思った時、中国は非常に重要な国であるといえます。
昨年オープンしたGINZA SIX地下三階の観世能楽堂は、おかげさまで好評を博しています。今後は海外からのお客様にも足をお運びいただけるよう、イヤホンガイド導入など多言語対応を計画しています。
現在我々は、目に見える目先のことだけで物事を判断しがちです。中国に対しても同様ですが、もっと理解を示さなくてはいけない時期にきているのではないでしょうか。日本の古典に触れると、先人達が中国の古いしきたり、慣習から多くを学んできたことに気づかされます。能を通じ、そのことを少しでも感じ、相互理解に繋がればと思います。来日される中国の皆様にも日中文化交流のルーツを知るひとつとして、能楽堂へぜひお越しいただき、それが未来に向けて日中関係のさらなる理解が深まる役割の一助になればと願っています。
<かんぜ・きよかず>
中国、この語り芸の宝庫!
(No.864 2018.3.1より)
浪曲師 玉 川 奈 々 福
日中文化交流協会と、中国曲芸家協会の交流事業で、北京、蘇州、上海をめぐりました。曲芸とは、中国語で語り芸のこと。各地域の曲芸家の方々と実演を披露しあい、芸と、芸をとりまく情報を交換し合いました。
訪問団は、お能の安田登先生、狂言の奥津健太郎さん、浪曲は玉川奈々福と曲師の沢村美舟、浅草・西徳寺の大谷たつさん、日本の語り芸の研究をしておられる京都市立芸術大学の時田アリソン先生という一行。
中国には四百種類を超える語り芸があるとか。さまざまな芸を堪能しました。北京では二人羽織みたいな「双簧(ソウコウ)」という芸にお腹抱えて笑い、河南墜子(巨大な箸みたいなのを打ち鳴らしながら語り、二胡、月琴、三絃が伴奏する)に感動し、単弦(一人語り、三味線伴奏)は浪曲に似てるなあ、京韻大鼓(太鼓を叩きながら、四胡、琵琶、三絃を伴奏に語る)の歌にしびれ。
こちらは能、狂言、浪曲の披露。浪曲は、字幕を作っていただきました。ご披露したのは「仙台の鬼夫婦」中国語入り。中国曲芸家協会の管さんが、笑いをこらえてひくひくしてました。
演芸のあとは、演者の方々と座談会。芸や修業のこと、国家の支援のありよう、どんな場所で活動するのか、それで食べていかれるのか、互いに興味津々、談論風発。
新幹線で移動して蘇州へ。蘇州評弾学校にて公演。国立の曲芸家養成学校で、学生三百人、五年制で二年間は学費無料……羨ましひ。
ちょっと京都に似た趣のある蘇州は、語り芸の本場。この学校がある他、評弾博物館があり、周辺の市を合わせて国営の寄席が百五十七カ所(!)、茶館などでも随時やられているそうです。政府が昨今、伝統文化支援に力を入れていて、曲芸家たちには基本給が出るほか、支援金も多く、寄席の木戸銭は日本円換算で六十円……なんという彼我の違い。
評弾というのは、「評話」という、一人で語る講談のような芸と、「弾詞」という、三絃と琵琶で演じる、歌と語りのある複数編成の芸とを合わせた言葉。両方を鑑賞。後、座談。
三か所目は、大都会・上海の一等地にある上海評弾団にて公演。お客様は曲芸家の方々のほか、一般の方々や、戯曲学校の学生、評弾の研修生、若い方々も。反応もよく、ここでも弾詞と評話を鑑賞。
中国の曲芸の方々は日本にたくさん語り芸があることをご存じなかったようですし、また、かほど共通点があることにも驚いておられました。これも、こちら側の芸を見ていただいたからこそ興味を持って聞いていただけたことだと思います。
ずっと旅に随行してくれた管さんが、これほど深い交流はかつてなく、これは大変大きな実績であると言ってくれましたが、五日間の間に、管さんをはじめ、中国の曲芸の方々と相当の言葉を交わしました。芸で生きる者同士、相互理解を深めた交流旅行でした。
<たまがわ・ななふく 一般財団法人日本浪曲協会理事>
絵画を通じた文化交流
(No.863 2018.2.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
浅 野 均
普段の絵画制作活動では、主に身近な生活と環境をテーマに描いています。具体的には付近のあちらこちらの美しい山岳や雲、水、樹木や植物、大気や差し込む光と影、家屋等で、身近な環境と人の生活との関わりです。今では既に忘れ去られた日本の絵画の古典技法、装飾的表現を蘇生させた技法で描いています。感動すればデッサンやスケッチなどを現場で行ない、深く観察します。そして古典的天然素材(和紙や岩彩、金、銀、墨、膠等)を中心に使用して描きます。
絵画の分野では日本と中国で、古代から展開した山水画の今日的表現に入るかもしれません。その観点では今日の中国の多くの画家との共通した心の世界が有るようで、太古からの長い時間と広大な空間の中での今、を共有しているように思えます。そして絵画を通じて広範囲な文化交流が楽しく行なえるように思えます。
例えば中国の画家とのスケッチ旅行や文化遺産の調査、共同シンポジウムなどを行ない、研究と絵画制作の成果を日中で発表するといったこともこれまでに度々行なってきました。又その活動を美術教育に反映させることも意義深いことに思えます。
記憶に残る交流はシルクロードの壁画と素材、岩彩画の技法と可能性、長江流域の山岳風景と水墨画、南方カルストの調査やスケッチ、美術教育の現状調査やシンポジウムなどです。
そういった交流の中で昨年は日中文化交流協会代表団に参加する機会に二度恵まれました。
9月下旬に北京国際美術ビエンナーレ(国立中国美術館)に絵画作品を出品すると共に、代表団(団長・入江観副会長)の団員として訪中しました。北京ビエンナーレは100カ国以上の国が参加した、美術館全館を使ったコンテンポラリーアートの世界最大級の展覧会で、絵画だけでなく立体や写真等世界中の様々な分野の美術作品が同時に展示されます。2010年の第4回に出品した時とは色々な面で異なっているように思え、今日の美術の移り行く姿がリアルタイムで実感できたように思えました。その様々な展示作品の中で自身の絵画作品がどのように見えるのかは大変興味深いもので、その場で感じ気が付いたことをできる限り作品制作や美術教育にも反映させるように努めています。
昨年のもう一つの日中文化交流協会代表団の訪中では、11月に団長として4人の団員と共に上海、杭州を訪問しました。せっかくの機会ですので日程的には少し欲張ったスケジュールでしたが、自然と山岳のスケッチ、古跡や博物館の訪問と調査、美術大学や国画院の参観等多彩でした。その時の中国の画家との交流は楽しく思い返されます。夕食時にはお互いに個々の作品集や資料を持ち寄り、団員の方々との作品制作時のことや内容に踏み込んだ会話には花が咲きました。
日中の絵画交流は古代から始まり、現存する多くの古典絵画はその時代に共通した要素と、それぞれで今日までに独自に発展した要素を持っているように思えます。加えて今日ではもうなくなってしまった大切な素材や表現や技術等も内包しているように思えます。そういった事を調査研究し創作することは、今後日中の絵画を通じた文化交流をますます盛んにさせるかもしれません。
中国の美術大学の絵画教育は、大学の大型化と共に学内に大きな美術館も併設等されていて、大変盛んです。又多くの画家が若い人の美術教育にも携わり、絵画を通じたこれからの文化交流の可能性を感じています。
<あさの・ひとし 日本画家、京都市立芸術大学教授〉
年頭に当って
(No.862 2018.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
二〇一八年という新しい年を迎える。
この年は、日中平和友好条約締結四十周年に当る。二〇一七年は日中国交正常化四十五周年であり、またその前年二〇一六年は吾が日中文化交流協会の創立六十周年であった。
このように幾つもの節目が年々相次ぐということは、それだけの稔りと重みのある歳月を我々が過して来た、という証であるに違いない。その道はしかし平坦であった、とはいえない。
政治、経済、外交等にからむ問題を前に時に立往生しながらも文化交流の道を探り続け、人間の交流をベースとした文化の通路を守って新しい領域へと進み出ようとする努力の歴史が、多くの節目をもつこの歳月であったに違いない。したがって、今前にある日々は、日本と中国との過去の交流の努力の積み重ねの中から生れたものであり、日本と中国とのこれまでの歴史に支えられたものであると同時に、将来に向けて進む一歩の足場ともなるものである、といえよう。
世界は今、大きく変動しつつある。アメリカのトランプ政権による米国第一主義の出現、英国のEU離脱とEU諸国における右派勢力の抬頭、核保有を目指す北朝鮮の動向、環境問題など、数々の波がかつてなかった規模をもって人類に迫ろうとしている。
その中にあって、日中両国の間にも島嶼を巡る領有問題などが発生し、政治的、外交的に厳しい状況が出現した。
当然その影響は文化交流の面にも影を落したが、しかし一方では、地道な交流が力強く押し進められた事実も見逃されてはなるまい。たとえば、日中国交正常化四十五周年に当る二〇一七年には「漢字三千年―漢字の歴史と美」特別展が開催され、東京をはじめ京都、新潟、東北、その他日本国内を巡って多くの人々の関心を集めた。この三千年という歳月の長さと重さ、その中に織り込まれている文化の足跡を考えれば、ここ五十年、百年の歴史は束の間に過ぎぬとも感じられてしまう。そして漢字という文字を共有する中国と日本は、特別の繋がりをもつ国であるとあらためて認識させられる。
その他にも、文化の各領域における人々の交流は、多少の影響を受けて滞ったところもありはしたが、基本的には従来の実績を大きく損うことなく続けられた。それが可能であったのは、これまでの両国の交流の歴史が稔りとして共有されているところがあったためではあるまいか。
二〇一八年にも、従来の代表団の往来に加えて、新しい訪中、来日の計画は検討されており、より豊かな繋がりが生れてくるものと熱く期待している。
この年が稔りある二〇一八年となることを願って止まない。
〈くろい・せんじ 作家、日本藝術院長〉
抑止と融和
(No.861 2017.12.1より)
作家 中 村 文 則
以前中国に二度行ったことがあるのですが、この度は日本中国文化交流協会のお世話になり、訪中することとなりました。
中国の作家との交流、会議、一般聴衆の前でのイベントなど、とても有意義な体験をさせて頂きました。この場を借りて、深くお礼を申し上げます。
中国に行く度に思うのは、日中の文化交流のさらなる重要性についてです。
日中の間には、政治的に様々な問題があります。そうであるからこそ、お互いの国の、文化レベルでの交流が必要です。そこでの関係性、相互理解は、両国が対立した時の、抑止と融和の土台になると考えています。
マスコミではどうしても、他国との対立を強調するような、不安と怒りを喚起する報道の仕方、演出が目立ちます。視聴率と関係があるように思います。不安と怒りは、言い換えれば「興味」であるので、それらを感じている間、視聴者はチャンネルを変えないからです。
出版においても、韓国や中国を悪く表現する、いわゆる「ヘイト本」が出版され続けています。このような本を出版するより、中国やアジア圏の作家の本を翻訳した方がどれほど有意義か、と思います。このような社会風潮の中で何ができるか。日々考え、実行していくことも、作家の役割の一つだろうと考えています。
中国文学は、言うまでもなく質が高い。それほど邦訳されているわけではないので、全体を語るのは難しいですが、日本にはあまり見られない特徴として、農村部と都市部の大きな差異に関する描写があります。
農村から北京などに出てきた人達と、元々都市部にいた人達の間の差異が、物語構築、人間の内面描写などに巧みに活かされています。日本は国土が狭く、農村部と都市部の価値観の差異は中国ほどではありません。ですが今は周知の通り、地方と都市の格差は広がっています。日本の文学に、現在の中国のような「都市部と農村部の差異」の文学が、今後極端な形となって逆流のように生まれてくるかもしれない。そんな感想も抱きました。
今年からペンクラブの国際委員になりました。そのペンクラブ主催の企画で、中国の作家達が先月来日しました。
今回お会いした方もメンバーにいましたし、以前お会いした方も来日されました。中国でのさようならは「再見」で、まさに一度お別れした後の再会となります。来年は新たに二冊、中国語での翻訳出版も予定されています。
今はそれを楽しみに、今後のさらなる文化交流に想いを馳せています。
〈なかむら・ふみのり〉
変化を生きる「訪中」
(No.860 2017.11.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
映画監督
小 栗 康 平
日中国交正常化四十五周年を記念して「日中大学生千人交流大会」が北京で開催された。日本から総勢五百人あまりが招かれたのだから規模としても大きなものだった。若い人たちにメディアを通した中国ではなく、自分の目で見て触って実感してほしい、そういう願いがあってのことだったろう。
訪中は欧米へ行くのとはまったく異なる体験である。漢字文化を共有してきた日中の長い歴史は、明治からの西洋近代のそれとは比較すべくもない。中国的なものは日々、暮らしの周辺にたくさんある。このことは皆、出発前にわかっていた。この確認はとてもいいことだった。しかし今日の中国の変化は凄まじい。ともすれば改革開放後の市場経済、近代化の成果にのみ目を奪われがちだ。出発前の私たちの中の中国が、中国にいてかすんでしまってはもったいない。
北京から貴州省に入った。私にも初めての地である。中国南西部に位置していて、稲作文化のルーツともされるところだ。雲南から続く照葉樹林帯には、ミャオ族など多くの少数民族が暮らしている。中国でもっとも貧困な内陸部とされてきた。ところがその貴州省が、今や成長率で中国国内トップスリーである。
飛行機が高度を下げていくと、三角おむすびの形をした、人懐かしいような不思議な山々が目に入って来た。高くはないそのカルスト台地の山々を縫って、高速鉄道が延びている。高層ビルは山に遠慮するのか、高さを揃えて林立している。日本の緑濃い里山の際にまったく突然、近代都市が現れたのだ。
天に三日の晴れなし、地に三里の平地なし、人に三文のお金なし、が貴州だったそうである。雨のよく降る天候は変わらないようで、あとは多くが変わった。省都、貴陽では地下鉄工事も進んでいる。
翌日、学生たちと見学したところは「ビッグデータ発展センター」という近代施設である。北京大学でもそうだったが、ITを含む先端科学技術で言えば、日中の若いエリートたちの「交流」はすぐに成り立つ。しかしそれだけではただの技術交流、情報交換だ。SNSなどのネットワークはいかにも便利にはなったが、忘れてならないのは相互の感情である。
私たちは誰しも変化を生きる。その中でそれぞれがなにを喜びとしなにを悲しみとして暮らしているのか、そういう想像力をこそ持ちたいものだ。私は貴陽のビルの谷間にあって、どこからか打ち消しがたく匂ってくる緑の匂いを嗅いでいた。水の湿った気配が身体の深いところで感じられもする。若者たちにはどうだったろうか。
帰路、上海に一泊した。近代建築の博覧会のような都市である。ここも中国、経済の中心である。政治の都市、北京と、経済の中心地、上海。両都市にサンドイッチされて、貴州があった。
〈おぐり・こうへい〉
南湖の虹
(No.859 2017.10.1より)
日本中国文化交流協会理事
放送大学教授
原 武 史
確かに「日本文化界訪中団」としての訪中は無事終わった。しかし団長としての責務をまっとうしたかといえば、到底そうは言えないというのが正直なところである。
今回はハルビン、長春、瀋陽、大連と、訪問した各都市で中国日本友好協会の方々や、黒竜江、吉林、遼寧各省や大連市の人民対外友好協会の方々に迎えられ、夕食会や昼食会が開かれた。団長である私は、当然主席に座らせられる。そして酒を飲まされる。ほとんど飲めないので、せめて食べないと失礼に当たると思って食べるのだが、慢性的に食べ過ぎの状態になる。ついに長春のホテルで体調を崩してしまい、同行する方々に多大なるご迷惑をかけてしまった。われながら、面目のなさを痛感している。
五泊六日で東北の四都市を回るというハードスケジュールになったのは、ひとえに私の趣味を優先させたからにほかならない。そう、鉄道である。たとえ超特急「あじあ」はもう走っていなくても、ハルビンから大連まで鉄道に乗って南下したいという長年の宿願を果たしてみたかったのだ。結果的に私は、自分の趣味にほかの方々を付 き合わせてしまったことになる。
しかし在来線で南下するのはダイヤ的に無理だとわかり、やむなく高鉄、すなわち新幹線を利用することにした。案の定、高鉄は速い。速すぎて鉄道に乗っている実感が湧いてこない。「あじあ」では四時間かかったハルビン―長春間が、たった五十四分しかかからない。東海道新幹線のような車窓の変化もないので、いつの間にか数百キロ移動しているような感じだった。
鉄道は実にあっけなかったが、ハルビンや長春では見ごたえのある場所を訪れることができた。まずはハルビン郊外にある「侵華日本軍第七三一部隊罪証陳列館」。個人的な話になるが、私の父は一九六一年から九二年まで、厚生省の国立予防衛生研究所(現・国立感染症研究所)でポリオウイルスを研究していた。この研究所は七三一部隊と関係があるという話を父から聞いていたので、ぜひとも訪れてみたかったのだ。実に丹念に史料を集め、客観的に事実を明らかにしようとする姿勢に感銘を受けた。最後の展示では、国立予防衛生研究所の初代所長が七三一部隊の出身であったこともきちんと記されていた。
長春では、「偽満皇宮博物院」を訪れた。「満州国」皇帝の溥儀が住んでいたところである。ここで見たかったのが、建国神廟と呼ばれる、アマテラスをまつった神社の跡であった。その隣には神体の鏡を避難させるための防空壕や、溥儀自身の防空壕もあった。
敗戦後、鏡は長春の南湖に捨てられたとされている。その南湖にも行ってみた。湖のほとりに立つと、なぜか突然、虹が現れた。湖底に沈んだ鏡が反射して、この不思議な光景を映し出しているかのような錯覚にとらわれた。
〈はら・たけし〉
さようならは、また会おう
(No.858 2017.9.1より)
劇団民藝舞台演出・翻訳
丹 野 郁 弓
水谷内助義団長の下、呑気に参加した二年前とは違い、今回は団長としてのぞんだ二度目の日本演劇家訪中団である。権威も頼りがいも無いなんとも軽い団長だけに、他の参加メンバーは吟味しないと、との心構えで前回も一緒だった白川浩司氏と共に厳選したのは、能登剛氏、ナガイヒデミ氏、ともに中国語に堪能な中国通である。これで少なくとも格好はついた。
私の所属する劇団民藝は日中文化交流協会との縁が浅からずある。滝沢修、宇野重吉といった劇団の代表が交流に参加してきたし、内山書店・内山完造氏の甥である内山鶉は劇団の演出家で長く活躍してきた。中でも滝沢の京劇への傾倒ぶりは甚だしく、京劇俳優の演技術について身振り手振り入りで熱心に語っていたことを懐かしく思い出す。とは言え、そうした数十年前とは違って今では中国に行くのは難しいことではない。誰もが気軽に行けるようになった国である。だからこそただの観光では訪中団の意味が薄れてしまう。そうした思いもあって、今回は観光はゼロ、ひたすら文化交流に時間を使おうと決めた。
特筆すべきは、北京で民間主宰による演劇団体と交流できたことである。政府主導の劇団がほとんどの中国で、民間人が私費を投じてやっている繁星演劇村や蓬蒿劇場などを見学して話を伺えたことは刺激的だった。繁星演劇村を主宰する樊星氏は演劇への熱い愛情から、蓬蒿劇場を主宰する王翔氏は舞台芸術を少しでも高めようとする理想から、とその成り立ちは一つではないけれど、こうした新たな演劇の潮流の芽生えを目の当たりにできたことは、私にとって大きな驚きでもあり喜びでもあった。
また、武漢の長江人民芸術劇院訪問も収穫だった。能登氏の豊富な人脈のおかげで、公式訪問にありがちな一辺倒な冷たさが無く、話している内にどんどん座が盛り上がり、ついにはあれよあれよという間に大人数の懇談会になった。初対面なのに、私までも古くからの知己のようにもてなしてくださり感激した次第である。最終訪問地の広州で迎えてくださったのは広州話劇芸術センターや広東省戯劇家協会の皆さん、まあ男性もいたのだが、何といっても圧倒されたのはその女性パワーである。いわゆるデキル女にありがちな取り澄ましたところがない。むき出しの大らかさ、人懐こさ、明るさ、しかも貪欲で強い。もう一度会いたい。そう言えば中国語のさようならは再見(ツァイチェン)!また会おうって意味ではないのか!?
文化芸術の中でも演劇は人間関係が濃厚にならざるを得ないジャンルである。手前味噌のようだがその意味で、演劇は文化交流にはまさにふさわしい。交流、というととかく堅苦しく考えがちだけれど、もう一度会いたい人たちができた、これこそ交流の根っこと言えるのではないだろうか。派手ではないがこうした活動を地道に長年続けてきた日中文化交流協会に敬意を表したい。
〈たんの・いくみ〉
本当の友情
(No.857 2017.8.1より)
日本中国文化交流協会副会長・理事長
池 辺 晋 一 郎
何度、中国へ行っただろう……。初めて行ったのは1985年11月。杉村春子団長のもと数人の旅だった。その折「私、ちょうど30回目なのよ」と言う杉村さんの記憶力に感嘆したが、いっぽう、よく考えなければ回数も分からない自分に、今いささか苛立っている。
映画人代表団や音楽家代表団があった。また、日本の現代音楽を披露するという国際交流基金の企画で、弦楽四重奏団とともに幾つかの都市を回ったこともある。北京中央音楽院で特別講義をしたこともある。
そして1986年の「日中合作バレエ」。当時の駐中国日本大使(故)中江要介氏はバレエ台本作家としてすでに僕と2作を協働していたが、その3作目として「蕩々たる一衣帯水」という作品を書かれた。中国の作曲家の友人・葉小鋼氏と僕が分担して作曲。北京と東京で上演した。
だが、僕の訪中で最も重い意味を持つのは、3度にわたる合唱組曲「悪魔の飽食」公演だと考える。先の大戦間に、日本陸軍が旧満州・哈(ハ)爾(ル)賓(ビン)郊外に構えていた731部隊がおこなった捕虜への凄惨な人体実験の記録。その全容を明らかにした森村誠一氏の著書をもとに、1984年、僕は7章から成る混声合唱組曲を作曲。そのとき僕はこう考えた――戦争を語り継がなければならないとよく言うが、それは原爆や空襲など「被害」についてのみでいいのだろうか?被害と同時に「加害」を含むのが戦争だ。その事実を放置してはいけない。この「悪魔の飽食」には、戦争が引き起こした狂気と罪への弾劾の血がにじんでいる。作曲しなければ……。
初演から何年か経って、新たな驚きがやってきた。この曲を歌いたいという人が大勢現れ、ついに1995年から「全国縦断コンサート」が開始されたのである。毎年どこかでコンサートが催され、その都度の地元に加えこれまで歌った人たちが全国各地から集合。今年は27回目で、7月2日、名古屋。総勢370人。ステージいっぱいの大迫力だった。
さらに、これまで7度の海外公演。うち3度が中国である。北京、南京、瀋陽そして2度の哈爾賓。これらの旅の途上、731部隊跡はもちろん、南京大虐殺や平頂山事件の現場も訪れた。あの戦争の侵略や加害に関して日本国民が深い謝罪の念と反省を抱いていることを、中国の人たちへ伝えたかった。民間の日本人が日本政府とは異なる意識を持っていることを、中国の人たちへ伝えたかった。
ベテラン女優たちが広島・長崎の記憶を読む朗読劇「夏の雲は忘れない」の音楽を僕は担当し、毎年の公演に関わっている。これは「被害」。そして「悪魔の飽食」に代表される「加害」を併せることで、戦争を語り継ぐことのバランスを形成しうると僕は考えている。戦後レジームからの脱却と為政者は言うが、勝手に脱却を標榜することは許されない。戦争を真に乗り越えたところにこそ、日中の本当の友情が存在すると思うのである。
<いけべ・しんいちろう 作曲家>
中国との絆―文化座創立七十五周年
(No.856 2017.7.1より)
日本中国文化交流協会評議員
劇団文化座代表 佐 々 木 愛
お陰様で劇団文化座は、今年創立七十五周年を迎える事が出来ました。
一九四二年、新劇団の中では一番歴史の古い「文学座」より五年遅れての出発でした。劇団の特長としては、創立者であった私の父、佐佐木隆や母の鈴木光枝など主要メンバーが、劇団新派の井上正夫演劇道場の出身者であった事ですが、戦時下の国策劇が強まっていく状況への反発が大きかったと思います。
一九四五年六月、文化座は、日本の現代劇の代表として中国(旧満州)へ招かれましたが、巡演の途中、ソ連軍の侵攻、続く敗戦によって、一年間の抑留生活を余儀なくされました。この一年間の中で、当時中国に滞在していた旧満映(現在の長春電影製片廠)の内田吐夢監督、木村荘十二監督や放送局の森繁久弥氏などとも親交を深め、帰国後も、大きな力をいただく事になりました。
しかし、何といっても歴史を見て驚くのは、敗戦の翌年、一九四六年三月に長春公会堂にて在留民団主催で、「彦六大いに笑う」の公演を行なっている事です。
旧満映で日本人スタッフと中国人労働者が非常に友好的に仕事をしていた事実は説明されても、敗戦から六カ月あまりでのこの公演の成立には、驚かざるをえません。立派なセットを飾っての記念写真の存在は、国と国との勝敗がつき、国境線の位置が変わっても、在中国の日本人と、中国の映画、演劇人の友情、友好が続いていた事を証明しています。
しかし、抑留生活の途中で内戦をも経験した両親には口に出せない苦労があったはずですが、母はいつも八路軍の兵士をパーロと呼んで、貧しい身なりをしながらも、その礼儀正しさと、規律の取れた生活ぶりを感嘆し懐かしがっていました。
父からは、「中国人というのはね、一度信頼したら、生命を賭けても相手を守る民族だよ」という言葉を聞かされていました。外地での敗戦という残酷を味わいながらも、父や母が人間を信頼する心を失わずに帰国出来た事は、文化座の歴史が今日迄続いた大きな原動力となっています。
引き揚げが遅れた内田吐夢監督は、亡くなる迄劇団の後援会長をつとめて下さいましたし、私が二十四才で父を亡くしてからは、作家の水上勉先生が親身に、私と文化座を見守って下さいました。
一九九七年「サンダカン八番娼館」で初めて訪中公演を行なった時、深夜到着した長春のホテルで、服務員の方達がずらっと並んで歓迎して下さり、母の事を抱きかかえるようにして部屋まで案内して下さった日の光景は今でも忘れられません。
――ここは、私が避難民として生活した街なのよ…と、つぶやいた母の言葉には、感無量の響きがありました。
水上勉先生から言われた事があります。
「僕は井上靖さんから言われたんだ。たとえ国と国とが再び争い合うようになっても、私達文化人は、海の底に穴を掘ってでも繋がり合いましょうと」
父や母が好きだった中国です。私も水上勉先生のお言葉を大事に、これからも微力ではありますが、中国と日本を繋ぐ努力をしてゆきたいと思っています。
<ささき・あい 日本新劇俳優協会会長、俳優>
玄奘三蔵と薬師寺―食堂落慶にあたって
(No.855 2017.6.1より)
法相宗大本山薬師寺管主 村 上 太 胤
かつて唐の玄奘三蔵は、仏法の真理を得るために命がけで印度へ向かわれました。正しい仏法を招来し弘めることが当時の政情不安定のなか、世の安寧に繋がると信じ願ってのこと。やっと辿りついた印度のナ―ランダで戒賢論師より唯識の教えを学び、往復十七年の歳月をかけ経典を中国に持ち帰られたのです。太宗皇帝の支援を受け、弘福寺、慈恩寺、玉華宮において経論七十五部千三百三十五巻を十九年かけて翻訳されました。その教えを根本教学として、玄奘三蔵の一番弟子である慈恩大師窺基が法相宗宗祖となって研鑽されました。やがてそれは日本からの遣唐使、留学僧、留学生らに依って脈々と日本へ伝えられてきました。
薬師寺では、苦難の旅をされた玄奘三蔵に報恩感謝と顕彰をする意味で玄奘三蔵院伽藍を建立し、この仏法東漸の道々を平山郁夫画伯に全長約五十メートルの大壁画として描いて頂きました。中国から印度までの壁画は、長安、嘉峪関、高昌国、西方浄土須弥山(天山山脈)、バーミアン、デカン高原、ナ―ランダの各風景です。平山郁夫画伯は玄奘三蔵が歩かれた道を百数十回旅し追体験され、スケッチ四千点、構想含め三十年を賭して描かれ、平成十三年に玄奘三蔵院壁画殿に御奉納頂きました。
さらに、中国から日本までの風景は、平山郁夫画伯に師事した田渕俊夫画伯に、同じく全長五十メートルに及ぶ大壁画を御奉納頂きました。この壁画は、薬師寺創建時の白鳳伽藍復興事業の一環として、今年五月に再建された食堂の内陣に祀られるものです。その内容は、ご本尊「阿弥陀三尊浄土図」を中心に、遣唐使船での旅立ち、航海中、日本へ帰帆、瀬戸内海、大和川、飛鳥藤原京、そして平城京までの「仏教伝来の道と薬師寺」十四場面が描かれております。
パソコンで情報を簡単に手に入れられる現代、日本の若者は海外留学をあまり希望しない傾向にあるようです。正しい教えを得るまでは何があっても東に帰らないという玄奘三蔵のような気概並びに文化、芸術、美術、すべてが最先端であった唐の都から、何としても学びとろうという遣唐使の情熱に感謝するばかりです。
現地に赴き、対話し、空気を肌で感じ、本物に触れなければ得られないものがあるのではないでしょうか。
去年、北京郊外の雲居寺の石室に保管されている般若心経の石刻が、玄奘三蔵訳による唐代に刻された現存最古のものであることが日本の新聞で報じられました。
この度、日中文化交流協会の御縁にて安田暎胤長老と共に雲居寺へ訪問させて頂くことになりました。是非、この目で確かめ拝ませて頂きたいと願っております。玄奘三蔵をより深く顕彰させて頂くことで、日中の文化交流が益々栄え、ひいてはアジア、世界の平和に繋がるきっかけになれば有難いと思います。合掌
<むらかみ・たいいん>
国を越えて通じるもの
-松竹大歌舞伎 北京公演を終えて
(No.854 2017.5.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
歌舞伎俳優
中 村 芝 翫
日中国交正常化四十五周年を記念し、三月十八日から二十日まで国際交流基金の主催、松竹株式会社、中国対外演出公司の企画・製作で、松竹大歌舞伎北京公演が開催されました。中国では十年ぶりの本格的な歌舞伎公演となり、会場の北京天橋芸術センターには、連日多くのお客様が足をお運びくださいました。十年ぶりに歌舞伎での文化交流ができ、中国の皆様が喜んでくださったのが何よりも嬉しいことです。
演目を選定するにあたり、どのように中国の皆様に喜んでいただくか話し合い、工夫を重ねてまいりました。「義経千本桜」では荒事の豪快さや歌舞伎の様式美を、中村鴈治郎さんの「恋飛脚大和往来」では歌舞伎のドラマ性を、片岡孝太郎さんの「藤娘」では女方の舞踊の美しさを存分に味わっていただけるよう趣向をこらしました。開演するまでは、今回のようにストーリー性のあるものがどれだけ理解され、中国のお客様に喜んでいただけるのか、不安もございました。十三年前に中村勘三郎の兄と「夏祭浪花鑑」をニューヨークで演じる際にも同じように不安がございましたが、その時同様、実際に舞台に立ちますと歌舞伎のストーリーとともに笑い、感動してくださるお客様の反応や心の動きが直に伝わってまいります。そこには国を越えて相通じるものがあると感じました。客席には多くの若い方もいらして、文化、芸術ともに優れた中国の若い世代の方に見ていただけたこともありがたいことでした。これほど情報も早い時代ですし、皆様の歌舞伎に対する理解も深く、言葉をはじめ歌舞伎を見るうえでの問題など心配せず、これからも様々な作品を中国で上演して大丈夫だと確信いたしました。長男の橋之助、次男の福之助も今回の舞台で心に響くものを感じ、多くを学んだと思います。
滞在中、京劇俳優の方々と食事をご一緒する機会がございまして、お話しておりますと、歌舞伎と京劇は、演劇文化として相通じるものがあり、演劇を通じた人の心の動きというものは遠く距離を越えても響き合うものだと感じました。
ぜひともまた中国に伺いたいですし、それが早く実現するよう、皆様にもご協力いただきたいと思っております。また、中国の皆様が日本にいらっしゃる際には歌舞伎鑑賞も目的のひとつとして来ていただきたいです。
このたびの北京公演はとても充実した三日間五公演でございました。今回は短い日数でしたが、将来中国でも一週間以上の公演が実現できればいいですね。また、歌舞伎と京劇の合同公演というのも大変興味深く思っております。父の七代目芝翫は日中文化交流協会副会長を務め、中国に度々訪れておりますが、その意志を引き継ぎ、日中の伝統文化である歌舞伎と京劇の交流をこれからも続け、中国の皆様にも、もっと歌舞伎を楽しんでいただきたいと思います。
〈なかむら・しかん〉
ぼくと中国
(No.853 2017.4.1より)
映画監督 山 田 洋 次
ぼくは旧満州で少年時代を過ごした引揚者です。父親が満鉄に勤務していた関係で転勤が多く、ハルビン、長春、瀋陽、大連といった都市を転々として育ちました。大連の社宅は旧ロシア人街の煉瓦建ての家でした。石炭の燃えるペチカの側で日本から流れてくるラジオの落語番組を聞きながら、長屋の暮らしや熊さん八さんという面白い人物が日本にはいるんだと想像するのが楽しかったものです。
敗戦後の暮らしは惨めでした。預金はすべて消滅した上仕事がまるでなく、日本人は売り食いするしかなかった。路上で着物や靴カメラ時計などを売ったり、石炭が買えなくて冬はストーブで本を燃やして暖をとりました。やがて引揚船が来て命からがら山口県の田舎に落ち着きましたが、一文無しの引揚者にとって戦後の日本の暮らしは満州時代に引けをとらないくらい悲惨だったものです。
70年代になって徳間康快氏の肝いりで中国と日本の映画人の交流がしきりに行われ、ぼくは瀋陽や大連を訪れる機会がありました。日本の植民地だった時代に幼少期を過ごしたぼくは中国の人に恨まれるのではないかとまるで罪人のような気分でいたものでしたが、中国側の映画人は一笑に付して「それはあなたの罪ではない、日本帝国主義の罪です、周恩来がそう言われたのです」と慰めてくれたものです。
そんなぼくの作品『家族はつらいよ』がこの度黄磊監督の手でリメイクされることについては格別の感慨があります。70年代の中国と日本の市民生活は服装から食物から町の風景から何もかもまったく違っていました。北京の大通りを自転車の大群が川のように流れる光景に圧倒された記憶がありますが、『家族はつらいよ』が昨年の上海映画祭で上映されたときには日本の映画館と同じように楽しげな笑い声が起きたのにびっくりしたものです。この作品で描かれるさまざまな事件、核家族、少子高齢化、無縁社会、熟年離婚からオレオレ詐欺にいたるまで両国がかかえる面倒な社会問題には共通する点が多いようです。グローバリゼーションということでしょうか。
『家族はつらいよ』の中国版ができるんじゃないかな、と親しい中国のプロデューサーと語りあったのは昨年の春先でしたがこれがたちまち実現して秋口にはクランクインの運びになったそのスピードの速さには驚きました。今日の中国映画界がいかに元気があるかということのあらわれです。中国語のタイトルは『麻煩家族』というこの作品は4月には封切りになるそうです。今や中国はアメリカに次ぐ映画大国でその発展には目を見張ります。日本の映画がもっともっとこの国で上映されることを、そして映画を通じて共通の文化を持つ日本と中国が仲良くなれることを心から願っています。〈やまだ・ようじ〉
アジア・太平洋地域の音楽創作者をひとつに
(No.852 2017.3.1より)
作曲家 都 倉 俊 一
二〇一六年十一月二十八日、中国・北京で開催された「世界創作者フォーラム」の冒頭、アジア・太平洋音楽創作者連盟(APMA)の発足式が執り行なわれ、その設立と、私が初代会長に就任することが発表された。その後、アジア・太平洋地域の各国から集まった錚々たる音楽創作者が、著作権管理団体国際連合(CISAC)副会長で映画監督の賈樟柯氏や「北国の春」の作詞で中国でも良く知られる一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)会長いではく氏も見守る中、会場を埋めた人々の万雷の拍手を浴びて壇上に集結、その門出を祝った。
思い起こせば今から三年前の十一月、当時JASRACの会長であった私が、オペラ作家で国際音楽創作者評議会(CIAM)の会長を務めるロレンツォ・フェレーロ氏に、CIAMの一員としてのアジア・太平洋地域を代表する音楽創作者の連盟を作らないか、と持ちかけられたのが始まりだった。
インターネットの普及と共に音楽の楽しみ方は大きく変わった。今ではインターネットを通じて無料で、あるいは月々一定額を支払うことで、膨大な曲の中から自由に好みの音楽を楽しめる時代である。
ところが、そのようなサービスを提供するグローバルな音楽配信事業者の成功とは裏腹に、私たち音楽創作者にもたらされる報酬は減少の一途を辿る一方、音楽創作者の権利を守る著作権制度を弱めようとする動きが各国で顕著になるなど、私たちを取り巻く環境は日々厳しさを増している。
こうした状況に危機感を感じた世界各地の音楽創作者がCIAMの名の下に結束し、私がロレンツォ会長と会った時には、既に欧州、北米、南米、アフリカにそれぞれ連盟が設立されていた。
もちろんこのアジア・太平洋地域においても、JASRACや中国のMCSC(中国音楽著作権協会)等著作権管理団体が音楽創作者の権利保護と適正な報酬の請求を目指し、日々努力を重ねている。しかし、世界全体からみれば、市場に対する音楽創作者の権利保護の水準は低いと言わざるを得ない。こうした状況を打開するためにも、この地域の音楽創作者自らが声を上げることが不可欠であることはだれの目にも明らかであった。
このときから、この地域に音楽創作者の連盟を旗揚げすることが私の大きな使命となり、およそ二年間にわたる各方面への働きかけの結果、遂にAPMA設立のときを迎えることができた。
今年、APMAはその大きな一歩を踏み出す。五月韓国・ソウルでの執行委員会や、十一月CIAM総会と合わせた東京での執行委員会・総会における声明の発表や各種イベントを通じて、私たちの声をアジアへ、そしてアジアから世界へ発信していけるよう、APMA会長として全力を傾ける所存である。<とくら・しゅんいち>
平和を誓う年
(No.851 2017.2.1より)
日本中国文化交流協会副会長俳優
栗 原 小 巻
春節に当たり、謹んで、新年のお祝いをお伝えします。
2017年が、日中両国の友好と、平和を誓う年になる事を願っています。
日中両国民の相互の尊重と、一人一人の緻密な交流は、政治の息苦しさを圧倒します。
これまで、日中友好に尽くされた方々は多くいらっしゃいますが、長谷川テルさんもそのお一人です。長谷川テルは、平和の実現に命がけで尽くしました。エスペランティストとして、戦火の上海、重慶にて、世界に、戦争の悲惨さを、ファシズムへの恐怖を、手紙で、詩で、作品として発言し続けました。わたくしは、長谷川テルさんの、ご著書を前にすると胸がしめつけられる様な思いをします。
日中合作ドラマ『望郷の星』で、長谷川テル役を演じたご縁で、テルさんの遺児、長谷川暁子さんと知遇を得ることが出来ました。昨年12月に『松井須磨子』京都公演を観劇していただき、お話をする時間を作っていただきました。
長谷川暁子さんは、心打つ作品『二つの祖国の狭間に生きる』を書かれ、関西の大学で、教育者として、若き学生たちの指導に当たられています。暁子さんにとって、テルは誇りであり、テルもまた暁子さんを誇りに思っているでしょう。日中友好の重い歴史を感じています。
『松井須磨子』は、昨年夏の九州から始まり、11月に四国、12月に近畿と、56ステージ公演しました。10月には、日中文化交流協会60周年記念交流事業として、素晴らしい俳優でもあられる濮存昕さんのご好意で、北京菊隠劇場での公演が実現しました。尊敬する、唐家?先生、孫家正先生両先生のお心配りご決断、長い友人李華藝さんのご尽力、中国の皆々様のご協力があって、公演無事に終えることが出来ました。
演劇公演の翌日、シンポジウムが開かれました。文化芸術に関わる出席者の皆様の一言一言が、胸に染み入りました。
わたくしが、日中友好の歴史を学んだ『時は流れて』の著者であられる、尊敬する劉徳有先生も、ご出席下さり、ご発言に感動いたしました。
劇中劇の細かい分析、松井須磨子が担った、社会的意味、女性の自立、独立、そして、わたくし自身の出演した、他の作品にも言及して下さいました。
平和な時代の文化交流に、深く感謝しています。
これからも皆様と共に、日中の友好に少しでも寄与できればと思っております。
時代が暗転しないように。〈くりはら・こまき〉
新しい年に向かって
(No.851 2017.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
日中文化交流協会は、昨年の創立六十周年の節目を経て、次の新しいステージに向かって第一歩を踏み出そうとしている。
この一年の交流は、長く育て続けて来た各界代表団の定期的訪中、同じく中国側代表団の来日、というこれまでの相互訪問という基本的な活動を維持、展開することが出来た。
その上に、記念すべき年にあたって、栗原小巻氏(副会長)の一人芝居の北京公演、前年に続く総勢九十名に及ぶ日本の大学生の訪中と中国の大学生との交歓や意見交換、鑑眞和上像の東渡記念行事などが行なわれ、日本では、「漢字三千年」展の開催が実現した。
日中両国の政治・外交関係が、領土問題や歴史認識をめぐって必ずしも滑らかには運んでいない今日、以前と同様の密接な関係を維持し続けるのにはそれなりの努力が必要ではあるだろう。しかし当協会のメンバーが中国の関係者と顔を合わせて語り合う時、そこにはかつてと変わらぬ親しみや温もりが漂っていた。これが六十年の歴史が生みだした力によるものか、とあらためて感じぬわけにはいかなかった。そして文化交流の営みは、政治や外交や経済の動きとは別なのだから、両国関係が滑らかに進まぬ時も積極的に活動を展開してくれ、といった協会外部の意見に接する度に、文化交流の力が、どこかで政治や経済の営みにも影響を与えるようにはならぬものか、といった夢の如きものが生まれてくるのを覚える。
英国のEU離脱の動きや、アメリカの大統領選挙の動向などを伝えるニュースに接する度に、世界は今や大きく変りつつあるように感じる。地震や津波、原発事故といった大問題を抱える日本も、この先どう生きるか、を深刻に摸索せざるを得ない地点に立っている。そして中国も、様々な問題を抱いたまま、この先の進路を懸命に探っているかに見える。
そのような時代、情勢、環境の中をどう生きるかは、国を超え、民族を超えて人類が取り組まねばならぬ課題であるに違いない。その中の一つの大切な繋がりとして、日本と中国の関係、結びつきは歴史の場で確かめられていくに違いない。
日本中国文化交流協会の、六十年を経て新しく迎えるこの年は、希望に満ちているなどとはいえまい。しかしそうであればあるほど、希望を求め、希望に向かう道を探り続けることが求められているといえよう。その営みの一年がここに始まったのだ、とあらためて感じる。
〈くろい・せんじ 作家、日本藝術院長〉
人的交流が大切
(No.849 2016.12.1より)
明治大学国際総合研究所特任教授
川 口 順 子
今年九月、甘粛省の敦煌と陝西省の西安を初めて訪れる幸運を得た。日本経済新聞社の平田保雄顧問を団長とする訪中団に参加したもので、シルクロードの要衝であった二つの街が交流の要として、アジア発展のために如何に大きな役割を果たしてきたかを実感することができた。一週間にわたる楽しい旅は、私の好奇心を大いに駆り立て、敦煌と西安で実見した壁画や各種文物から、中国文化の多様性を肌で感じ、日本へ戻ってから西域の歴史をもう一度学び直したいと思ったほどである。印象的だった事を二、三記したい。
西安で見た兵馬俑や陝西歴史博物館の唐代壁画は言葉で表現することができない位素晴らしかった。もう一つ心に残っているのが隋代建立の青龍寺(唐代に改名)である。空海が学んだ寺院で、その後の戦乱で焼失したという。国交正常化後、四国四県の人々が中心となって中国側に働きかけ、青龍寺が再建された。今では、四国八十八カ所の零番札所にもなっている。昔の交流が今の交流につながっていることはうれしいことだ。
ユネスコの世界文化遺産になっている敦煌莫高窟では、四世紀から千年にわたって描かれた壁画群を見せていただいたが、その規模、内容は圧巻だった。数百年の眠りから莫高窟が再び世界に注目を浴びるのが、一九〇〇年の蔵経洞の発見によってであるが、日本では井上靖の小説や平山郁夫画伯の作品により、敦煌の魅力が知れ渡った。その壁画や仏像はインドやペルシャの影響が色濃く見られ、また奈良や京都に残る仏像や絵画とも相通じていた。インドで誕生した仏教は、中国、朝鮮半島、そして日本へと伝来し、各国固有の文化、習慣と融合し発展してきた。この仏教交流の流れは、千数百年という時を越え、今日に至るまで絶えることなく続いているのだ。
私が初めて中国を訪問したのは通商産業省(現経済産業省)在籍中の八十年代初めで、自動車ではなく自転車の大群を目にしたことを鮮明に記憶している。その後、森内閣および小泉内閣において、環境大臣、外務大臣を拝命し、中国を何度も訪れるようになった。外務大臣在任中に唐家?外交部長及び李肇星外交部長と諸問題のやり取りをしたことが昨日のことのように思い出される。
今回の訪中で、悠久な日中交流の歴史と文化交流の厚みを実感した。中国は国土の規模が大きく、異民族の侵略を何度も受けており、日本とは異なった歴史を有している。体制の異なる日本と中国が関係を良好に発展させていくためには、日中関係の観点からのみでなく広い視野で互いを見る相互の努力が必要であると思う。意見の不一致や互いの短所だけを取り上げるだけでは進展は望めない。一人でも多くの人が訪問し、両国の千数百年にわたる交流の歴史を認識し、心の触れ合いを持つことこそが重要ではないかと思う。<かわぐち・よりこ>
「文化交流」の力
(NO.848 2016.11.1より)
日本中国文化交流協会理事
日本女子大学教授
成 田 龍 一
はじまりは、2004年10月に篠田正浩団長のもと、上海、西安、北京を訪れたときからである。ともすれば政治に翻弄されがちで、経済的な効率を持ちだしてきた日中関係のなかで、「文化交流」をメインのゲートとすることの意義と重みとを感じた。
以来、そうした姿勢を学ぶなか、日中間の「文化交流」の軌跡を辿る格好のシリーズに接した。今年3月から刊行された張競、村田雄二郎編『日中の120年 文芸・評論作品選』(岩波書店)である。日清戦争前後から現在までの日中関係を論じた、様々な書き手による「各種ジャンルの古典的資産」といえる80篇以上を選択し提供している。収録作家は、日中の比率がほぼ同数になるように工夫され、ここ60年に限っても、巴金、開高健、堀田善衞、武田泰淳、孫平化、張承志らの文章が並ぶ。
全体は「共和の夢 膨張の野望」、「敵か友か」、「侮中と抗日」、「断交と連帯」、「蜜月と軋み」と時代別に全5巻で構成され、この間の日中関係の軌跡が端的に表現されるが、同時期の双方の文化人による文章をあわせ読むことにより、その対応関係――「交流」の様相がうきあがる。
もっとも、実際にページを繰って行くと、両国の関係が決して一筋縄ではいかないものであったことがわかる。認識がすれ違い、噛み合わず、異なった姿勢が目につく。対抗や断絶もみられる。また、従来の思想史や文学史に登場してこなかった作家名が散見され、中国との関係を軸とした思想・文学が、なかなか主流となってこなかったことも窺い知れる。
しかし、双方には、真摯な姿勢があった。たとえば、第5巻「日中国交正常化」の項には、中島健蔵、永井陽之助、衞藤瀋吉、竹内好、遠藤三郎、張香山の文章が収められている。そのなかで、中島は「未来に向かって胸を張って歩きだすため」「どうしても必要な反省」(71年)を説いていた。こうした姿勢が、他の日本側の論者にもみられる。
だが、いまや、いわゆる「嫌中本」が溢れ返るまでに、事態は転変してしまっている。第5巻はタイトルに「軋み」が記されるほか、各章にも「陰影」「暗転」「揺れる日中関係」という文字が並ぶ。そうした状況であればこそ、いまこそ「双方の他者認識を総点検」(編集部「刊行にあたって」)する営みが求められよう。日中間の「文化交流」の厚みを知り、この財産をいまのものとし、さらに増していかなければならない。竹内好は「中国との講和に役に立つ資料集のようなもの」をつくろうとしたが、「いかにその種の文献が少ないか」を憂えている(72年)。歴史を学び、文化交流の軌跡を知ることの意味をあらためて説くのである。
このシリーズで取り上げられている、中島健蔵、亀井勝一郎、井上靖、水上勉、司馬遼太郎、加藤周一、辻井喬、そして現会長の黑井千次らの諸氏が、日中文化交流協会の中心的な指導者であったことも重要である。協会が培ってきた信頼と関係の分厚さという財産をもとに、困難な〈いま〉の事態を相対化し、切り開いていくことが喫緊の課題ではないだろうか。〈なりた・りゅういち 近現代日本史〉
いま漢字を考える
(NO.847 2016.10.1より)
京都大学大学院教授
阿 辻 哲 次
「漢字三千年」と題する展覧会が、まもなく開催される。さまざまな領域で、中国文化の神髄をあますところなく示す数多くの展覧会が、これまで日本各地でなんども開催されてきた。それらはいずれも、日中両国の相互理解に関して非常に重要な成果をあげるものであった。だが日中両国の文化的営為の根源に数千年の時間にわたって存在する「漢字」だけに焦点をあてたイベントは、これまでほとんど開催されたことがなかった。
今回の展覧会は、その「漢字」だけに焦点をあてておこなわれる。中国人民対外友好協会と中国各地の博物館の協力を得て招来される主要な展示品には、最古の漢字である「甲骨文字」や殷周時代の「金文」、戦国時代の竹簡、文字が刻まれた兵馬俑、前漢の「馬王堆遺跡」から発見された帛書(絹に書かれた書物)、長安で逝去した若き遣唐使を悼んで作られた墓誌、則天武后が天地の神に捧げた純金製の祭文など、一つ一つあげていくときりがないが、これまでほとんど門外不出だった貴重な文物100点あまりが一堂に会するのは実に空前のことである。
中国は文字の国である。そして日本も非常に早い時代に中国から漢字を受容し、それによって高度な文化を発展させてきた。しかしそんな中国や日本においても、漢字だけが勝手に一人歩きしてきたわけではない。漢字はいつの時代でも、人間の活動とともにあった。それは国家を統治する法律を記し、人々の生活に幸福をもたらすための制度や契約を記すのに使われた。漢字を使って数多くの書物が書かれて学問と科学技術が発展し、文学や書道・絵画などの芸術的領域においても漢字から高度な達成が生まれてきた。そして漢字がもつ役割と使命は、これからの時代においても、なにひとつ変わるところがない。
第二次世界大戦がおわってからのアジアには、漢字は国家の進歩をさまたげる諸悪の根源だ、という議論があった。漢字廃止論の論拠のひとつに、漢字は機械では書けないという事実があった。その主張は、過去において確かに事実だったが、しかしそれは永遠の真理ではなかった。技術の急激な進歩とともに、今ではごく小さなコンピューターで大量の漢字を簡単に処理できるようになった。
技術革新と社会の変化によって機械が漢字を扱えるようになるとともに人々の漢字に対する認識が変わり、漢字廃止論の前提はあっさりと崩れさった。こうして漢字は復権をとげた。しかし過去の伝統的文化へのまなざしを持たない復権は、底の浅い、きわめて脆弱なものとなるだろう。
漢字の未来は過去の延長線上にある。その当たり前のことを、今回の展覧会はしっかりと気づかせてくれるであろう。〈あつじ・てつじ 特別展「漢字三千年」監修〉
「希望」の確かな芽生え
(NO.846 2016.9.1より)
日本中国文化交流協会理事 洋画家
入 江 観
出発前夜、ホテルマロウドイン赤坂の広間は「若さ」で溢れていた。 全国27大学から集められた90名の学生の訪中は、日中文化交流協会の実施する訪中団として異例のスケールであった。 壮行会に出席頂いた程永華大使夫人でもある汪婉参事官から「日本の学生には客観的、理性的な中国観を作り上げて欲しい」との挨拶があった。それを受け、私は、日本の青少年が招かれるのは、中国側が若者同士の交流を重視していることの表れであり、政治的関係は常に不確定要因を避けられぬにしても、人や文化の交流を通じた両国民の心のつながりこそが重要であり、大切なことは「自分の眼」で「手触り」の中国を実感することであり、今回は、その貴重な契機となる筈であると述べた。 北京到着後、二班に分かれ、北京師範大学と中国人民大学を訪問し、日本語学科の学生と交流を行なった。グループに分かれての話し合いは抽象的なテーマではなく、学校生活、VOCALOIDの中国における受容、日本のファッション誌の中国への影響、中国・日本の類似語の比較研究等々、日常的、身近な話題について話し合われたことが良かったと思う。日本棋院から推薦された学生による囲碁対戦も行なわれ、勝敗を超えた成果もあったようである。 その日の夜、中日友好協会主催の歓迎会で宋敬武対外友好協会副会長から次のような歓迎の挨拶を受けた。 「青少年は未来と希望であり、中日友好は若者により受継がれ、発展させられなければならない。私は代表団を迎えるたび、若者の真摯で、温かな交流の雰囲気に胸を打たれ、青春の活力や生命の炎を感ぜずにはいられない。両国の若者が相互理解を深め、友情を築き、友好の大木が成長し続けることを期待している」 答礼に立ち、私は司馬遼太郎氏の談話を引用して、民族論や国家論だけのレベルで他の国を見ると間違うことがある、大切なことは「住民」の感覚で中国を見ることであり、それこそが各々の手で相手に触れることになる訳で、その機会を与えて頂いたことに心から感謝すると述べた。 宴会の間、両国の学生が披露したパフォーマンスは、そのために取り繕ったものではなく、器楽演奏、日本舞踊、タップダンス、ストリートダンス等、各々の日常の中での修練の成果であり、見応えのあるものであった。昼間の討論に続き、日中大学生の交流の深まりは明らかであった。 帰国後、協会に寄せられた感想文からは、参加者の一人一人が、メディアによる情報から踏み込んで、自分の眼で中国を見て、自分の手で中国の人々に触れた実感が確実に伝わって来た。個人的な交流も芽生えていることも確認でき、短時日の交流であっても、友好への確かな種が蒔かれたことは疑う余地が無い。 出発前夜、若者たちの中に、私が感じた漠然たる思いは、「希望」というものであったことが明らかになった気がしている。 〈いりえ・かん〉
記憶から経験が失われる時
(NO.845 2016.8.1より)
作家 中 沢 け い
中国からの留学生の姿が大学で目立つようになった。私が教員として勤務する法政大学にもたくさんの中国人留学生がいる。ここ十年ほどの傾向だ。出身地もいろいろで、雲南省から来たという学生もいれば、延辺出身だという大学院生もいる。それぞれに個性に富み、日本の生活をおおいに楽しんでいる様子を見ているだけで楽しくなる。総じてお洒落で、アニメやゲームなど日本の現代文化には旺盛な興味を示す学生も多い。その積極的な探求心は日本の学生にも良い刺激となっている。かつて、中国は日本からの旅行者さえ受け入れてなかったことを考えれば、時代を大きく変わったと言えるだろう。
今年は戦後七十一年目である。戦後七十年の安倍首相談話がいかなるものになるのかが注目された節目の年よりも静かな終戦の夏が近づいている。戦後七十年と聞き、思い出したのは、私自身が高校に通っていた時分のことだ。もう四十年も昔のことになる。その時分には戦争中、中国戦線へ配属されていた先生たちが教壇にたっておられた。教室で戦争中の体験をお話になることはめったになかったが、それでも折に触れ、異国での戦争経験を話されることがあった。顎の下に入った銃弾がそのままになっているという先生もいた。中国文学を学ぶ学窓から、そのまま戦線に出て翻訳など仕事に従事した先生もいた。経験を語る時には声や表情に陰影がでる。ことさらに惨たらしさを強調しなくとも、聞く人の耳に伝わるものがある。
残念ながら経験を語り継ぐことはできても、経験者の声や表情にこもった陰影までは受け継ぐことができない。昨今の日本では外国人を排斥するヘイトスピーチが繰り返されるようになった。戦争の経験を語ることができた世代がいた時代には考えられなような罵詈雑言、誹謗中傷が繰り返される。韓国人を対象としたヘイトスピーチが目立ったが、対象は韓国人には限らない。外国人全般に及ぶ。中国人もまたその対象となった。日本を愉快な国だと感じて旺盛に日本の生活を楽しんでいる中国人留学生が不愉快な思いをすることもあったに違いない。ヘイトスピーチはなまなましい経験の記憶が失われたところから生まれてくる。そこには経験が持つ陰影がまったくない。記憶の中に経験を深く宿した世代が、三十年前にはまだ多かったのだ。高校通っていた頃から四十年の歳月は暴力的で想像力を欠落させた人々によるレイシストを生み出した。
私の世代には戦争の経験がない。それはこの七十年間、平和であったことを意味している。今や、その平和は繁栄という果実をもたらそうという時期を迎えた。繁栄という果実を熟させるためには、経験の記憶ではなく理知の力を必要としている。ヘイトスピーチ対策法が成立したのは、まさにその理知の力によるものだ。世界の中で日本が孤立しないための理知である。〈なかざわ・けい〉
『日本泉屋博古館巻』の
中国での刊行にあたって
(NO.844 2016.7.1より)
住友商事株式会社名誉顧問
公益財団法人泉屋博古館理事長
宮 原 賢 次
このほど、豪華図録『日本泉屋博古館巻』が中国で刊行された。中国国家博物館が出版する海外所蔵の中国古代文物を特集した図録は、英ビクトリア・アンド・アルバート博物館に続く2冊目という。呂章申館長が主編となり、泉屋博古館所蔵の中国古代青銅器、書画等199点の図版を収録、丁寧な解説が付されている。四月に中国国家博物館で発表会が開かれ、泉屋博古館小南一郎館長が出席させていただいた。
本書刊行のきっかけは2010年日本経済界訪中団参加に遡る。日本経済新聞社と日中文化交流協会が毎年実施している旅で、北京、上海、敦煌、西安を訪ねた。砂漠の大画廊と称される敦煌で莫高窟の壁画を鑑賞した夜、杉田亮毅団長を中心にメンバーが酒を酌み交わしながら、見聞の印象や夢を語り合った。医療機器分野で活躍しているメンバーは、アジアの未来を見据えた中国との医療交流をしたいと話された。経済関係で数多く訪中してきた私も、新しい分野で中国と交流ができたらと思った事を記憶している。その後、日中文化交流協会を通じ、中国国家博物館より泉屋博古館の「青銅器」をテーマにした交流の提案があり、11年9月に私と小南館長が中国国家博物館を訪ね、共同研究を進めていく事となり、その中で『日本泉屋博古館巻』刊行協力の打診を受けた。12年には協会の招きで呂章申館長ら同館代表団が来日、実務がスタートした。直後に尖閣諸島問題が生じ、心配していたが、中国側の御尽力もあり、この度刊行が実現した。両国関係方面の皆様に感謝の気持ちを表したい。
泉屋博古館は、住友家15代当主、住友春翠が蒐集した美術品を中心に、1960年に京都の住友本邸敷地の一角に設立された。「泉屋(せんおく)博古館」の名称は、住友家屋号「泉屋(いずみや)」と、約千年前に中国で編纂された青銅器図録「博古図録」に由来している。当館収蔵の青銅器、書画、絵画、茶道具など国宝、重要文化財を含む美術品を季節にあわせ公開している。東京都港区に開設している「泉屋博古館分館」と併せ、来日する中国の方々にも鑑賞していただければと願っている。
私は商社マンとして50年以上にわたり中国とのビジネスに携わってきたが、文化交流の面では、国際民商事法センターの会長という立場を通じ日中の法制度の相互理解のためのセミナー活動を長年行なっている。その御縁で昨年、中国パンダ保護研究センターの四川省雅安壁峰峡基地を訪問し、赤ちゃんパンダに命名する貴重な機会を頂き、私自身の名から「賢賢(ケンケン)」と名付けた。賢という字は賢いと同時に殖えるという意味があるそうで、中国の方からは喜んでいただけた。今後とも、経済と文化の両輪で、中国との交流を深めていきたいと思っている。 〈みやはら・けんじ〉
中国の曲芸と和の語り芸 楽しみな交流
(NO.843 2016.6.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
能楽師
安 田 登
中国から「曲芸」がやってくる。
曲芸といっても、日本語の曲芸とはちょっと違う。中国語の曲芸は、語りと歌からなる「説(語り)唱(歌)芸術」、すなわち歌つきの語り芸をいう。「曲芸」という語はすでに五経のひとつ『礼記』にも見える。由緒正しい系譜をもつ芸能なのである。
すでに本誌四月号で詳細が報じられたが、河南省の宝豊県で行なわれた曲芸の祭り、馬街書会に鑑賞訪中団の一員として参加した。だだっ広い麦畑に、しかし広さを感じさせないほどの多くの説唱芸人たちが荷台付きの車でやって来る。車の荷台を開ければそのまま舞台となる。昔懐かしい紙芝居のおじさんみたいだ。手作りの拡声器を用意し、ガンガン語り歌う。隣の拡声器の音と混じりあい(たぶん言語が理解できたとしても)、何を言っているのかは全然わからない。でも、それはあまり問題ないのだ。ここはお上品な芸術祭ではない。飯をかけた、己れの芸の見本市なのである。客はここに芸を買いに来る。気に入った芸人がいれば交渉が始まる。「俺の親父の長寿の祝いで語ってくれ」、「娘の結婚式で歌ってくれないか」などなど。演じる方も観る方も真剣である。
昔、日本の辻で行なわれた芸人や説教師たちのエネルギーも、さぞかしこんなだったろうと想像しながら見ていた。
そう。曲芸は、日本人の私たちには非常に近しい存在なのである。いや、近しいどころか、日本は曲芸、すなわち歌付きの語り芸がもっとも豊富な国のひとつなのである。古くは『平家物語』を語った「平曲」、さらにはそれに動きが加わった「能楽」。江戸時代には「義太夫」が生まれ、明治になれば「浪曲」が生まれた。さらにそのルーツを探れば、稗田阿礼の『古事記』誦習まで遡ることができるだろう。日本には神代の昔から、節付きの語り芸があった。
しかし、歌付きの語り芸の発生が、中国が先か日本が先かなどということを考えることは意味がない。語りに歌がつくのは必然なのである。
毛詩大序には「詩は志のゆく所なり。心に在るを志と為し、言に發するを詩と為す。情、中に動きて言に形はる。これを言ひて足らず。故にこれを嗟嘆す。これを嗟嘆して足らず、故にこれを永歌す。これを永歌して足らず、知らず、手のこれを舞ひ、足のこれを蹈む」とある。
語りは歌になり、歌は舞になるのは自然の摂理だ。トークはラップになり、バースになり、コーラスとなり、そしてダンスになる。万国共通だ。
むろん、文字を始めとして、多くの文化がそうであるように中国は日本の先生であった。馬街書会でのエネルギーをはじめ、私たち日本人が中国の曲芸の方たちから学ぶことはたくさんあるだろう。
しかし、歴史の波の中で中国では消失してしまったものが、日本に残っているものもある。中国の曲芸師の方たちが日本のさまざまな語り芸に接したときに、そこから何を感じられるか、それをうかがうのも楽しみである。
〈やすだ・のぼる 下掛宝生流〉
鑑真和上像の東渡
(NO.842 2016.5.1より)
日本中国文化交流協会顧問
壬生寺貫主
松 浦 俊 海
日中文化交流協会の創立六十周年を記念して、このたび日中合同により同じ二体の鑑真和上像を中国で制作し、一体が和上東渡を今に再現するような事業が展開されていることは、私にとって無上の喜びであります。
鑑真和上は千二百七十年も昔に中日友好の先駆けとなり、十二年の歳月と五度の挫折にも屈せずに初志を貫徹して七五三年に渡日を果たし、仏教のみならず多くの医薬や先端技術を日本にもたらされました。和上はその後の十年間に聖武上皇、光明皇太后、孝謙天皇始め多くの人々を教化して七六三年に七十六歳で遷化され、故国を遠く離れて日本の土となられたのです。和上の御廟は唐招提寺御影堂の東、苔の緑が素晴らしい林の奥にあります。
和上遷化の直前に弟子達によって作られた肖像は、脱活乾漆造りで日本最古の肖像として国宝に指定され、重要文化財の御影堂に安置されています。
和上が七五九年に創建されたこの唐招提寺は南都六宗のひとつ、律宗の総本山であります。
かねてから私は、律宗寺院において宗祖の鑑真和上像を本堂でお祀りしている事が少ないのを懸念してきました。他宗派寺院の本堂では、本尊に次いで必ずや宗祖の像を安置しているのです。
二〇一四年十月、日中文化交流協会による、「鑑真和上の中国での足跡を尋ねる旅」の中、揚州から和上が東渡の際に乗船された埠頭の前にある文峰寺と壬生寺が提携寺院として調印しました。今後両寺は、同一の鑑真和上像を安置して末永く共に和上の遺徳を偲んで顕彰し、日中友好親善の共同事業を計画、推進する事になりました。
一九八○年四月、当時唐招提寺の森本孝順長老は前々年に来日した鄧小平氏に嘆願し、和上像を中国に「里帰り」させました。その時から、大明寺の鑑真記念堂前と唐招提寺の御廟の前に同一の灯籠が置かれて、両寺ではこの灯籠に毎日蝋燭の火を灯し続けています。それはともに和上の遺志を引き継いで行く誓いのしるしであります。このことにあやかって今回の鑑真和上像は寸分違わない同一のお像としました。
またこれも鑑真和上が第十次遣唐使船で来日された故事から、KADOKAWA (角川歴彦会長)が二〇一○年の上海万博の際に復元建造された遣唐使船が提供され、鑑真和上像の乗船式が行なわれ、次にお像は中国の定期フェリー船「新鑑真号」により、上海から海路で大阪へという、和上東渡を再現する計画です。
鑑真和上の遺徳により、「共結来縁」(共に来縁を結ばん)の絆が時空を越えて多くの人々と結ばれる事を切に願う次第であります。
〈まつうら・しゅんかい 唐招提寺第85世長老〉
国を超えた曲芸の交換を
(NO.841 2016.4.1より)
作家 いとうせいこう
二月下旬の六日間を中国で過した。まずは河南省鄭州、平頂山、そして江蘇省蘇州で。どちらも民間の芸能を聴く(見る)ためである。
特に平頂山宝豊県では馬街村という場所へおもむき、土煙の舞う広場に続々と集ってくる全土の芸人たちの二胡、三弦、思い思いのサウンドシステムで歌い語る者の声に酔いしれた。芸人たちはおおむね土埃にまみれており、手作りの衣装に身を包む女性や子供の他にはまるで地の底から出現したかのような男たちばかりであった。
曲芸、とくくられている。私たち日本人が想像するものと違い、それは歌であり音曲である。同行した能楽師・安田登氏、言語学者・金田一秀穂氏らの交わす言葉を盗み聴けば、「曲」とは雑多なことを指すようだ。つまり雑技団の雑である。
とすれば、中国で体験することの出来た雑芸は、日本の寄席でいう色物、さかのぼれば種類の未分類な田楽のようなものかもしれない。いまだ生き残る中国芸人たちは儒教ベースの物語を伝え、『三国演義』のような文芸を語り(とはいえ、各々の訛りと古い言い回しのためだろう、現地ガイドにさえ、何割かしか聴き取れないのだそうだ)、軽く踊ってみせもする。ただし、馬街村は麦の新芽が出る旧正月のまっ盛りで、訪れる見物客(最大で二十三万人という)があちこちに移動するため、麦は踏まれる。強くなる。すなわちそれは農事なのだ。だからこそ私は田楽の起源を思ったのである。稲作ゆえの日本の水と芸能のイメージが、乾いた麦畑と砂塵の芸能とつながるのは大変刺激的なことだった。
村では群衆の中で曲芸博物館を見学し、屋台の活気を味わい、数メートルごとに陣取る芸人たちの演奏、あるいは大ステージで披露される名人たちの楽曲を楽しみ、さらに宝豊県の中心にある新しいホール内で行なわれた漫才、名芸能、コントまで見ることが出来た。
上海に戻って蘇州へ向かった私たちは、評弾と呼ばれるやはり語りと歌の学校や博物館を訪問し、ちょうどひらかれていたまさに中国版の寄席での演芸を堪能したし、中にまじって謡や朗読やその場で借りた弦楽器の演奏を日本代表として披露し返した。すると、カタコトの日本語をしゃべりかけてくる老人がいた。指を立てて誉めてくれる人もいた。浪曲師・玉川奈々福さんにも多くの観客が声をかけたようだ。
まさに民間外交、それも行きあたりばったりのアドリブだらけの、しかし心のこもった芸の贈り物を私たちはし、中国の人々から同じように体当たりの返礼を受けたのである。
これこそが「曲」というものだ、と蘇州の寄席で私は思った。雑であることは粗であることではない。形式から時にこぼれ落ち、伝えようのないものをとるものもとりあえず伝えてみせる。そこに雑の広がりがあり、思いもよらず伝わる何かがある。つまり私たちもまた曲芸団なのであった。
是非とも今後も、国を超えた曲芸の交換をしていきたいものである。
文化の「交流」が初めて実質あるものに
(NO.839 2016.3.1より)
社会学者
大 澤 真 幸
私は、昨年の11月4日から8日、日中文化交流協会代表団のメンバーに加えていただき、北京、成都、そして上海を駆け足で旅行する機会を得た。この旅行のひとつの目的は、団長の磯崎新氏が設計した建築を視察することにあった。私が、他のメンバーとともに見学することができた建物は、二つである。一つは、成都の空港から車で一時間半ほど郊外に行った大邑県にある建川博物館集落の中の建物の一つ。この集落は25もの歴史博物館の集合体で、一種のテーマパークである。その中の、なんと日軍侵華罪行館(日本軍の侵略を記憶にとどめる館)が磯崎氏の設計によるのだ。もう一つは、上海交響楽団音楽庁の建物だ。
これらの建造物を見て、そしてまた建川博物館集落の樊建川館長をはじめとするこれら建造物を活用されている中国側の人々の我々への心からの歓迎を身をもって体験して、私は日本人としてちょっとした誇らしさや喜びを感じるとともに、ある感慨を抱かずにはいられなかった。私があらためて思ったことは、日中文化交流における極端な「貿易不均衡」をやっとほんの少し是正できるところにきたのだなあ、ということである。文化の「交流」がまさにその名の通りの相互性を獲得できるときが、やっと訪れたのである。
文化交流という観点で日中間の歴史を振り返れば、中国から日本への「輸出」が圧倒的に勝っていた。日本は、中国から実に多くの「よきもの」を学んできた。例えば、こうして私が使っている文字も、中国から導入した文字を日本語仕様にカスタマイズしたことで創られたものである。その他、学問にしても、思想にしても、政治や法の観念にしても、日本は圧倒的な中国の影響を受け、中国をモデルとしてきた(それらは、日本に導入されたとたんに相当な改変を被るのだが)。逆に、日本から中国に輸出した文化的な要素はあっただろうか。率直に言えば、つい最近までほとんど何もなかった。中国の方が、文化的・文明的に圧倒的に先進的だったからだ。例えば、われわれ代表団は、この旅行中に、成都郊外にある都江堰を見学した。これは、始皇帝による中国統一の少し前に建設された水利施設である。川を人為的に分流させたり合流させたりすることで、ダムを使わずに水を巧みに管理しており、この施設は今日でも活きている。この施設が建造されたとき、日本列島は弥生時代のごく初期で、「日本人」は原始的な農業しか知らなかっただろうということを思うと、中国の先進性は驚異的だ。
しかし、磯崎氏の建築を見ながら、やっと日本からも文化を「輸出」できるときがきた、という思いを私はもった。つまり、日本はようやく、ほんのわずかだが、文化の面で中国に恩返しできるときにきたのである。文化交流は、どちらかが一方的に学ぶだけのような状況では、決して創造的な結果を生まない。今や日中は、歴史上初めて、真に文字通りの文化の「交流」をなしうるときを迎えたのだ。
〈おおさわ・まさち 元京都大学教授〉
若者たちがつむぐ未来
(NO.838 2016.2.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
佐 川 光 晴
「皆さんにお願いしたいのは、自分の目で、今の中国の姿をよく見ていただきたいということです。そして、中国の大学生たちと積極的に交流してきてください」
昨年の十一月二十二日、中国大使館の広間で、郭燕公使は日中文化交流協会大学生訪中団の団員四十六名に語りかけた。首都圏、中部、関西の十九の大学から集まった学生たちは女子が二十八名で、男子は十八名、中国に留学経験がある大学院生から、今回が初の海外という一年生までバラエティーに富んでいる。
二十四日の午後、我々一行は北京にある国際関係学院を訪れた。中国教育部直属で、ハイレベルな国際交渉に当たるエリートを養成する大学だというので私はおっかなびっくりしていたのだが、迎えてくれた日本語学部の学生たちはシャイでおしゃれな若者たちだった。グループに分かれてのディスカッションのテーマも恋愛や部活についてといった穏やかなもので、我々と親しくなろうとする意欲が伝わってきた。学生食堂に場所を移しての交流夕食会では、日中の大学生たちはすっかりうちとけて笑いあっていた。国籍の違いや政府間の軋轢にとらわれない若者たち姿に、私は感激した。
二十五日は飛行機で四川省に向かい、綿陽市にある西南科学技術大学を訪問した。こちらでも前日に倍する大歓迎を受けて、交流会では双方が歌や踊りを披露しあった。楽しい時間は瞬く間に過ぎ、午後八時に別れの挨拶をして建物の外に出ると、夜空にはまるい月が輝いていた。
「蜀犬、日に吠ゆる」の諺が示すように、四川省では滅多に空が晴れない。綿陽の夜空に月が出たのは、十一月下旬にして、今夜が今年初めてとのことだった。
「天も祝福してくれているわけですね」
私は秘書の竹本さん、倉本さん、山本さんと二日続けての盛会を喜びあったが、日中の大学生たちは月を見あげるどころではなく、並んで写真を撮ったり、メールアドレスを交換したりと、バスが出る直前まで別れを惜しんでいた。
一週間に及ぶ訪中の間、日本の学生同士も実によく話をしていた。異なる大学の学生と知り合う機会はあまりないうえに、中国を旅する緊張感がお互いをより親密にしたのだろう。大雪が降ったおかげで北京の大気汚染はまぬがれたが、二〇一二年の反日デモの記憶は生々しい。実際、中国人民対外友好協会は最大限の配慮で我々の安全確保に努めてくれた。程海波副秘書長をはじめとする皆様のご厚意に改めて感謝申し上げたい。
訪中団に参加した四十六名の大学生たちは、短い期間とはいえ、中国の現実に肌で触れた。中国の各地で結ばれた若者どうしの縁からどんな未来が生まれるのか。大いに期待しつつ、私も創作に励もうと思っています。 〈さがわ・みつはる 作家〉
創立六十周年にあたって
(NO.837 2016.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
今年は当協会の創立六十周年にあたる。この歳月は日本と中国との古来よりの交流の歴史を振り返れば、束の間であるとしても、人間でいえば還暦にも相当する節目の年である。
そしてその間、建国以来の新しい中国を日本政府が認めようとせずに往来が容易ではなかった時期、文化大革命によって中国の国内が混乱していた時期、国交が正常化して様々な交流が花開いていった七十年代後半、その後も歴史認識や領土問題が生じ、この歳月も決して平坦なものではなかった。双方の政治や経済の変化もあった。それを顧みれば、よくぞ折々の困難や様々の障害を乗り切って今日まで来ることが出来た、と思わずにいられない。創立時、会員の会費で運営する民間団体のわが協会が、六十年も存続すると思った人は一人もいなかったのではあるまいか。
今日の日中文化交流協会があるのは、協会の趣旨に賛同して支えて下さった会員の皆様の支持と協力、折に触れ協会の活動を支援して下さった各界、各層の方々、そして交流の相手方である中国関係方面の皆様の心温まる対応があったからこそである。この節目の年にあたり、それらの方々にあらためて心からの感謝の意を表する次第である。
また、協会の先頭に立って指導された中島健蔵、井上靖、團伊玖磨、辻井喬ら歴代会長や役員諸氏の努力、創立以来一貫して歴代会長を支え続けた事務局長の白土吾夫氏、その白土イズムを継承している事務局の日々の仕事の積み重ねがあったことも忘れてはならない。
ここ二、三十年ほどの間に、内陸と沿海部に発展の差はあるとはいえ、中国の人々の暮しの様相や街並みが激変している。昨今の両国関係の悪化にもかかわらず、中国からの観光客の激増の動向を見ても、両国の関係は質的に変化して来ていることがうかがわれ、そして今後も更にダイナミックな変化を遂げていくだろうことが予想される。そしてその動きの中で、文化の役割はますます重要になっていくに違いない。これまで六十年の交流の歴史は、今後も起きるであろう様々な困難や問題に対処する際の貴重なヒントになるし、また新たな交流を創造していく上での頼りになる財産ともなるだろう。
人は変り、社会構造も変化していく。当協会も先人の精神を受け継ぎながら、時代の変化にしなやかに対応していく柔軟性が一層必要となるに違いない。
今年、創立六十周年を記念する各種展覧会、各分野の代表団、訪問団の相互往来など、様々な事業・企画の準備が、関係方面の団体、個人の理解と協力を得て進められている。それらの一つ一つが成功し、文化交流の果実として稔り、更には貴重な歴史として今後に伝えられることを願わずにいられない。
<くろい・せんじ 日本藝術院院長、作家>
「望月望郷詩碑」建碑25周年にあたって
(NO.836 2015.12.1より)
一般社団法人日本書道院会長
日本中国文化交流協会常任委員
中 村 雲 龍
日中文化交流の先達ともいえる阿倍仲麻呂を顕彰する「望月望郷詩碑」を中国江蘇省鎮江市の風光明媚な北固山に建立したのは25年前の1990年のことであった。この碑は、日本書道院が日本中国文化交流協会とともに、中国側と協力して建碑したもので、碑額の題字を趙樸初中国仏教協会会長が、正面の碑文「天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山にいでし月かも」の日文を田中凍雲日本書道院会長が、中文を沈鵬中国書法家協会副主席が揮毫した。当時日本書道院副会長であった私と鎮江書道界の重鎮であった李宗海氏が碑の裏面に建碑記を担当した。日本側から119名が参加して盛大に行なわれた除幕式の情景が今でも目に焼き付いている。
私ども日本書道院の田中凍雲会長が昨年11月に101歳で大往生された。本来なら今年は建碑25周年を盛大に祝いたかったのだが、田中前会長を偲ぶ会の開催などが重なって準備が充分にできず、日本書道院の30名余の有志を募って鎮江を訪れることとなった。日中文化交流協会には事前に鎮江市側との連絡をしていただき、中野暁専務理事に御同行いただいた。到着した夜に開かれた祝賀夕食会では、出席していただいた鎮江市人民対外友好協会の張国雲副会長、郭桂鳳副秘書長、石碑の設計者である王亜楠氏、北固山公園の責任者王智慧女史、そして曹松筠鎮江中国旅行社元社長と建碑前後の想い出や、今後の交流の抱負を語り合った。
4半世紀が過ぎ、日本も中国も大きく変わった。今年10月初旬の1日足らずの鎮江滞在ではあったが、久しぶりの市街は他の中国の都市同様、高層ビルが林立し、別世界のように発展していて驚かされた。翌早朝は北固山に登り、白い大理石の「望月望郷詩碑」と久しぶりに対面した。歳月の経過で一部の刻された文字の色が褪せてはいたが、逆に風格を醸し出していた。
私ども日本書道院は昭和27年(1952年)の設立以来、書芸術の故郷中国との交流を促進してきた。その交流の一大事業として奈良時代の遣唐留学生である阿倍仲麻呂を顕彰する「望月望郷詩碑」を建立した。仲麻呂は中国では晁衡/朝衡の名で知られ、科挙に合格し唐朝において諸官を歴任、玄宗に仕えるほどの高官に登った。日本への帰国を果たせずに唐で客死したが、「天の原ふりさけみれば春日なる~」の歌が残されており、千数百年後に生きるわれわれの胸にも当時の望郷の心境が伝わってくる。李白、王維ら数多くの唐詩人が残した漢詩からも仲麻呂との親交の深さを窺い知ることができる。この詩碑が今後とも日中友好の象徴として一つの役割を果たしていくものと願って止まない。5年後には、書道作品の交流展を開くなど、ぜひ建碑30周年を盛大に行ないたいと思っている。<なかむら・うんりゅう>
悠久の時を越えて
(NO.835 2015.11.1より)
日本中国文化交流協会副理事長
東京藝術大学教授
永 井 和 子
朝十時五分羽田発―十二時五分上海着。中国は本当に近い。そう、入口までは―。そこから計り知れない広大な中国が広がっている。今回はどんな中国と出会うのだろう・・・。
旅の第一歩は上海博物館。何回観ても圧巻である。今回は範囲を絞り、じっくり見る事にした。時を越えて残されて来た文物の素晴らしさに改めて感動すると共に、これらを創った人々の事に想いを馳せていた。当然その時代に日常使われる必需品として、あるいは生活を彩る装飾品として創られたものであろう数々の品を通して、当時の人々の呼吸や美意識を感じ、正に時空を越えて私の思考や感性が遊ぶ楽しいひと時となった。
また、現代最新建築の代表とも言える上海交響楽団音楽ホール(二〇一四年オープン、設計・磯崎新当協会顧問。音響・豊田泰久氏)を参観。オーケストラの本拠地であり大・小二つの演奏会用ホールを有する。地下四階、地上二階。広大な敷地の立地由、地下と言っても採光充分な視界も広がる緑の空間があり、地下に降りている感じが全くない。その地下部分にオーケストラのリハーサル室が見事に完備されている。上海交響楽団は一八七九年設立のアジアで最も歴史ある楽団の一つである。在りし日の團伊玖磨先生(元当協会会長)がこのオーケストラを指揮し、御自身作曲のオペラ「夕鶴」公演(一九七九年)をこの地で行なった話を思い出した。つう役は伊藤京子(当協会副会長)、中澤桂両先生。国交回復してまだ浅い時代の先達方の熱意を想像した。我が師でもある伊藤京子先生に今回の旅で厦門を訪れる旨をお伝えした所、先述の「夕鶴」公演の折、子供の役は現地中国の子が担ったが、その指導に当たった指揮者の鄭小瑛女史が厦門在住と伺った。残念ながら今回はお会いする事は叶わなかったが、目に見えずとも様々な所に息衝いている人と人との関わり、繋がりを感ぜずにはいられなかった。
旅の半ば、童心に帰り心底楽しんだ場所がある。厦門文化芸術センターで中国漳州木偶劇団の布袋木偶劇を鑑賞した事だ。小さな展示室の様な部屋にひっそりと、間口一間程の可愛らしい舞台が赤い緞帳を降ろして私達を待っていた。人形を扱う点では日本の文楽に似ているが、文楽の様に一体の人形を二人、三人がかりで操るのではなく、一体の人形を正に一人が五本の指を駆使し、両手で巧みに人物を表現する。この日は『水滸伝』から「大名府」の物語。門番の役人を演じた庄陳華氏は国家一級俳優で国家無形文化遺産である布袋木偶劇を継承する国宝級の方である。御年七十一歳。観劇後に人形を持たせて頂き、指を入れ、庄陳華氏が直々に扱い方を教えて下さった。
小柄ではあるが、肩や腕の筋肉は相当に強固な印象であった。私が巧みに動くその指に触れたくて握手を求めると、快く応じて下さった。指の先は固くタコの様な部分があったが、意外にもその手の平は柔らかく温かだった。庄陳華氏のチャーミングな笑顔と相俟って、ほのぼのとした心持ちでお別れした。実はこの日の観客は我々日中文化交流協会代表団の五名のみ。普段は隣の市に住む庄陳華氏は、何と私達の為にこの日この場所に出向いて下さっての実演だった。本当に貴重な体験であり心に感動を刻む出会いとなった。
この誌面に書き切れない沢山の歴史的文物に触れる中で、悠久の時を越えて人々の息遣いが伝わってくる、そして今を生きる人と人とが国を越えて触れ合う素晴らしさを再確認した旅であった。〈ながい・かずこ 声楽家〉
中国青磁の故郷 龍泉を訪ねて
(NO.834 2015.10.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
入 江 観
今回の旅が、かねて再訪を望んでいた杭州から始まったことが嬉しいことであった。
浙江省外事弁公室が用意してくれたホテルは緑豊かな木立に囲まれ、繁忙の日本から逃れるよう出かけた私達は、いきなり安らぎの中に迎えられた思いであった。その上、翌朝、西湖の湖上は霧雨に包まれ、私たちは夢幻の世界に誘われつつ「青磁の故郷」への旅は始まった。
今回の訪中の成果は何と言っても、中国陶磁の、とりわけ龍泉窯に関する気鋭の研究者である出光美術館の徳留大輔氏が同行してくれたことに負うところが大きかったと言わなければならない。参加者の全員が、徳留氏の懇切な説明を通して、青磁に対する知見を深めることが出来たと思う。私自身、単純に澄んだ緑青色と決めつけていた青磁が実は、黄褐色を帯びた越窯のもつ味わい深いもの等、多様で幅の広いものであることを教えられた。
実際、古い登り窯跡に佇んでいると、古の工人たちが生き生きと立ち動く姿が想像され、彼等の一人一人に尋ねてみれば名前の無い人は居ない筈だが、彼等の作った物に、彼等の名前が残されてはいない。名前が消えてなお残されたものが、今私たちの前にあることの意味は、現代の芸術の有りように厳しい示唆を与えることにもなり、粛然たる思いに駆られるばかりであった。
これは、中国に限ったことでもなく、陶磁器に限ったことでもないが、しばしば、優れた芸術作品が生まれる背景には、権威、権力の保護があったことは、まぎれもない事実であるが、「形」をつくることに於いて、作者は自由であったことも事実であろう。
唯、青磁の故郷を巡って、気づいたことは、そこで生まれた超一級の作品は、その故郷にとどまることが出来ず、故宮博物院やその他、外国の博物館に旅立たざるを得ない皮肉な宿命を持っているということである。又、中国工芸美術大師の称号を持つ二人の作家のそれぞれ美術館を備えた仕事場兼住宅を訪問し、その宏壮さに驚かされたこともあったが、そこでも青磁の伝統は見事に受け継がれていることが理解された。
本来、器は使われるべき役割りを背負っている筈だが、今回、私が龍泉の博物館で出会った、平明な中に深さを湛えた葵口碗等、時間が許されるならば、いつまでも向い合っていたいと思わせる力は一体、何なのかと思う。移ろい易い政治とは別次元で、私たちの文化交流の本質的な基盤は、こういうところにあるのだと確認せざるを得ない思いであった。
今回の訪中にあたって、浙江省各地の関係者の方々に温かいもてなしを頂いたこと、とりわけ外事弁公室の陳福弟、陳燕虹両氏には、上海の空港の出迎えから、見送りまで、全行程にわたって、終始、誠意に充ちたお世話を頂き、私たちの旅を実りあるものにして頂いたことに、心からの感謝の意を表したい。
〈いりえ・かん 洋画家〉
優れた文化の共有を
(NO.833 2015.9.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
東京藝術大学社会連携センター長
宮 廻 正 明
寧波市人民対外友好協会のお招きにより日中文化交流協会代表団の団長として寧波を訪問した。代表団は私のほか、東京藝術大学社会連携センター所属の4名、中野暁専務理事で構成された。1989年6月に絵画の取材旅行で訪れた時とは隔世の感があったが、天童寺付近の村落は昔の面影が残っておりとても懐かしく感じられた。
今回のきっかけになったのは、4月末に寧波市人民対外友好協会の一行が東京藝術大学の視察に訪れたことだった。同大学社会連携センターで作品の再創作として開発している最新のデジタル複製技術を見て頂き、そこで今後このような技術を使った文化交流が可能ではないかとの提案を受け、寧波で試作品でのプレゼンテーションを行なう機会を得たのだ。
もともと中国仏教の聖地である寧波は、唐代に明州、南宋では慶元府とも呼ばれ、遣唐使や日宋貿易・日明貿易の拠点となり、日本には大きな影響を与えたゆかりの深い町だった。多くの文化的遺産が日本側でも享受されており、中でも仏教絵画や南宋北宋の絵画は、日本文化の根幹をなす精神性にも大きな影響を与えている。また世界的に見てもその芸術性の高さは卓越したものがあり、これからの中国文化が世界に及ぼす影響力は計り知れないものがある。しかしながら、その発祥の地寧波の貴重な作品は、中国各地または世界各地に拡散してしまっている。寧波で生まれ育ったこの世界最高レベルの文化を寧波に戻す方法はないものかと模索した。
そこで、東京藝術大学が開発し、特許を取得した技術によって南宋時代の紅白芙蓉図(国宝)の再創作画(高精細複製画)を作り、寧波を訪問することにした。この作品は東京国立博物館に所蔵され、データが公開されている。東京藝術大学社会連携センターではこれらのデータを利用し、同一素材(絹本)での複製画の制作を試みた。同センターには保存修復の技術や古典技法、表具の技術に卓越した人材が揃っており、ほぼオリジナルと同等の作品を作り上げることに成功した。これまではオリジナルと同一のものを作り出すことはタブーとされていたが、この技術は悪用されない限り国を越えて多くの人々と優れた文化を共有することが出来る。そういった意味では、大変意義のあることのように思われる。
寧波では、天一閣博物館、寧波市美術館、私立華茂美術館、沙孟海書学院、寧波画院を訪問した。持参した絹本、板絵、油絵等の複製画を実際に見て触ってもらい、実感を味わうという具体的な体験をすることにより若い研究者にも大変興味を持ってもらい、貴重な意見交換が行なわれた。
訪中を通して、両国の文化交流の充実が今後一層大切であること、日中で協力していくことを確認した。特に新しい技術を使った文化財の再生事業は、文化財の共有という意味でも両国の発展に大きく寄与するものと期待してやまない。
〈みやさこ・まさあき 東京藝術大学文化財保存学専攻教授、日本画家〉
今からでも遅くはない
(戦後70年特集NO.832 2015.8.1より)
日本中国文化交流協会副会長・理事長
池 辺 晋 一 郎
残念ながら先年逝去された元駐中国日本国大使・中江要介氏にはいくつもの名言があるが、今も印象に残っているのは次のような言葉。「日本が近隣諸国に対し戦後すぐに謝罪を行なっていたら、東アジアのその後の展開は違ったものになっていただろう」。
僕がこの小文を書きかけたころ、本誌の前号(No.831)が届いたのだが、その最初のページの井出孫六常任委員(作家)の文章を読み、実は驚いた。戦後ドイツの歩みかたについて、僕も書きかけていたからだ。従って井出氏と重複するかもしれないが、そのまま貫徹することをお許し願いたい。
旧西独で1969~74年に首相の地位にあったヴィリー・ブラント氏は70年にポーランド・ワルシャワのゲットー英雄記念碑の前に跪き、花を捧げた。
その次代の首相、ヘルムート・シュミット氏が国連で行なった演説の大意はこうだ─「戦後、長い時が経った。しかしドイツが再び過ちを犯さないと確約するには、まだ、短い」。
そして昨年6月、北フランスでの「ノルマンディー上陸作戦70周年式典」にヨーロッパ各国首脳が集った。何とそこに、現独首相アンゲラ・メルケル氏も並んでいるではないか。テレビの映像に、僕は驚愕した。
メルケル氏は、イスラエルへ赴き、ユダヤ人への謝罪をすでに行なっている。先の大戦に関し、「すべてのドイツ人は永久にその罪を負う」という発言もしている。
驚愕と同時に、たとえば中国のどこかで終戦○周年記念行事が挙行されるとして、そこに日本の首相が列席している図を想像できるか、と僕は自問していた。
閑話休題。僕は、日本のベテラン女優たちが毎夏につづけている朗読劇「夏の雲は忘れない」の音楽を担当しているが、「ヒロシマ・ナガサキ1945年」というサブタイトルを持つこの劇は、被爆児童の詩を中心に読まれるもの。すなわち、被害の記憶である。
いっぽう僕は、84年に作曲した混声合唱組曲「悪魔の飽食」に全国の人が集い「全国縦断コンサート」をつづけている際の指揮者でもある。国内のみならず、すでに2度の中国を含む6度の海外公演を成功させてきた。この9月にはハルビン郊外の「731記念館」リニューアル式典に招かれ、300人近くがそこで歌う。これはすなわち、加害の記憶だ。
被害と加害の双方の記憶を語り継がなければならない。このバランスは極めて重要だ。加害の罪を語ると自虐的史観という人がいるが、謝罪が自虐につながると考えることこそ奇妙だと僕は考える。
戦後70年。戦後の史観に恒久的でよりよいバランスを与えることが、今年に課されていると思う。前記の中江氏はバレエ台本作家という文化人で、僕は3作でコンビを組んでいる。かつて日中国交回復が卓球で始まったように、文化が日本及び東アジアに正しい史観をもたらす芽になるかもしれない。中江氏が生きていらしたら、「今からでも遅くはないよ」とおっしゃるのではないか、と思うのである。〈いけべ・しんいちろう 作曲家〉
前事不忘 後事之師
(NO.831 2015.7.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
作家
井 出 孫 六
敗戦から50年目の1995年8月、元西ドイツ大統領ワイツゼッカー氏が来日し、氏の講演を聴く機会があった。彼はドイツと日本の比較から入った。両国は共に第二次大戦の敗戦国で、戦後いち早く復興し共通点も多いが、異なる点をあげると、ドイツは大陸国家で西欧のまん中に位置し、9カ国と隣りあい、大戦中はドイツが占領した。日本は海に囲まれた海洋国家で、国境のない点で英国に近く、先の大戦では大陸や他国の島々を戦場とした。
敗戦後のドイツは9カ国の隣国と国交を回復する外交とそのための賠償に全力を傾けるほかない時間が長かった。最も残酷な戦禍を及ぼしたポーランドには、全権団は12月の雪降りしきる大地にひれ伏して謝罪し、その姿にポーランド国民の怒りは柔らいだ。もちろん真摯な謝罪には心からなる賠償金も伴ったと、元大統領は念をおすように披瀝した。
敗戦から70年目の今年初め、雄弁家の元大統領ワイツゼッカー氏の訃報を知ったが、3月にはドイツのアンゲラ・メルケル女性首相が来日し、東アジアで日中韓など近隣諸国の緊張が高まっている現状をめぐり、「大切なのは平和的な解決策を見いだそうとする試みだ」と述べていることを新聞で知った。ワイツゼッカー氏の講演は炎暑の8月7日だったが、わたしは信州の山から降りてきて拝聴した。だが今年は体調がすぐれずメルケル首相のお話を直接聴けなかったのが残念だ。
今年は戦後70年の刻まれる年だ。この得難い機会に、東アジアの国々の首相が、たとえば8月15日を期して、沖縄でも、広島でも、東京でもよい、一堂に会する。そういう東アジアの平和会議を安倍晋三氏が主催しようとすれば、わたしは信州の山から傍聴のためぜひかけ降りてこようと思う。
メルケルさんは「他の地域にアドバイスする立場にはない」と慎ましやかなことばのあとで、ドイツが欧州で和解を進められたのは「ドイツが過去ときちんと向き合ったからだが、隣国(フランス)の寛容もあずかって大きかった」と語ったそうだが、過去ときちんと向き合ったことが、フランスの寛容さを引き出した。そのことが肝要だ。
戦後70年という年の刻みはおろそかにはできない。戦争体験者は年々その数が少なくなってきている。わたしがきちんと向き合うべき過去は1931年、正確にいえば9月の誕生の日から始まっている。1931年9月18日当時、旧満州に駐屯する日本の関東軍司令部にあって3人の参謀によって企てられた満鉄沿線柳条湖の線路爆破から満州事変とその後の15年戦争が始まった。わたしは誕生の日から幼稚園、小学校、国民学校、そして中学2年の日まで戦争とともに育ったことになる。今年は戦後70年といわれるが、向き合うべき過去はさしあたって、70年をさかのぼったそれ以前の15年の歳月であることを肝に命じなければならないと思っている。〈いで・まごろく〉
父、辻井喬の「第二の祖国」を訪ねて
(NO.830 2015.6.1より)
セゾン現代美術館代表理事
堤 た か 雄
日中文化交流協会の会長を務めた父、辻井喬には、「第二の祖国」と言える国が二つあったと思う。一つは、妹であり私が敬愛してやまない叔母、堤邦子が四十年生きたフランスであり、もう一つが中国である。理由は、文化のために生涯を捧げた父が、中国の「文化の力」に畏敬の念を常に持ち、深い興味を抱いていたからだ。亡くなる三年ほど前から病気を繰り返していた父が生前最後に訪れたのも中国であり、それも詩人辻井喬が初めて受賞した「室生犀星賞」と縁のあるハルピンの地であった。
次男である私が中国を訪問したのは今回が四回目だが、前回が父の訪問に母と同行する形で訪れた二〇〇二年であったから、十三年ぶりの訪中になった。「日本文化の祖国」はどんな変化を遂げているのか、期待に胸を踊らせながら北京首都空港に降り立った私は、空港の近代化に驚いたのも束の間、市内に向かう途中に立ち寄った「宋庄芸術村」の素晴らしさに驚嘆した。ここは約二十年前に価格が安いという理由で数名の画家が家を買って住み始めた農村の一部で、現在では八千人ぐらいの芸術家が一千平米以上のアトリエ兼住居を構え、活発に制作を行なっているのだ。その制作環境は日本より遥かに恵まれている印象を受けた。
翌日はまず中国文学芸術界連合会で文芸評論家の郭運徳氏、中国作家協会で鉄凝主席と会見したが、父が如何に両氏と親密な関係にあったかを認識した。特に鉄凝主席にはご自身の小説も含む文芸誌『人民文学』のフランス語版を頂戴した。その後、中国人民対外友好協会の李小林会長を表敬訪問した。宋敬武副会長、王秀雲中日友好協会副会長が同席し、日中両国が芸術文化を通して真の友好関係を築くことの重要性について有意義に話し合った。会見後は旧国営工場跡地の「798芸術区」で中国現代アートの勢いを目の当たりにした。
続いて訪問した上海では、これも工場跡地の現代アート地区である「M50」を訪問した。四万平米の広大な敷地にギャラリーがひしめき、素晴らしい作品の数々を鑑賞した。印象深いのは建物の外壁に沢山描かれたグラフィティだ。イギリスのバンクシーなど、昨今の現代アートの世界では当たり前になっているが、それでも「M50」のグラフィティには興味をそそられた。また、上海市対外友協にも歓迎夕食会に招かれ、遇建浩、朱政寧両氏や父と親交のあった女性作家、上海市作協主席の王安憶氏らと歓談の一時を過ごした。
今回は短い滞在ながら、錚々たる方々と日中の文化交流と友好について前向きに話し合うことができた。私の専門である現代アートに関しても、中国の現状をつぶさに観察することができた。特に近年の日本ではあまり出会えない「メッセージ性の強い」素晴らしい作品にも出会えたことは大きな収穫である。貴重な機会を頂いた日中文化交流協会と中国人民対外友好協会には感謝の気持ちで一杯である。今後、父の遺志を受け継ぎ、日中文化交流の一助になりたいと思っている。〈つつみ・たかお〉
『周斌回想録』を翻訳して
―戦後日中関係を俯瞰できる「歴史の語り部」の証言
(NO.829 2015.5.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
同志社大学大学院教授
加 藤 千 洋
中国外交部の日本語通訳として長年活躍した周斌氏の回想録『私は中国の指導者の通訳だった―中日外交最後の証言』の日本語版を、このほど岩波書店から上梓した。先に香港で繁体字版が出版されていたが、中国国内での簡体字版はまだ実現していない。歴代の指導者が数多く登場する内容であり、関係部門の綿密な審査が長引いていることも、その一因ではないか。
回想録執筆は2012年秋の日中国交正常化40周年を迎える少し前に思い立ったそうだ。「歴史を正しく伝えたい」との思いからだったという。当時は2年ほど前に起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件をきっかけに日中関係が悪化し、さらに12年夏の日本政府による尖閣国有化によって、40周年記念行事のほとんどが中止に追い込まれてしまう。こうした暗雲を目の当たりにして、1972年の国交正常化交渉で主に外相会談の通訳を担当し、難航した共同声明作りにも加わった経験を持つ周氏としては、何か期するものがあったのではないだろうか。
回想録は半年ほどで書き上がった。周氏は優れた記憶力の持ち主だが、重要な通訳の後には個人的なメモを残した。ご本人は「記憶違いもあるかもしれませんが」と謙遜するが、こうした記録と記憶が興味深い原稿に結晶したのだろう。
私は周氏が外交部を離れ、人民日報社に在職した1980年代後半に面識を得た。回想録執筆を知り、日本語版にする価値ありと判断し、すぐに翻訳(共訳者は中国の若手日本研究者、鹿雪瑩さん)を提案した。邦題を『私は中国の指導者の通訳だった―中日外交 最後の証言』としたのは、周氏が文字通り毛沢東、周恩来、鄧小平らの通訳を何度も担当しており、中国の革命第一世代を肌で知る人物の「最後の証言」になるだろうと考えたからだ。
80歳の今日まで、周氏の1時間以上におよぶ通訳機会は約1万回にのぼる。担当した日本の首相経験者は、北京大学東方言語文学学部を卒業した翌1959年に相次ぎ訪中した片山哲と石橋湛山が最初で、21世紀の小泉純一郎、福田康夫、鳩山由紀夫、菅直人に至るまで20人に近い。通訳人生のハイライトとなったのは前述の北京における田中角栄・周恩来の国交正常化を巡る首脳外交だろう。
こうした「歴史的な現場」を数多く踏むほど重用されたのは、言語能力の高さはもちろんだが、対日外交の司令塔であった周恩来と実務責任者の廖承志の信頼を得ていたからだ。それだからこそと思うが、周氏は外交交渉だけでなく幅広い民間外交、文化・スポーツ交流の現場にも登場している。回想録で紙幅が割かれる日中文化交流協会理事長の中島健蔵、作家の有吉佐和子らとの交遊の思い出からは、単に通訳という職務を超えて、周氏が日本各界の人々と心からの付き合い方をしていた姿が浮かび上がる。
本書の後記にこうある。
「願わくは近年両国間に生じた不正常な情況をできるだけ速く終わらせ、一九七〇年代の国交正常化と日中平和友好条約の『原点』に立ち戻り、確実に『戦略的互恵』を実現する正しい方向へ向かって前へ進みたいと思う」。
戦後70年、日中関係を俯瞰できる「歴史の語り部」の言葉だけに重く受け止めたい。 <かとう・ちひろ>
中国とデザインで繋がっていく
(NO.828 2015.4.1より)
日本デザインセンター代表取締役社長
原 研 哉
中国との付き合いで、深く印象に残っているのは、二◯一一年から一二年にかけて北京、秦皇島、上海の三カ所で開催した個展である。同じ規模のことを日本でやろうと思っても施設が思い当たらない。この個展の開催に、僕は多くの意欲とエネルギーを注ぎ込み、驚くほどの反響と動員を得ることができた。
なぜ、日本でもやらないような規模の展覧会を、中国で開催することに情熱を覚えたのか。それは、この地の歴史文化の厚みと多様性、人の数、さらには、かつてあれほどの先進性をもって世界を席巻した大国の、近代化に乗り遅れたゆえの、歴史文化からの乖離と相克に思いを馳せつつ、むしろそこにこの国の潜在力と可能性を感じたからである。台北の故宮博物院に展観されている歴代中国の所蔵品に触れると、今でも自分の中に確かに存在する文化遺伝子がざわざわとさざめくのを感じる。
北京を訪ねるようになったのは、二◯◯◯年の前後である。北京オリンピックのシンボルマークの設計競技に応じ、最終選考に残ったことで中国はぐっと近くなった。中国初のオリンピックのマークを日本人デザイナーが勝ち取ることは至難である。それでも僕は中国五輪について真剣に考え、応募した。結果は次点となり、優秀賞をいただいた。この経緯から中国のデザイン界と多少の縁ができたように感じている。シンボルマークの発表会は天壇で盛大に行なわれ、授賞式が北京飯店で催された。北京飯店前の大通りがまだクルマで埋め尽くされる前のことである。
同じ頃、自分の作品集が中国で初めて刊行された。依頼を受け、版下を送ってから二年ほど音沙汰がなかったが、無事出版できれば幸運と鷹揚な気分でいたので、出来上がった作品集を手にした時には、中国との関係が深まっていく予感がした。
それを契機に大学で講演を依頼されるようになった。美術系大学の学生数も膨大で、千人を越えそうな収容力のある会場が、立錐の余地なく学生で埋まり、瞳を輝かせて話を聞く学生たちの熱気も心の奥に響いた。やがて、自著の翻訳が繁体語で出はじめ、それが野火のように読まれ広がるうちに、一度是非この地で、充実した個展を開催し、中国の学生や若いデザイナーたちにデザインの本質に触れるメッセージを送り出してみたいという気持ちが高まっていったのである。
当初、会場候補は北京の中国美術館であった。黄色い屋根が翼を広げる鳥のように反り返った中華人民共和国風の建築。ここで文化の未来を標榜するデザイン展を開催するのも面白いと考えつつ、空間を精密に測量し、把握しはじめていた。
その後、天安門広場に近い、アメリカ領事館の跡地で、現代美術が展観できるように再整備された施設での開催を打診され、その空間を見て、展覧会は構想から具体的な計画へと変わった。この現代美術館は中国美術館の分室に相当する。導入部の回廊を入れると四層に分かれる魅力的な空間。その全てを使って自分の作品とデザイン思想を、思う存分に展開してみようと考えたのである。
現在では北京に事務所もでき、仕事を通しての結びつきが深まりはじめている。四年前、魯迅生誕百三十年の記念書籍を、中国の三聯書房と日本の平凡社が共同出版することとなり、造本デザインをお手伝いした。簡潔に極まった、赤い中国語版と白い日本語版。その本は思いがけず、ドイツの「世界で最も美しい本賞」を受賞した。
<はら・けんや>
もう一つの〝中国文学〟
(NO.827 2015.3.1より)
日本中国文化交流協会常任委員
早稲田大学名誉教授
岸 陽 子
昨年八月、北京で中国作家協会主催の第三回「中国文学の翻訳をめぐる国際シンポジウム」が開催された。
主席の鉄凝氏をはじめ、莫言氏、賈平凹氏など中国の著名な作家たちと、アジア・アメリカ・ヨーロッパ・ロシア・中東など世界各国から招かれた中国研究者・翻訳家たちが一堂に会して、それぞれの国における中国文学の翻訳と受容の現状を紹介、さらには歴史や文化の差異に由来する作品理解の難しさ、原作の言語体系の解体と自らの言語による再構築という翻訳作業におけるさまざまな困難など、話題は多岐にわたり、前二回に比べて一段と交流が深められた感が強い。
講演の演壇に立った莫言氏の「すぐれた翻訳がなければ〝世界文学〟は生まれない」という発言は、翻訳者たちの志気を鼓舞したが、それに続けて「翻訳者はなによりもまず原作の〝信徒〟となり、自らの〝情感〟を全面的に対象に投入すべきである。その上で訳者は原作にこめられた思想や情念を自らの言語に自由に置き換える権利を持つ。翻訳者は、まずは原作の〝信徒〟たれ、しかる後に〝叛徒〟たれ」と、翻訳におけるモチベーションの重要性を指摘した。
私は、日本にはもっと翻訳・紹介されねばならないもう一つの〝中国文学〟――「満洲国」の〝中国文学〟があることを、梅娘(メイニャン)という女性作家の例を挙げて語った。
梅娘は、日本と深くかかわり、その小説『蟹』が「大東亜文学者大会」で大賞を受賞したために、その後の人生を「漢奸」とされて苦しんだ作家である。のちに名誉回復され、一昨年、現役の作家として九十七歳の生涯を閉じた。私は梅娘文学の原型とも言うべき短編小説「僑民」を翻訳して追悼した。若き日、彼女は、かつて日本で「大陸雄飛」のブームを生んだ久米正雄の『白蘭の歌』を、原作の新聞連載を追いながら中国語に訳した。その直後に書かれた「僑民」には、『白蘭の歌』を翻訳した折の屈辱や苦悩が、ひそかにちりばめられている。
中国でも「満洲国」の文学の研究が本格的に始まるのは八〇年代に入ってからである。あの時期の文学を中国現代文学史にどう位置づけるかをめぐって激しい論争が展開されたが、やがて一九九九年に『中国淪陥区文学大系』(全七巻)が刊行され、「満洲国」を含む日本支配下の文学が、苦渋に満ちた言葉で文学史の空白を埋めていくことになる(「淪陥区」とは満洲事変以降、日本に支配された地域を指す)。
その後、日本でも「満洲国」の中国文学の研究が進められていくが、当時の作品の翻訳はまだ少ない。とりわけ、植民地支配と伝統的差別構造におけるジェンダー規範という二重の抑圧の中で生きなければならなかった女性作家たちの言葉は、植民地支配という形での「近代化」によって経験する内部の分裂と葛藤をも含み、さまざまなことを問いかけてくる。
そして彼女たちの生の軌跡は、私たちの歴史の傷痕をはっきりと映し出し、日中友好の原点に連れ戻してくれるにちがいない。<きし・ようこ 中国文学>
中国現代文学の翻訳紹介と作家の交流
―文化講演会に向けて
(NO.826 2015.2.1より)
中央大学教授
飯 塚 容
戦後間もなく、米軍占領下の日本で中国現代文学の紹介が始まった。その中心となったのは「中国文学研究会」の同人、竹内好、武田泰淳、岡崎俊夫らである。雑誌『中国文学』の座談会や作家論特集は、今日読み返しても十分面白い。座談会に作家の阿部知二が参加していること、作家論特集に佐々木基一が魯迅について、小田嶽夫が落華生(許地山)について書いていることも注目される。
雑誌『近代文学』も中国文学に強い関心を寄せていた。宮本百合子による『春桃』(落華生の表題作など、中国作家の短篇七作を収録)に対する書評は大きな反響を呼んだ。また、「中国文学研究会」の竹内好、武田泰淳、千田九一と『近代文学』の荒正人、佐々木基一、埴谷雄高による座談会は、両グループの親密さを物語っている。
その後、日本で刊行された翻訳全集類の編集においても、作家の関与が見られる。一九六〇年代の『中国現代文学選集』(全二〇巻、平凡社)には中野重治が、八〇年代の『現代中国文学選集』(全一三巻、徳間書店)には野間宏が加わっていた。七〇年代の『現代中国文学』(全一二巻、河出書房新社)に名を連ねる武田泰淳と高橋和巳は、作家でもあり学者でもあるところに重みがあった。
このように、日本の作家や評論家は一貫して隣国の文学に注目し、敬意を払ってきたのである。武田泰淳から黑井千次日中文化交流協会現会長まで、作家がいかに自身の中国観を作品化したかについては、張競氏『詩文往還 戦後作家の中国体験』という好著が出たばかりだ。作家たちが重ねてきた魂の交流の歴史は複雑で、大変興味深い。
中国現代文学紹介の第一のピークが戦後の十数年だとすれば、第二のピークは一九八〇年代初めから九〇年代前半までだろう。良好な日中関係と日本経済の好景気が、それを後押しした。まとまった翻訳紹介としては、前述の徳間書店の選集のほかに、『発見と冒険の中国文学』(全八巻、JICC出版局)、『新しい中国文学』(全六巻、早稲田大学出版部)、『現代中国の小説』(全四巻、新潮社)などがあった。
作家交流の歴史で言えば、日中文化交流協会は長年にわたって作家代表団の相互往来を続けてきた。また、今世紀に入ってからは、「日中女性作家会議」「日中青年作家会議」、日中韓三ヵ国による「東アジア文学フォーラム」という作家交流のイベントが開催されている。政治的な出来事の余波を受けて、思いがけず文化交流事業が突然中止になるなど、依然として中国との付き合いは一筋縄でいかない。何とか粘り強く、日中間の作家交流と作品の翻訳紹介が歩調を合わせて進む環境を作り上げたいものだ。三年ほど前、『コレクション 中国同時代小説』(全一〇巻、勉誠出版)を編集刊行したとき、辻井喬前会長からいただいた推薦の言葉を思い出す。「その国の人を理解するには、その国の人が書いた優れた文学作品を読むに限る」。〈いいづか・ゆとり〉
新しい年の新しい意味
(NO.825 2015.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
二〇一二年の尖閣諸島をめぐる問題の発生以来、日中両国の関係は悪化を続け、きわめて不安定な状態のまま月日が流れている。このままではどうなってしまうのか、と憂慮していたある日、日中文化交流協会の事務局職員として、一貫して両国の文化交流の仕事に取り組み続けて来た人に会った。年齢のこともあって今は事務局職員を退き、本協会の役員を務めている男性である。
こんな状態が続いて、この先どうなるのだろう――そう問いかけずにいられなかった。
ゆったりと笑みを浮かべたその人は答えた。これまでには、もっとひどい状態の時期がありましたよ。それを乗り越えてここまで来たのだから、大丈夫ですよ、今度も。しっかりと取り組んでいきさえすれば、行く手にきっと光は見えて来ます――。
日中国交正常化の時期から同じ仕事に携わって来たその人の言葉の内には、波風を孕みながらもゆったりと流れ続ける歴史の時間の横顔のようなものが隠されているかに感じられた。個々の出来事に一喜一憂するのではなく、より高い視点から、全体の流れを過たずに掴むことが出来たなら、この先の眺望を得ることも可能であるのかもしれない――不安を抱きながらも、その人の自信たっぷりの言葉に、ほっと息をつくことが出来る思いを味わった。
また、こんなこともあった。日中関係に深い関心を寄せるある政治家が、我々の仕事として日中関係改善に取り組んで、今具体的な仕事を進めることはなかなか難しいが、文化交流の営みにはそういった障害がないだろう。だからその方面の仕事に取り組んでいる人達は、今可能な文化交流の仕事を積極的に進めてもらいたい、と。
政治家というものが政治的事情の中で動かざるを得ないのは当然であろうけれど、そして政治が問題を抱えて動きが取りにくくなった時、文化交流面の友好を少しでも進めてもらいたいと考えるのは自然であるのかもしれないが、ただ「政治」と「文化」とを同じ盤の上で動かすゲームの駒の如くに扱う考え方がもしあるのだとしたら、ことはそう簡単ではないことを認識する必要があるだろう。「政治」と「文化」は別のものでありながら、どこかで深くつながっている。人類の長い歴史の中で、政治の結果が文化となり、また文化の力が政治を動かすことも考えられなくはない。
文化交流が良好な状態で進められている時には、そのあたりの事情は見えにくくなっているのかもしれない。
しかし国際関係に問題が生じて交流も進みにくいような困難な状況の中でこそ見えてくる課題があり、それへの取り組みが求められているともいえよう。
明けた年を、困難を乗り越えつつそこに新たな課題を発見し続ける、力のこもった年として受け止めたい、と祈念せずにいられない。〈くろい・せんじ 作家〉